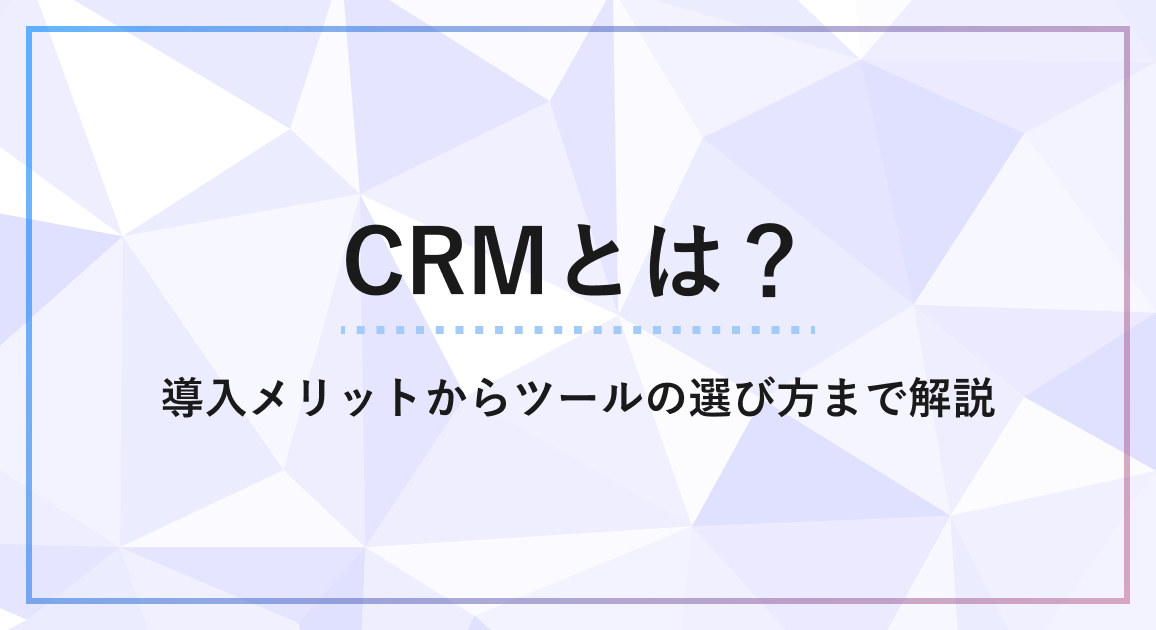- CRM
CRMの費用相場とは?タイプ別でわかる導入コスト・選び方・費用削減のポイント
公開日:
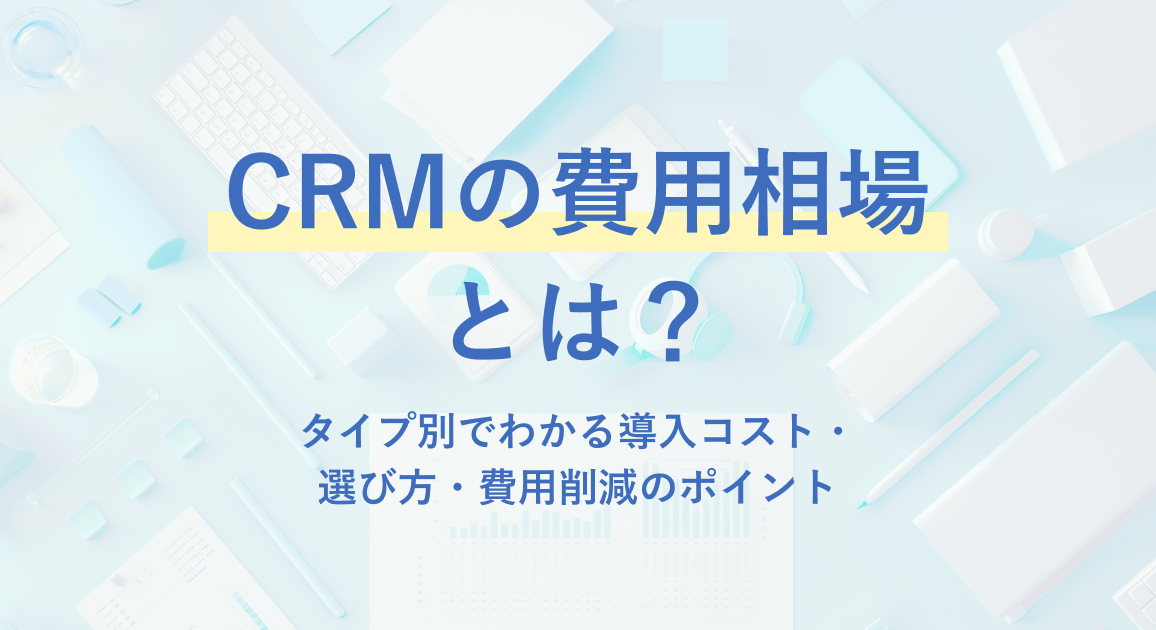
CRMの費用について検討する際は、価格の安さだけでなく機能性やサポートなど、さまざまな視点から判断することが大切です。
CRMには大きく3つのタイプがあり、それぞれ特徴と費用相場が異なります。タイプごとの特徴を理解しておけば、自社に合ったCRMを選ぶ際にも役立つでしょう。
本記事では、タイプ別のCRMの費用相場と、自社に合った選び方、導入コストを安く抑えるコツについて紹介します。
使いにくい顧客データの問題を解決
CRMとは
CRM(顧客関係管理)システムは、顧客情報を一元管理し、営業やマーケティング活動の効率化を支援するツールです。
顧客の基本情報や商談履歴、問い合わせ対応、購買履歴などのコミュニケーション履歴を集約・可視化することで、チーム全体で顧客対応の質を高められます。
CRMには大きく以下3つのタイプがあり、それぞれで費用や導入難易度が異なります。
タイプ | 特徴 |
|---|---|
クラウド型 | インターネット経由で利用。初期費用や運用負担が小さい。 |
オンプレミス型 | 自社サーバーに構築。セキュリティーを重視し、高度なカスタマイズが可能。 |
自社開発型 | 自社独自に開発。業務に合わせ最適化できるが、費用と期間は大きくなる傾向。 |
CRMについてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をぜひご覧ください。
CRMの導入にかかる費用の相場

CRMの導入にかかる費用は、導入形態や求める機能、運用体制によって異なります。
費用は「初期費用」と「ランニングコスト」の2つがあり、それぞれの相場を把握しておくことが重要です。また、コストは機能数、ユーザー数、サポート体制などにも影響を受けるため、単純な価格比較ではなく総合的な判断が求められます。
ここでは、主要な導入形態であるクラウド型、オンプレミス型、自社開発型それぞれの費用感を解説します。
導入形態 | 初期費用 | ランニングコスト |
|---|---|---|
クラウド型 | 無料~10万円程度 | 1ユーザーあたり月額1000円~1万円程度 |
オンプレミス型 | 50万~200万円程度 | 1ライセンスあたり月額5万~30万円程度 |
自社開発型 | 200万~500万円以上 | 保守・改修費が都度発生 |
クラウド型の費用相場
クラウド型CRMは、初期費用・運用コストを抑えて導入しやすいのが魅力です。
月額課金モデルが一般的で、自社の成長にあわせて段階的にユーザー数や機能を拡張できる柔軟性があります。
- 初期費用:無料~10万円程度(ベンダーにより初期設定サポート費用が発生する場合も)
- 月額費用:1ユーザーあたり1,000円~1万円程度(機能・プランにより幅あり)
中には無料プランから利用可能なCRMもありますが、多くの場合、営業支援機能やカスタマイズ性に制限があります。
そのため、利用人数や求める機能を明確にしたうえで最適なプラン選定を行うことが、コストを抑える鍵となるでしょう。
オンプレミス型の費用相場
オンプレミス型CRMは、自社サーバー上にCRMを構築・運用するスタイルです。
高いセキュリティ性や柔軟なカスタマイズ性を求める企業に選ばれていますが、初期費用はクラウド型に比べて高額になる傾向があります。
- 初期費用:50万円~200万円程度(サーバー構築、ソフトウェアインストールなど)
- ランニングコスト:月5万~30万円程度/1ライセンス(保守・アップデート費用を含む)
一括払いの導入コストは高めですが、既存のITインフラと統合したい場合や独自仕様のCRMが必要な場合などには有力な選択肢です。
特に中〜大規模企業、あるいはセキュリティ要件の厳しい業種での採用が多く見られます。
自社開発する場合の費用相場
自社開発型CRMは、自社の業務プロセスにフィットしたCRMをゼロから開発する選択肢です。
その分費用と期間は大きくなりますが、他のCRMでは対応できない特殊な要件に応えることができます。
- 開発コスト:200万円~500万円以上(要件定義、設計、開発、テスト、保守費用を含む)
- ランニングコスト:月額費用は発生しないが、保守・改修・運用に定期的なコストが必要
内製開発のためには社内に十分なITリソースや知見が求められます。
また、導入までの期間が長くなる点も考慮が必要です。
既存CRMのカスタマイズだけでは対応しきれない企業や、高度な業務プロセスを持つ企業に選ばれていますが、導入検討時は費用対効果の見極めがとても重要になります。
自社に合ったCRMの選び方4つのポイント

CRMは導入しただけで自動的に成果が出るわけではありません。自社の目的と現状に合ったCRMを選ぶことが、効果的に活用するための第一歩となります。
ここでは、選定時に押さえておきたい4つのポイントを紹介します。
1.自社の目的に合った機能が備わっているか
まず、自社がCRM導入で何を達成したいのかを明確にすることが不可欠です。
CRMに求める機能は業種や抱えている課題によって異なります。
例えば、新規営業を強化したい企業は商談管理やリード管理機能を重視し、既存顧客との関係を深めたい企業は過去の購入履歴や問い合わせ履歴、対応履歴などの可視化やアラート機能などが求められるでしょう。機能が多ければ良いわけではありません。必要な機能が使いやすく実装されているかが選定時の大きなポイントになります。過剰な機能は、コスト増と運用の負担の増加につながるため注意が必要です。
導入前に自社の業務フローと照らし合わせ、「必須機能」と「あれば便利な機能」とを整理しておくと、無駄のない選定ができるでしょう。
2.スタッフにとって使いやすいか
CRMは現場で日常的に使われてこそ効果を発揮します。
そのため、実際に操作するスタッフにとって使いやすいかどうかは、重要な選定ポイントです。
確認すべきポイントとしては、管理画面のわかりやすさや入力項目の整理度、スマートフォンやタブレットへの対応状況などがあげられます。特に、ITに不慣れなスタッフが多い場合は、設定の自由度よりも操作のシンプルさを重視しましょう。
導入前にトライアルやデモを活用し、現場スタッフの使用感を確認した上で判断するのがおすすめです。
3.費用対効果に見合うか
CRM選定では、初期費用や月額料金の安さだけではなく、業務改善の効果に見合った投資かどうかを検討することが大切です。
例えば、CRM導入によって一人あたり毎日30分の作業が削減できれば、5人チームで年間600時間の工数削減が削減されます。時給3,000円で換算すると、約180万円相当のコスト削減に相当します。
CRMが定着しなければコストだけが残る結果になりかねません。運用体制や社内教育まで含めて、「使い続けられるか」も見極めることが重要です。
4.サポートや拡張性が充実しているか
CRMは導入後も長期にわたり活用するため、サポート体制や拡張性の充実度が重要です。
具体的には、以下のようなポイントを確認しておくと安心です。
- 導入直後のトラブル対応や定着支援の有無
- 自社に合わせたカスタマイズや他ツールとの連携の可否
- 業務拡大に応じたユーザー数や機能追加の柔軟性
中長期での運用を想定する場合は、導入時のコストだけでなく、事業成長に合わせてCRMが拡張できるかできるかどうかも重視して選びましょう。
CRM導入にかかるコストを抑える2つのコツ

CRMを導入する際は、コストを抑えながら自社に最適な形で運用を軌道に乗せることが重要です。ここでは、導入コストを軽減するために押さえておきたい3つのコツを解説します。
1.トライアルで試してみる
トライアルを実施できるCRMなら、初期費用をかけずに使用感を確認できます。導入のハードルをできるだけ下げたい企業にとっては有効な方法です。
ただし、トライアル時には機能やユーザー数に制限が設けられているケースが多いため、自社の業務に必要な機能が利用できるか、事前に確認しておくことが大切です。
また、本格導入の前にチーム単位でトライアルを行えば、現場の意見を取り入れながら使い勝手を見極めることができ、導入後の失敗リスクを軽減できます。
2.最小限の機能とユーザーから始める
CRMは、必要最小限の機能とユーザー数から始めるのがおすすめです。
不要な機能を盛り込みすぎると、実際には使われずにコストだけが膨らんでしまう可能性があります。導入前に必須機能と「あれば便利」な機能を明確にし、しっかりと整理して選びましょう。
また、ユーザー数も、まずは営業チームなどの限られたメンバーで導入し、効果を確認したうえで段階的に拡張すると無駄がありません。
拡張しやすい料金プランやライセンス体系を選ぶことで、将来的な成長にもスムーズに対応できます。
まとめ
CRMは、営業活動や顧客対応の質を高め、業務全体の効率化に大きく貢献できるツールです。
CRMの効果を最大化するためには導入形態やコストだけでなく、CRMに入力される顧客情報の正確性や一元化が欠かせません。
顧客情報のバラつきや属人化が原因で、CRMを十分に活用できないケースは少なくありません。
このような課題を感じている方におすすめなのが、Sansanです。Sansanを利用することで、名刺情報を基にした正確な顧客情報がCRMに反映され、営業報告やマーケティング活動の質が高まります。
CRMの選定とともに、情報の質を支える基盤づくりにも目を向け、自社に最適な活用体制を整えていきましょう。
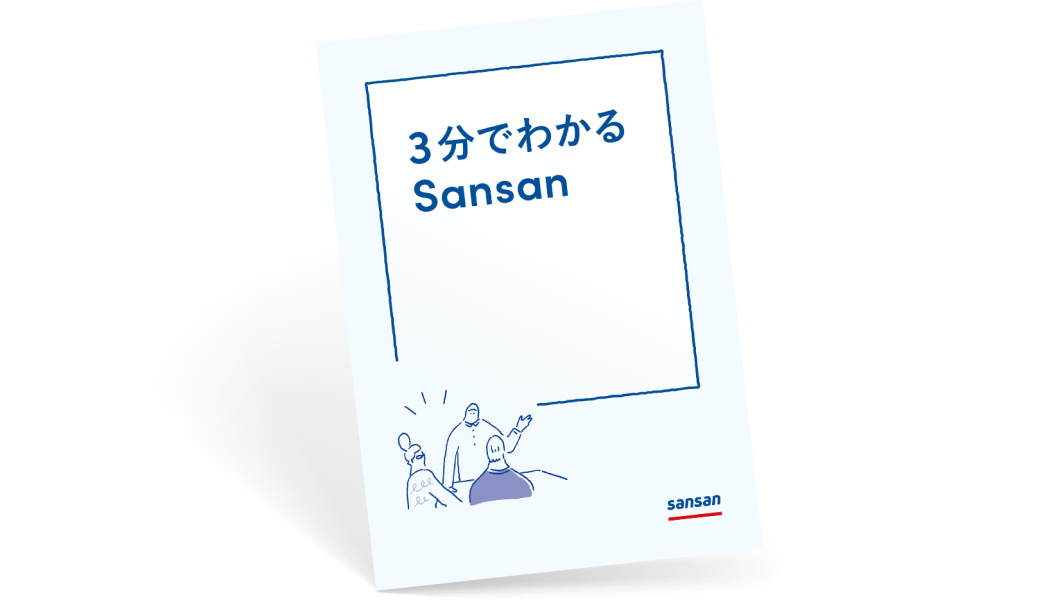
3分でわかるSansan
ビジネスデータベース「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部