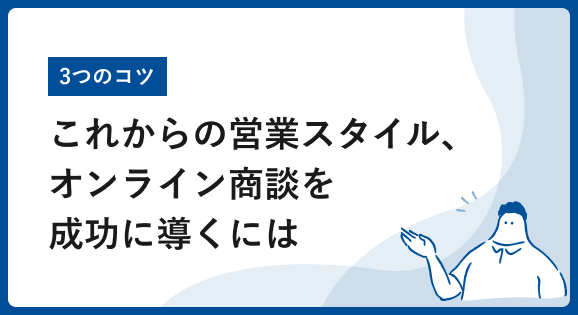- 営業ノウハウ
オンライン商談ツールのメリットやデメリットは?導入手順や活用のポイントを解説
公開日:
更新日:
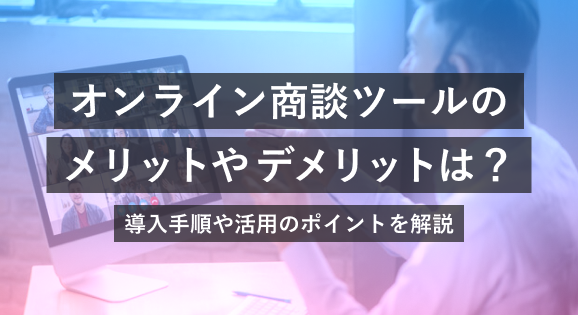
2020年4月の緊急事態宣言以降、対面商談は急速にオンラインへ移行し、いまやオンラインMTGが営業活動の標準手法となっています。本記事では、そのメリット・デメリットを整理し、商談効率を向上させるツールの活用法をご紹介します。
営業力強化で生産性向上を後押しする
オンライン商談とは
オンライン商談とは、ITツールを活用してオンライン上で商談を行う営業手法です。
従来は客先を訪問して対面で商談を行うのが一般的でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、オンライン商談が急速に普及しました。現在では、大企業だけでなく中小企業でもオンライン商談の導入が進んでいます。
オンライン商談には、対面商談やウェブ会議といくつかの違いがあります。
まず、オンライン商談は、対面商談ではかかっていた交通費や移動時間が不要です。これにより、コストを抑えながら効率的に商談を進められます。
また、オンライン商談に必要なITツールも、交通費に比べて安価なケースが多くなります。
ウェブ会議との違いとしては、専用アプリケーションが不要な点と言えます。
ウェブ会議は、専用アプリのインストールやログインが必要になることが多く、一方で、オンライン商談はブラウザ上で簡単に参加でき、顧客に負担をかけずに実施できます。
想定される参加人数も異なり、ウェブ会議が数十人〜数百人規模を想定しているのに対し、オンライン商談は1対1、もしくは数人規模で行われるのが一般的です。
オンライン商談のメリット
オンライン商談では、従来の訪問・対面での営業スタイルに比べて効率的に営業活動を行うことが可能です。
具体的なメリットは、以下があげられます。
移動時間とコストを削減
オンライン商談は顧客先への訪問が不要です。
そのため、移動にかかっていた時間を、商談準備や顧客フォロー、その他の重要業務に充てられるようになります。移動時間がなくなるため、1日あたりの商談件数を増やして成約数や売り上げの底上げにもつながるでしょう。
交通費の節約はもちろん、資料の印刷代などのコストも大幅に削減できます。
ビジネスチャンスの拡大
オンライン商談によって、ビジネスチャンスを広げられるのもメリットです。
訪問営業の場合、営業できる範囲は近隣エリアに限られます。全国展開を目指すには支社や頻繁な出張が必要となり、多大なコストがかかるでしょう。
この点、オンライン商談は地理的な制限を受けません。
日本全国だけでなく海外の顧客にもアプローチできるため、ビジネスチャンスを大きく広げられます。
これまで機会を逃していた新規開拓や顧客フォローなども実現できるでしょう。
リードタイムを短縮
オンライン商談によってリードタイムを短縮できるのもメリットです。
移動の必要がないオンライン商談は、日程が組みやすく手軽に実施できます。場所を準備する必要もないため、無駄に長い商談を避ける効果もあるでしょう。
また、複数の関係者が自席から参加できる点も特徴です。対面の商談であれば、個別に日程調整が必要だった複数のステークホルダーを一度にまとめやすいため、結果的にリードタイムの短縮につながります。
商談のスピードや件数が上がることで、営業担当者1人あたりの生産性が上がったり、顧客満足度が向上したりなどの恩恵も得られるでしょう。
ペーパーレス化を促進
オンライン商談はインターネット上で行われるため、紙の資料を用意する必要がありません。
デジタルデータをクライアントと共有しながら商談を進められるので、印刷コストや印刷作業にかかる工数を大幅に削減できます。訪問中の資料紛失による情報漏れのリスクも防げるでしょう。
オンライン商談ツールには、強固なセキュリティ対策が施されているため、データ管理の安全性も向上します。
アポイントが取りやすくなる
オンライン商談は、アポイントを取りやすくなるメリットもあります。
対面での営業に対して、売り込み感が強いと感じる人は一定数いるでしょう。心理的に圧迫感がある人は少なくありません。
移動や準備などの手間がかかる点も、アポイントが取りづらくなる要因です。
この点、オンライン商談であれば、自席から参加できるため商談のハードルを下げられます。移動時間がなくなるため「30分だけなら時間が取れます」といった要望にも対応しやすいです。
結果として商談の件数が上がるため、契約件数の向上も見込めるでしょう。
オンライン商談のデメリット
ここでは、オンライン商談のデメリットを見ていきましょう。
事前準備や相手に合わせた柔軟な対応が必要
使用するオンライン商談アプリやツールは、商談相手によって異なります。
そのため、事前にどのようなツールを使ってオンライン商談を望んでいるのか確認しておくと安心です。こちらからツールを指定する際は、インストール不要で利用できるサービスを活用するとよいでしょう。
人によっては、オンライン商談の事前準備にストレスを感じるケースもあります。
相手の負担を最小限にするためにも、相手に合わせた柔軟な対応を取るように心がけましょう。
インターネット環境に左右される
オンライン商談は、インターネットの通信環境に左右されるデメリットもあります。
商談中にインターネット接続が不安定になると、映像や音声が途切れてしまうケースもあるでしょう。場合によっては接続が切れてしまう可能性も考えられます。
このような事態を防ぐためには、双方で安定した通信環境を確保することが大切です。
手軽にできるためキャンセルされるケースも多い
オンライン商談はキャンセルされやすいデメリットもあります。
手軽にできるゆえ優先度が下がりがちなので、アポイントを取る際は近い日程を設定するのがおすすめです。また、前日〜当日にかけてリマインドを行うと、キャンセルリスクを下げるのに役立ちます。
信頼関係が形成しにくい
オンライン商談は、対面商談に比べて信頼関係を築きにくい側面があります。
画面越しのやり取りでは、相手との距離感が生まれやすく、会話も必要最小限になりがちです。商談中も表情や温度感などが伝わりにくく、打ち解けるまでに時間がかかる場合も少なくありません。
営業担当者から一方的に話を進めてしまうと、クライアント側は冷静な思考に戻りやすく、成約のハードルが高まる恐れもあります。
また、オンラインでは直接の名刺交換ができないため、今後のコンタクトに必要な正確な顧客情報を取得しづらいことも多いです。
顧客と良好な関係を継続するためにも、対面での相談にはない工夫が求められます。
オンライン商談ツールの導入手順

ここでは、オンライン商談ツールの導入手順について紹介します。
1.インターネット環境の整備
オンライン商談は、インターネット接続の安定性の確保が最重要です。
商談が佳境に入ったタイミングで接続が途切れると、流れが止まるだけでなく、顧客に不安や不快感を与えかねません。そのため、接続が不安定になりやすいWi-Fiやテザリングなどではなく、大容量の固定回線を使うのが理想です。
通信トラブルは信用問題にもつながりやすいので、事前に準備しておきましょう。
2.営業資料とシナリオの用意
インターネット環境を整えたら、次に営業資料とシナリオを準備します。
オンライン商談では、対面のような空気感や雰囲気の伝わり方が限定されるため、細かい意図や段取りを言葉で明確に伝える工夫が必要です。
例えば資料を提示する場面では、「これから資料をお見せしますので、少しお待ちください」といった声がけを挟むだけで、相手の理解度や安心感が大きく変わります。
リアルの“あうんの呼吸”が通じにくいのを前提に、「見せる+伝える」の両面から設計しておきましょう。
3.ツールの選定とテスト
商談で使用するツール選びも重要なポイントです。
オンライン商談ツールには多種多様なものがあり、機能や操作感が異なります。機能面に関しては、自社と商談相手の双方のニーズを満たすツールを選びましょう。ツールの選定が完了したら、事前に運用テストを行っておくと安心です。
カメラ、マイク、画面共有機能など、実際の商談を想定して一通り試しておくことで、当日のトラブルを防ぎ、商談に集中できる環境を整えられます。
4.商談
オンライン商談では、対面に比べて表情や身ぶり手ぶりが伝わりにくいため、ややオーバーリアクションを意識して相手に安心感を与える工夫が必要です。
また、対面よりも相手の理解度を把握しにくいので、要所ごとに「ここまでの説明でご不明な点はありませんか?」など、理解度を確認する声かけを増やすとよいでしょう。
加えて、営業担当者の名前を画面上に表示しておくと、初対面の商談でもコミュニケーションが生まれやすいです。
声はできるだけハキハキと明瞭に話し、資料や画面共有を適宜活用することで、情報伝達の精度を高められます。
5.アフターフォロー
オンライン商談が終わったら、アフターフォローを行います。
迅速にフォローアップしておくと、相手に商談内容が定着しやすいです。次のステップへスムーズに移行しやすくなるので、アフターフォローの重要度は高いと言えます。
アフターフォローの具体例は以下のとおりです。
- お礼のメールを送付
- 商談で使った資料や議事録の送付
- 関連資料や追加情報の送付
- 今後の流れについての提案
- 商談内容に関する質問の募集
このような項目を満たしておけば、オンライン商談に不慣れな人のニーズにも応えられます。
商談の成約率にも関わるので、商談後のフォローアップについても真剣に取り組むようにしましょう。
オンライン商談ツールを上手に活用するポイント
オンライン商談ツールに関する活用ポイントを紹介します。
1.事前テストは入念に行う
オンライン商談に入る前には、カメラとマイクのテストを必ず行いましょう。
単に映ればよい、声が聞こえればよいというレベルではなく、相手に不快感を与えないかまで確認することが重要です。
例えば、カメラ位置が高すぎたり低すぎたりすると、目線の高さに違和感が出て印象が悪くなります。カメラは自分の目線より少し高い位置にセットして、自然な印象を与えられるように工夫しましょう。
特にノートパソコンの内蔵カメラを使う場合は、見下ろすような角度になりがちなので注意してください。
また、マイクの感度も重要です。
感度が低すぎると声が小さく聞き取りづらくなり、逆に高すぎると音割れして耳障りになる可能性があります。多くのオンライン商談ツールには、マイクやカメラのテスト機能が備わっているので、最適な状態に整えておきましょう。
2.リマインドメールを送る
オンライン商談を行う際は、事前にリマインドメールを送るのが効果的です。
対面商談に比べて手軽に実施できるオンライン商談は、予定を忘れられたり、優先順位を下げられたりするデメリットがあります。アポイント取得時には相手が前向きだったとしても、時間がたつと熱量が冷めやすいのです。
例えば、商談の前日にリマインドメールを送ることで、予定を確実に思い出してもらえるだけでなく、相手の意識を高めるのにも役立ちます。
商談当日の温度差やドタキャンのリスクを減らすためにも、リマインドのメールを送信するようにしましょう。
3.リードタイムは短く取る
オンライン商談では、相手の熱量が時間とともに下がりやすいため、リードタイムはできるだけ短く設定しましょう。
アポイントはできれば当日、翌日、遅くとも翌々日までには設定するのが理想です。
また、商談後に顧客から問い合わせや相談があった場合も、可能な限り即日で返信するように心がけましょう。迅速に対応することで、相手の関心をキープしたり、成約率を高めたりなどの効果が得られます。
オンライン商談を行う際の注意点
オンライン商談の際に注意すべきポイントについて見ていきましょう。
オンライン商談スペースを作っておく
オンライン商談を成功させるためには、事前に商談スペースを整えておくことが重要です。
背景や周囲の音は、商談の印象に大きく影響します。整った環境を用意しておけば、相手に安心感と信頼感を与えられるでしょう。
具体的には、生活感のある物や不要な情報が映り込まないように配慮し、バーチャル背景の活用やカメラアングルの調整などを行うのが効果的です。照明を整えて表情をはっきり見せることも、相手に好印象を与えるポイントになります。
また、外部の音を遮断するために、ヘッドセットやノイズキャンセリング機能を備えたマイクの導入もおすすめです。
短時間の商談であっても、対面と同じ意識で環境を整えることが、成果につながる第一歩となります。
チェック項目 | 内容 |
|---|---|
背景 | 生活感のあるもの(洗濯物、雑誌など)は映らないように、企業の共通のバーチャル背景などを活用しましょう。 |
カメラ位置 | 目線と水平になるよう調整し、見下ろす/見上げる角度は避ける。 |
照明 | 顔に光が当たるように配置しましょう(自然光+リングライトがおすすめ)。 |
音声 | マイクのテストを事前におこないましょう。ヘッドセットやノイズキャンセリング機器の導入も検討してみるのもおすすめです。 |
通信環境 | 有線LANであれば、最低でもZoomなどが安定する速度(10Mbps以上)を確保できます。 |
話すスピードに気をつける
次に、話すスピードです。
通信環境によって遅延や切断が発生するため、早口で商談を進めてしまうと相手に内容が伝わらない可能性があります。
一文ごとに間を空けたり要点を区切って話したりなど、相手が理解しやすいように工夫するのもおすすめです。また、意識的に話すスピードを抑えると、相手の反応や表情の変化にも気づきやすくなり、双方向の対話を生み出しやすくなります。
オンライン商談の理想的な話し方のポイントは以下の通りです。
- 一文を短く、要点を明確にする
- 主語・述語をはっきり発音する
- 一つの話題ごとに「間」をとる
- 要所で資料を画面共有して補足する
- 話す内容は事前に整理しておく
オンライン商談では、聞き取りやすさが対面以上に商談の成否を左右します。意識的にスピードを調整しながら会話を進めましょう。
また、聞き返しや確認を恐れない姿勢も重要です。「音声が乱れたようなので、もう一度説明させてください」と一言そえるだけで、丁寧さと誠実さが伝わりやすくなるでしょう。
こまめに顧客をフォローする
オンライン商談では、対面での商談と比べて顧客をこまめにフォローする必要があります。
なぜなら、画面越しのコミュニケーションは、相手の温度感や理解度を把握しづらいためです。
商談中は、「ここまでの説明でご不明な点はありますか?」といった声かけを定期的に挟むようにして、会話の一方通行を防ぎましょう。また、相手の表情やうなずきが見えにくいため、反応を引き出す工夫も必要です。
例えば、オンライン商談中のフォローの例には以下があります。
- 「ここまででご不明な点はありませんか?」
- 「いまお伝えした内容、画面でもご覧いただけます」
- 「少し専門的でしたので、簡単に要点を整理しますね」
また、商談後にもこまめなフォローが成功のカギを握ります。商談が終わった後は以下の対応を実施するようにしましょう。
■ 商談後の対応チェックリスト
フォロー項目 | 目的 | タイミング |
|---|---|---|
議事録の送付 | 内容の再確認と認識のズレの防止 | 商談後24時間以内 |
提案書・資料送付 | 購入検討の材料提供 | 商談翌日までに |
お礼メール | 丁寧で信頼感のある印象を与える | 即日または翌朝 |
次回提案・打ち合わせ提案 | 次のアクション促進 | 商談中に予定調整 or 翌日 |
商談後、相手に議事録や提案資料などを速やかに送付すると、信頼感と商談の継続性をキープするのに役立ちます。
オンライン商談は、対面以上にフォローの頻度と質が重視されるため、丁寧な対応を心がけましょう。
まとめ
オンライン商談は、移動やコストの負担を抑えながら手軽かつ効率的にアプローチできる営業手法です。スピーディーな商談設定とリードタイムの短縮によって、商談数そのものを増やしやすく、結果として成約件数の増加にもつながるでしょう。
ただし、オンライン商談には「名刺交換ができず、正確な顧客情報を取得しにくい」「次の提案機会につなげづらい」などといった課題があります。
そのような方には、Sansanの活用をおすすめします。オンライン商談のデメリットをカバーし、成果につなげたいとお考えの方は、下記の資料をご覧ください。
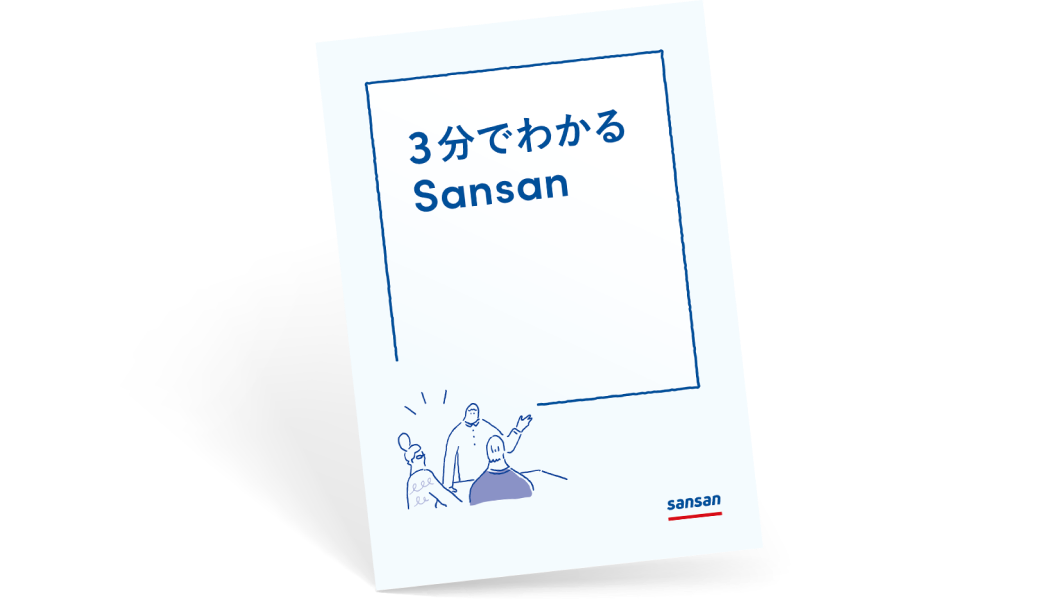
3分でわかる Sansan
営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部