- 営業ノウハウ
名刺は個人情報になる?個人情報保護法における取り扱いと管理方法を徹底解説
公開日:
更新日:
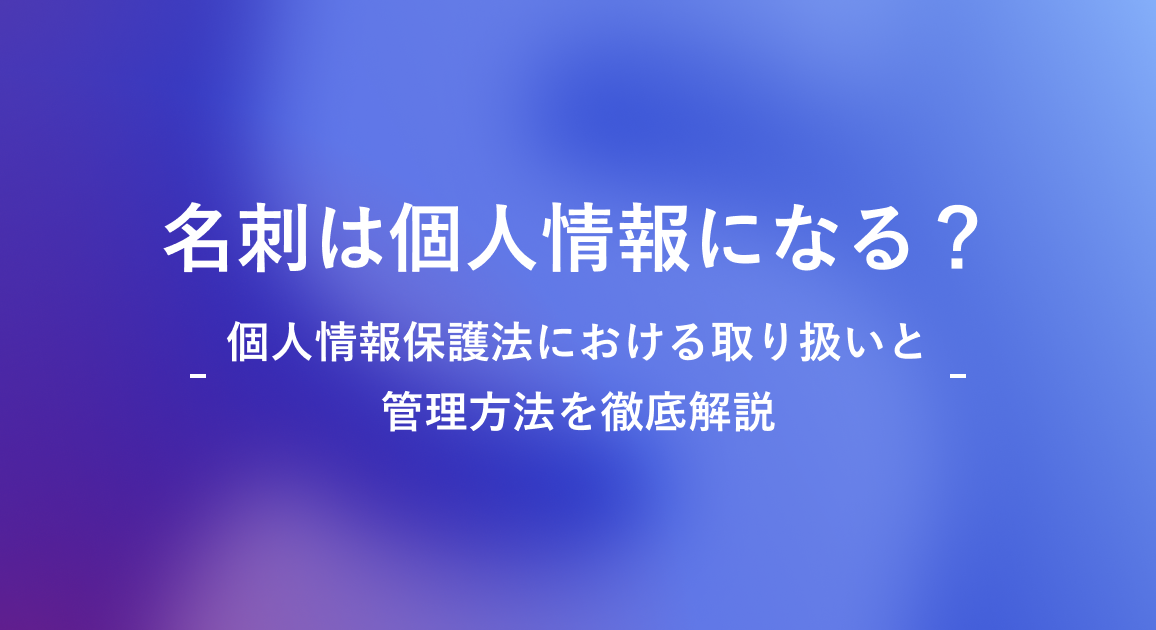
ビジネスシーンで欠かせない名刺交換。しかし「名刺は個人情報にあたるのか」「どのように管理する必要があるのか」と悩む担当者は少なくありません。
個人情報保護法の改正により、名刺情報の取り扱いも厳格化されており、不適切な管理は法令違反やトラブルリスクを高めます。本記事では、名刺の個人情報に該当する判断基準から、物理・電子両面での適切な管理方法、法令遵守と業務効率を両立する名刺管理のポイントを解説します。
名刺管理から始める営業DX
個人情報保護法上における名刺の位置づけ
個人情報保護法では、個人情報を「生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報」と定義しています。
つまり、名刺に記載される氏名、会社名、役職、電話番号、メールアドレスなどは、それぞれが単独、またはこれらを組み合わせることで特定の個人を識別できる情報となり得ます。そのため、基本的に名刺に記載された情報は個人情報に該当すると考えるべきでしょう。
個人情報保護法は2022年4月に改正法が施行され、情報漏えい等の報告・通知の義務化や越境移転に関する情報提供の充実、個人関連情報の第三者提供規制の創設などが盛り込まれました。
また、取り扱う個人情報の件数が少ない事業者は対象外となる決まりが改正されたことにより、すべての事業者が法の適用対象となりました。名刺管理においても、これらの改正内容を踏まえた対応が求められています。
名刺交換は一般的にビジネス上の連絡や関係維持を目的とした情報提供の同意を含むと解釈されますが、その利用範囲には制限があります。
マーケティング目的での活用や第三者への提供など、通常想定される範囲を超える利用には改めて本人の同意が必要となるケースがあるため、注意が必要です。
名刺が個人情報保護法の対象となるケースとならないケース
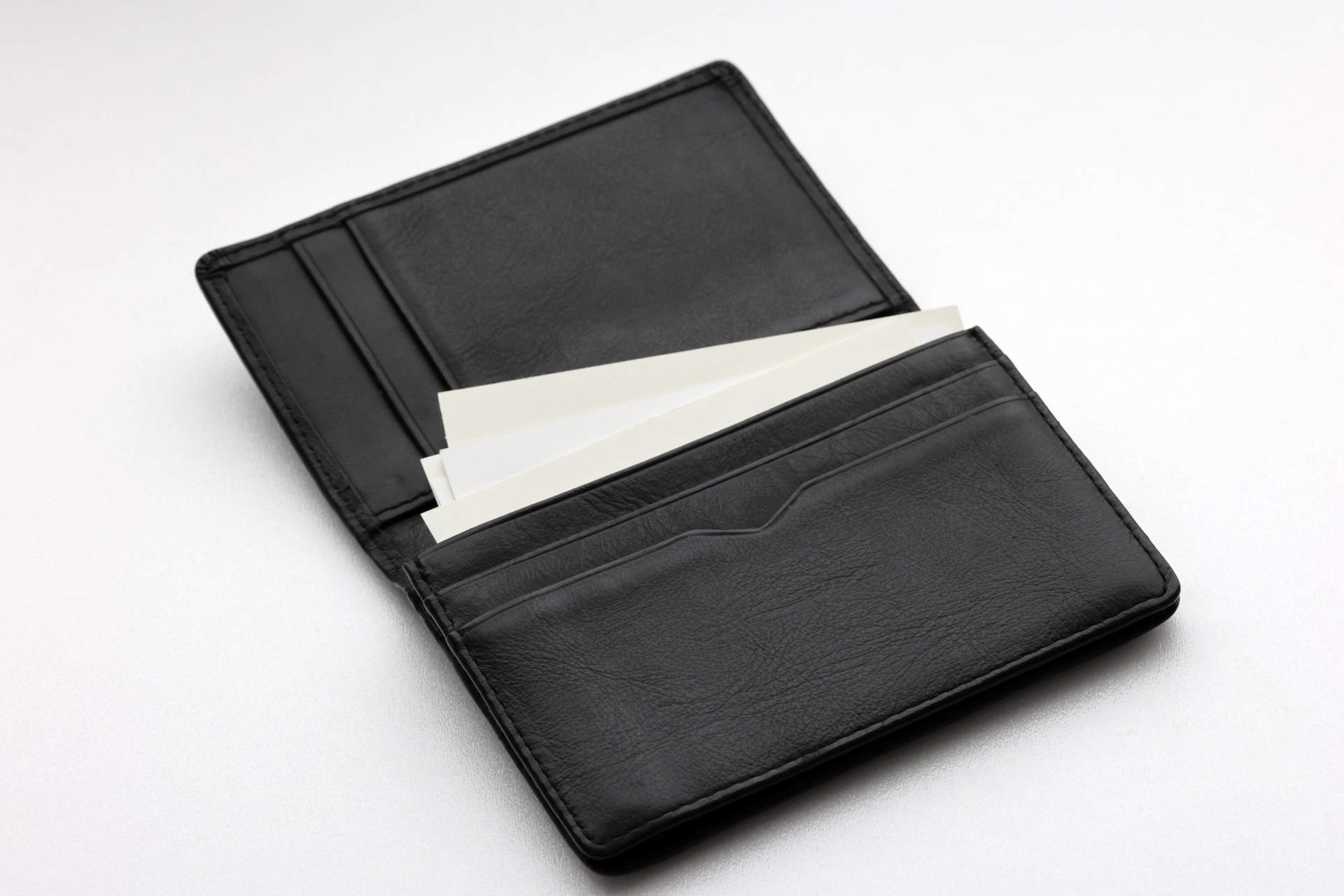
名刺が個人情報保護法の対象となるかどうかは、その管理方法や利用目的によって判断が分かれます。適切な対応をするためには、どのような場合に対象となるのかを正確に理解する必要があります。
名刺が個人情報保護法の対象となるケース
名刺情報をデータベース化して管理している場合、個人情報保護法の対象となります。企業で利用される名刺管理システムやCRMツールに取り込まれた名刺情報は、体系的に構成された「個人情報データベース等」に該当し、「個人データ」として扱われます。
このような電子化された名刺情報は検索性が高く、大量の情報を一元管理できるため、個人の権利利益を保護する観点から適切な管理が求められます。
企業内で共有されるエクセルファイルなどに名刺情報を入力して管理している場合も、検索可能な状態にあれば同様に保護の対象となります。
例えば、営業担当者が収集した名刺情報を一覧表にまとめて共有フォルダで管理している場合などが該当します。
2022年の法改正により、以前は対象外だった5,000件以下の個人情報を取り扱う小規模事業者も法律の適用対象となりました。
名刺情報をデジタルで管理する場合、アクセス制限や暗号化などの技術的安全管理措置が必要です。特に、クラウドサービスを利用する場合は、サービス提供者のセキュリティー対策や個人情報保護方針を確認することが重要です。
また、社内規定の整備や従業員教育といった組織的安全管理措置も求められます。
名刺が個人情報保護法の対象とならないケース
単発の名刺交換で受け取った名刺を特に整理せずに保管している場合、つまりデータベース化されていない形で保管されている名刺は、法律上の「個人データ」には該当しません。
例えば、営業担当者が自分用に保管している名刺ホルダーで、特定の検索機能がない場合などが考えられます。ただし、こうした名刺も業務上必要がなくなった場合は、適切に廃棄することが推奨されます。
完全に個人的な利用目的で収集・保管している名刺は、事業活動に利用しない限り法律の対象外です。
例えば、プライベートな交流会やセミナーで集めた名刺を個人的に保管している場合などが該当します。
ただし、当初は個人的な目的で収集した名刺情報でも、後に業務で利用する場合は法律の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。
破棄された名刺や情報価値を失った過去の取引先の名刺は、適切に処分されれば管理対象から外れます。ただし、廃棄する際には、シュレッダー処理や溶解処理など、個人情報が復元できない方法で処分することが重要です。
なお、法律の適用対象外となる場合でも、名刺には個人の連絡先など重要な情報が含まれています。社会通念上の配慮として、適切な管理を心がけることが信頼構築につながります。
ビジネスシーンにおける名刺情報の管理方法

名刺情報の適切な管理は、法令遵守だけでなく業務効率化にもつながります。ここでは、アナログとデジタル、それぞれの管理方法における具体的な実践ポイントを解説します。
アナログ管理
紙の名刺をアナログで管理する方法は、現在でも多くの企業で用いられています。基本的な管理方法ですが、個人情報保護の観点からいくつかの重要な注意点があります。
管理ポイント | 具体的な方法 | 留意点 |
|---|---|---|
保管場所の安全確保 | 施錠可能なキャビネットの使用 | 鍵の管理者を限定する |
整理・分類の方法 | 業種別・取引状況別の分類 | 検索可能な状態は法対象となる |
共有ルールの設定 | 閲覧記録の作成、複製制限 | 不必要な情報共有を避ける |
廃棄の手順 | シュレッダー処理、溶解処理 | 廃棄記録を残すことも重要 |
アナログ管理は導入コストが低く手軽である反面、紛失や誤廃棄のリスクがあり、在宅勤務やリモートワーク時には、必要なときに情報にアクセスできないという課題も生じています。
デジタル管理
名刺情報のデジタル管理は、検索性の高さや情報共有の効率化など、多くのメリットがあります。一方で、セキュリティーリスクへの対応が不可欠です。
管理ポイント | 具体的な方法 | 留意点 |
|---|---|---|
情報の電子化 | 名刺スキャナー、OCRアプリの活用 | データ化の正確性を確認する |
アクセス権の設定 | 役職・部署別の閲覧権限付与 | 定期的な権限見直しが必要 |
バックアップ体制 | クラウド保存、定期的なデータ複製 | 自動バックアップの設定確認 |
セキュリティ対策 | パスワード設定、暗号化 | 外部アクセスからの保護強化 |
システム選定 | 専用CRMツール、名刺管理アプリ | 自社規模に合ったツール選び |
デジタル管理は情報検索や共有が容易になる利点がある一方、導入コストやセキュリティ管理の負担が生じます。また、社員のITリテラシーによって活用度に差が出るため、適切な研修や運用ルールの整備も重要です。
名刺管理ツールを選定する際には、自社の業務フローや組織規模に合った機能を持つものを選ぶことが重要です。また、導入後の定着を図るためには、使いやすさや既存システムとの連携性も考慮すべきポイントとなります。
社内で名刺情報を保護するための取り組みポイント
名刺情報の適切な保護には、システムやツールだけに加えて、組織全体での取り組みが不可欠です。本章では、社内全体での取り組むべき方針策定や教育体制、情報漏えい対策などのポイントを解説します。
個人情報保護方針の策定と社内周知
企業として個人情報保護に対する姿勢を明確にするためには、具体的な方針を策定し社内へ徹底的に周知する必要があります。個人情報保護方針には、収集する情報の種類や利用目的、安全管理措置などを明記し、社内規定として整備する必要があります。
この方針を基に、部門ごとの具体的な対応手順を定めることで、組織全体での一貫した情報管理が可能になります。
- イントラネットや定期研修での方針共有と周知徹底
- 名刺情報を扱う部門への重点的な教育実施
- 法改正や社会環境変化に応じた定期的な方針見直し
また、従業員からのフィードバックを積極的に収集し、現場の実態に即した実践的な方針に改善していくことも大切です。
従業員教育とセキュリティー意識向上の取り組み
入社時の基本研修から部署別の専門教育まで、段階的かつ継続的な教育プログラムを実施することで、日常業務における適切な情報管理が定着します。特に名刺情報の取り扱いについては、具体的な事例を用いた実践的な研修が効果的です。
- 部署ごとの業務特性に応じた具体的なルール作成と定期確認
- 四半期ごとの自己点検シートや年次理解度テストの実施
- インシデント事例の匿名化共有によるリスク意識醸成
セキュリティー意識を効果的に高めるには、実際の業務に即した演習が有効です。ヒヤリハット事例を共有し、その原因と対策を解説することで現実的なリスク理解が深まります。
また、定期的な注意喚起メールやセキュリティー関連ニュースの配信によって、継続的な意識維持を図ることができるでしょう。
定期的な監査とルール見直し
個人情報保護の実効性を確保するためには、定期的な監査と評価が不可欠です。計画的な内部監査を実施することで、実際の運用状況と規定との乖離を把握し、早期に是正することができます。
特に名刺情報を大量に取り扱う部署では、より詳細な監査を行うことが推奨されます。
- 個人情報の取得・利用・保管・廃棄の各段階における手続き確認
- アクセス権限設定やセキュリティー更新状況の定期チェック
- 従業員の理解度や遵守状況の確認と評価
監査結果は必ず経営層に報告し、全社的な課題として認識することが重要です。発見された問題点に基づいてルールや体制を見直し、PDCAサイクルを回すことで継続的な改善が可能になります。
また、新たなセキュリティーリスクや脆弱性に関する情報を積極的に収集し、先手を打った対策を講じることも大切です。
情報漏えい時の対応フローと報告体制の整備
万が一の情報漏えい発生時に被害を最小限に抑えるためには、迅速かつ適切な対応が求められます。事前に明確な対応フローと報告体制を整備し、全従業員に周知しておくことで、緊急時の混乱を防ぎ、組織的な対応が可能になるのです。
特に初動対応の遅れは被害拡大につながるため、責任者と連絡体制を明確にしておくことが重要です。
- インシデント発生時の事実確認と暫定対策実施の手順策定
- 漏えい規模や影響度に応じた対応レベル判断基準の設定
- 社内、監督官庁、本人への連絡のタイミングと内容整理
効果的な対応体制を維持するためには、定期的な訓練やシミュレーションの実施が欠かせません。実際のインシデントを想定した対応訓練を行うことで、報告体制や対応フローの実効性を検証できます。
名刺情報の利用目的の明確化と限定
名刺情報の活用においては、利用目的を明確に設定し、その範囲内での利用を徹底することが重要です。個人情報保護法では利用目的の特定・通知が義務付けられており、目的外利用は原則として禁止されています。
そのため、取得時に想定される利用シーンを具体的に検討し、必要に応じて同意を取得する体制を整えることが必要です。
- 利用目的の社内周知とアクセス権限による利用制限
- 営業活動とマーケティング分析の適切な同意取得
- 第三者提供時の提供先・情報範囲の明示と同意確認
名刺情報の利用においては、「名刺を渡した相手が納得するか」という視点で判断すること重要です。当初の想定を超える利用が必要になった場合は、改めて通知や同意取得を行うプロセスを設けましょう。
適切な利用範囲を守ることは、法令遵守だけでなく、ビジネス上の信頼関係維持にも直結する重要な取り組みです。
まとめ
名刺情報は、管理方法によって個人情報保護法の適用対象となります。特に電子化してデータベース管理している場合や、検索可能な状態で整理している場合は、「個人データ」として厳格な管理が求められます。2022年4月の法改正により、個人情報を扱う事業者をすべて対象とするルールが施行されました。
企業のDX推進が進む現在、名刺のデジタル管理は避けて通れません。
ビジネスデータベース「Sansan」は、正確なデータ化と高度なセキュリティー対策を両立し、法令遵守と業務効率化を支援します。以下をご覧ください。
営業DXサービス「Sansan」が、政府の新たな セキュリティー評価制度「ISMAP-LIU」の第一号に認定 〜政府基準を満たす信頼性の高いサービスを継続的に提供~
名刺は単なる連絡先ではなく、ビジネス関係の入り口となる重要な情報資産です。法令を遵守しながら効果的に活用することで、顧客関係強化や業務効率向上を実現しましょう。
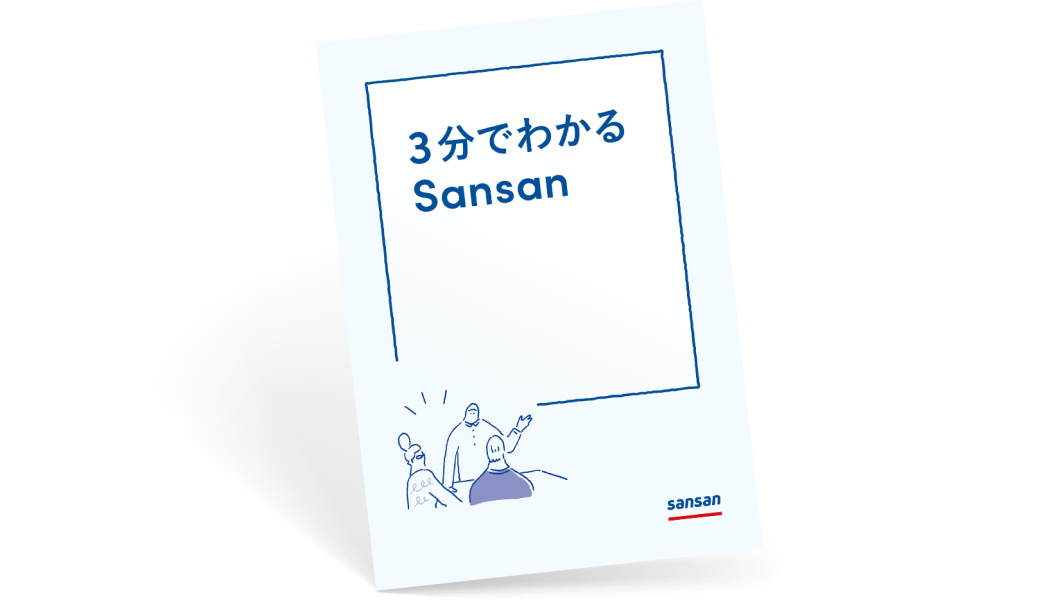
3分でわかるSansan
ビジネスデータベース「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部
