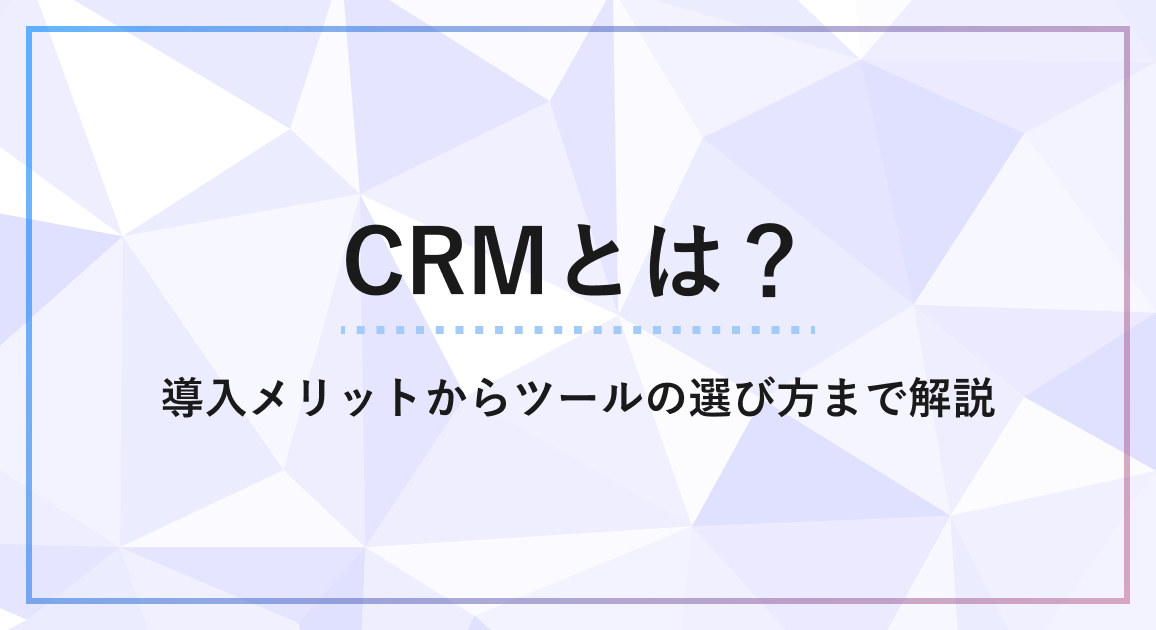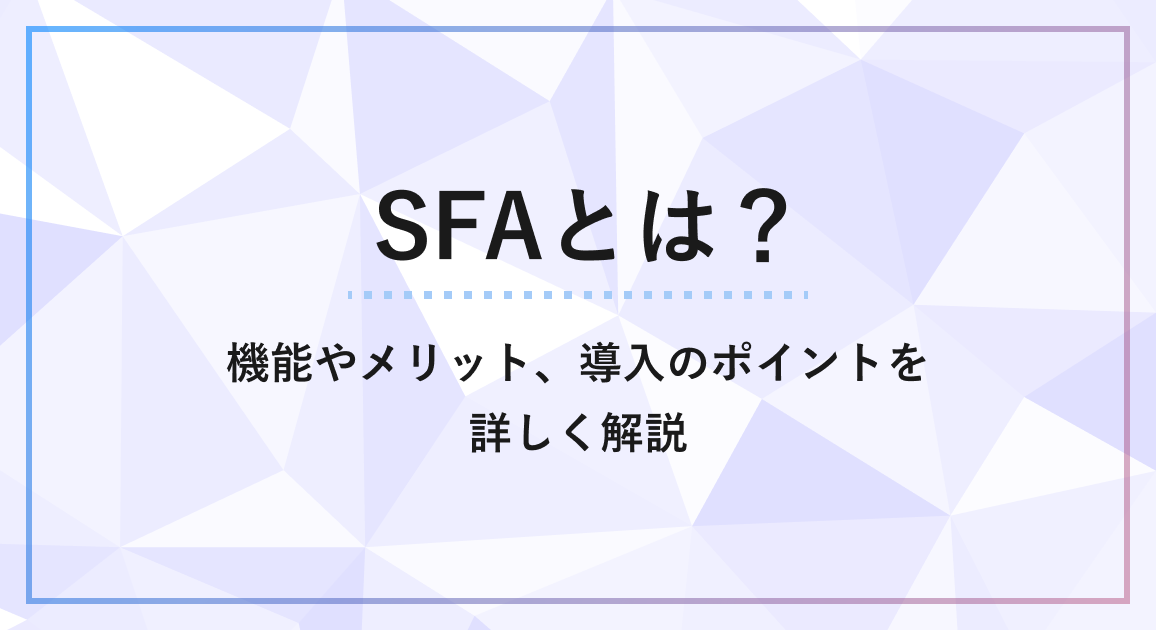- 営業ノウハウ
案件管理が必要な理由とは?ツールの種類・選び方と定着させる3つのコツ
公開日:
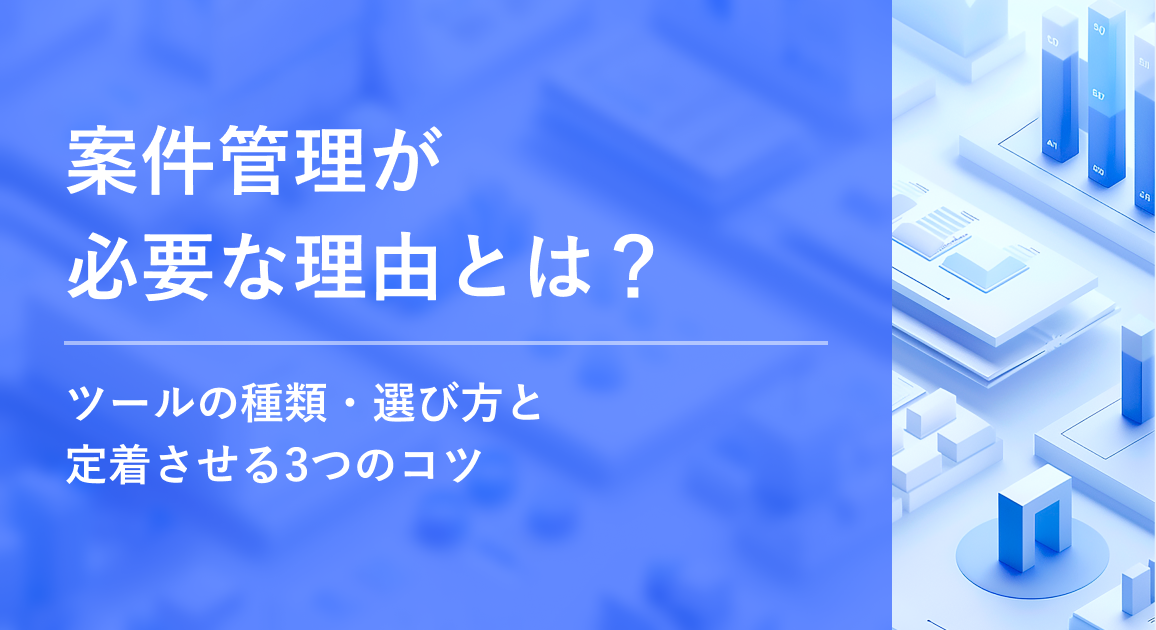
案件管理は、業務の進捗を正確に把握し、的確な戦略を立てるために欠かせない取り組みです。一方で「チーム内での情報共有がうまくいかない」「どの管理ツールを選ぶべきか判断が難しい」といった課題を抱える企業も少なくありません。
この記事では、案件管理が営業活動において重要とされる背景や、ツール選定のポイント、現場で運用を定着させるための工夫について解説します。
営業現場に定着する
案件管理とは

案件管理とは、顧客情報や営業の進捗状況を記録・整理し、営業活動を可視化する仕組みを指します。
リーダー層がチーム全体の動きを把握できるようになることで、次に取るべき戦略を立てやすくなります。また、案件の受注確度を高める営業活動の基盤としても欠かせない仕組みです。
案件管理に必要な項目
効果的な案件管理を行うには、商談の進捗や営業活動を正確に把握できる情報を整備する必要があります。
主な項目は以下の通りです。
- 顧客名/担当者名/案件名/提案内容/見積金額/受注予定日
営業フェーズ(例:初回訪問/提案中/交渉中/契約済み) - 受注確度(例:30%/70%/90%など)
これらの項目を事前に定義することで、チーム内で情報の整合性を保ち、営業活動の質とスピードが向上します。
案件管理が必要な4つの理由
ここでは、案件管理が必要な理由について見ていきましょう。
1.属人化を防ぐことができる
案件管理が行われていない現場では、情報が担当者個人の頭の中や手元のメモにとどまりやすく、担当変更時に引き継ぎがうまくいかないケースが頻発します。
必要な情報をチーム全員が確認できる状態にしておけば、担当者が不在の時でもスムーズな対応が可能になります。
さらに、営業のノウハウが共有されやすくなり、属人化しがちな営業活動を組織全体で推進しやすくなるのが大きなメリットです。
こうした仕組みが整うことで、組織全体の営業力を強化する土台が築かれます。
2.案件の受注確度を高められる
商談の進捗状況や提案内容、過去の対応履歴などを可視化することで、各案件に対して今後どのようなアプローチが必要か明確になります。
対応の遅れやフォロー漏れを防ぎ、成約機会を逃すリスクを減らせる点も大きな効果のひとつです。
また、受注確度の高い案件にリソースを集中させやすくなるため、営業活動全体の効率が改善され、結果的にチームの受注率上昇につながります。
案件の状況を正しく把握したうえで、戦略的に営業活動を展開できる環境が整うことが、受注確度向上に直結します。
3.営業プロセスを可視化できる
案件ごとの進捗状況が一目で確認できるようになると、「現状はどの段階にあるか」「停滞の要因は何か」が把握しやすくなります。
また、営業担当者ごとの活動内容も可視化されるため、業務の偏りや課題を明確に把握できるようになります。
営業プロセスを整理し可視化することは、再現性の高い営業手法の確立にもつながります。
結果として、チーム全体の営業力強化への貢献が期待できます。
4.データに基づいた判断が可能になる
感覚や経験だけに頼るのではなく、実際のデータをもとに意思決定ができることも、案件管理の大きなメリットです。
案件数や進捗、金額、受注確度などのデータを活用すれば、売上予測の精度が向上し、より先を見据えた戦略を立てやすくなります。
営業会議やチーム指導の場で客観的なデータを根拠として活用でき、判断のスピードと質が高まるため、マネージャー層にとってはより柔軟かつ戦略的な営業マネジメントが実現できるでしょう。
案件管理のツールの種類

次に、案件管理で利用する主なツールについて解説します。
Excel
Excelは、案件管理の導入初期によく活用されるツールです。
コストをかけずに導入でき、自由にカスタマイズしやすいといった特徴があります。
担当者ごとにシートを作成したり、関数やフィルター機能を活用して一覧性を高めたりと、柔軟な運用が可能です。
その一方で、複数人による同時編集やリアルタイムな情報共有には不向きであり、データの更新漏れやファイルが分散して管理が煩雑になりやすい課題があります。
特に小規模チームや案件数が少ない段階では有効な一方、組織拡大にともない運用の限界を迎えやすくなります。
タスク管理ツール
タスク管理ツールは、個人やチームの作業進行を可視化する目的で広く利用されており、案件単位のステータス管理にも応用しやすい点が特徴です。
代表的なツールとしては「Trello」や「Backlog」などがあり、カードやチケット形式で進行状況を整理できます。
業務フローやToDoを案件ごとに整理して管理できるため、対応漏れの防止にも役立ちます。
ただし、営業データや数値の分析には適していないため、案件ごとの金額や確度などの定量情報を扱いたい場合は、他のツールと組み合わせて運用することが前提となります。
CRM
CRM(顧客管理システム)は、顧客情報の管理に加えて、案件情報やコミュニケーション履歴をひもづけて管理できる点が特徴です。
顧客との接点や過去のやり取りが可視化されるため、関係性を深める営業活動をサポートします。また、案件情報も顧客単位で整理されるため、商談状況やパイプラインを俯瞰しながら、ステータスごとに発生するタスクの対応漏れを防ぎやすい仕組みが整います。
ただし、CRMの種類によっては、営業プロセスの詳細な管理や分析機能が限定される場合もあるため、選定時には必要な機能が備わっているか確認することが重要です。
SFA
SFA(営業支援システム)は、営業活動全体を管理・最適化することを目的としたツールであり、案件管理に特化した機能が充実している点が特徴です。
案件ごとのステータス、受注確度、商談履歴、アクション予定などを一元的に記録できるため、営業プロセスの改善や成果分析に活用しやすい環境が整います。
レポート機能やダッシュボード機能を備えたツールも多く、データに基づいたマネジメントの実践にも適しています。
一方で、機能が多岐にわたる分、初期設定や運用ルールの整備が不可欠です。導入後のサポート体制も、選定時の重要なチェックポイントになるでしょう。
案件管理ツールの選び方5つのポイント

案件管理ツールの選び方で失敗しないためのポイントを見ていきましょう。
1.目的にマッチしているか
案件管理ツールは種類が多岐にわたるため、まずは自社が解決したい課題や目指す運用スタイルに合った機能が備わっているかを確認することが重要です。
よくある目的の一例は以下のとおりです。
- 進捗を可視化したい
- チームで情報を共有したい
- 売上予測に活用したい
ツールの導入そのものが目的になってしまうと、現場に定着せず形骸化する恐れがあります。
「何のために使うのか」を明確にしたうえで選定を進めることが大切です。
2.使いやすい管理画面か
どれほど高機能なツールでも、操作が難しかったり画面が見づらかったりすると、現場で使われなくなるリスクが高まります。
画面のレイアウトや入力のしやすさ、一覧性など、営業担当者が直感的に操作できるかどうかは非常に重要なポイントです。
可能であればトライアル版を活用し、実際の入力から検索・更新までの一連の操作を体験し、現場にフィットするかを確認するとよいでしょう。
また、スマートフォンやタブレットでも快適に利用できるかどうかも、営業現場では重要な判断材料となります。場所を問わず情報の閲覧や更新が可能なツールであれば、外出の多い担当者にも定着しやすくなります。
3.他のシステムと連携できるか
営業活動は案件管理だけで完結するものではなく、顧客情報、商談履歴、売上管理など、さまざまな業務と密接に関係しています。
そのため、既存のMAツールやCRM、請求管理システムなどとスムーズに連携できるかどうかも、選定時の重要な基準となるでしょう。
APIの有無や連携先の柔軟性、標準機能での連携範囲などを事前に確認し、所属している企業のシステム全体としての業務効率化を見据えて選ぶことが大切です。
4.サポート体制が整っているか
ツール導入後のスムーズな運用を実現するには、サポート体制の充実も重要な選定基準となります。
例えば、設定方法の相談や、現場からの質問への対応、トラブル発生時のサポート体制などを事前に確認しておくと安心です。
また、オンボーディング支援や初期設定の代行サービスが用意されているかどうかも、現場にツールをスムーズに浸透させるうえで有効なポイントになります。
5.チームで情報を共有しやすいか
案件管理は、個人だけでなくチーム全体で活用することで、より大きな価値を発揮します。
例えば、案件の進捗状況をメンバー全員が確認できる、担当者以外でも次のアクションを把握できるといった共有性が求められるでしょう。
ユーザーごとの権限設定やコメント機能、通知機能など、チーム運用に適した機能が備わっているかを確認しておきたいところです。
案件管理で企業が抱えやすい課題

ここでは、案件管理において、企業が直面しやすい課題について解説します。
営業担当者がツールを使わなくなってしまう
案件管理ツールを導入しても、営業担当者が入力や更新を後回しにしてしまい、次第に使われなくなるケースがあります。
ツールが使われなくなる主な理由は以下のとおりです。
- 入力に手間がかかる
- 操作に慣れていない
- 使うメリットを実感できない
ツールが使われなくなると、情報が古くなり、管理の精度が低下するという悪循環に陥る可能性があります。
こうした状態では、ツール本来の効果が発揮されず、現場の運用負担ばかりが増えてしまいやすくなります。
データの入力基準が担当者によって異なる
案件の進捗や受注確度の判断基準が担当者によって異なると、データの信頼性が損なわれてしまいます。
例えば「確度80%」と入力されていても、その裏付けが各担当者の主観に依存している場合、数値の定義が統一されず比較や分析が難しくなるでしょう。
その結果、データに基づいた正しい意思決定が行えなくなり、案件管理全体の精度も低下します。
全社で統一された入力ルールや基準を設けないまま運用を始めてしまうと、このような課題が表面化しやすくなるため注意が必要です。
蓄積したデータを生かせていない
案件情報を入力しても、その後十分に活用されなければ、ツールが単なる記録システムとして形骸化してしまいます。
営業会議でデータが参照されていない、マネージャーが目を通していないといった状況では、現場のモチベーションも下がりやすくなります。
本来、蓄積されたデータは売上予測や進捗確認、失注要因の分析など、さまざまな場面で活用できる貴重な資産です。
しかし、それを生かす仕組みが整っていないと成果にはつながりません。
データが「使われることを前提」として運用されていないことが、活用不足の根本的な原因になっているケースが多く見受けられます。
案件管理を現場に定着させる3つのコツ

案件管理を現場に定着させるための3つの工夫を紹介します。
1.業務フローに入力作業を組み込んで習慣化する
案件管理ツールを定着させるためには、入力作業を特別な作業としてではなく、日常業務の一部として自然に組み込むことが重要です。
例えば「商談終了後30分以内に入力する」「夕方の業務整理の時間に更新する」といったルールを設け、具体的な行動とひもづけることで習慣化しやすくなります。
現場にとって無理のないタイミングや頻度を設定し、業務の流れと一体化させれば、入力作業も定着しやすくなります。こうした仕組みを整えることで、入力漏れや後回しが減り、ツールが継続的に活用される土台が生まれます。
2.案件情報の入力ルールをチームで統一する
ツールを有効に活用するためには、何をどのように入力するかを明確にしておくことが不可欠です。
受注確度の定義や営業フェーズの進め方など、人によって判断が分かれがちな項目については、チーム全体で事前に基準をすり合わせておく必要があります。
ルールは複雑になりすぎないよう、誰でも理解できるシンプルな内容にまとめ、チーム内で共有・確認する機会を定期的に設けるとよいでしょう。
入力の基準がそろうことで、ツールに蓄積されたデータに対する信頼性が高まり、マネジメントや営業改善にも効果的に活用できるようになります。
3.案件データをチームで共有して改善につなげる
蓄積された案件データは、入力されたまま放置せず、定期的にチームで確認して改善することが大切です。
営業会議の場で進捗状況を確認しながら「どこで停滞しているのか」「なぜ失注したのか」といった観点で話し合うことで、行動改善につながりやすくなります。また、成果を上げているメンバーの案件の進め方を参考にするなど、ナレッジ共有にも効果的に活用できます。
データを「見る → 話す → 改善する」というサイクルを定着させていくことで、案件管理が日常業務にしっかり根付いた文化として育っていきます。
まとめ
案件管理は、営業活動の状況を可視化し、成果を最大化するための重要な仕組みです。
適切に案件管理を行うことで、チーム全体の情報共有が進み、受注確度の向上や営業プロセスの改善につながります。
こうした効果を十分に発揮させるためには、自社の目的に合ったツールの選定、現場での運用ルールの整備、チーム全体への定着を意識した工夫が欠かせません。
特に、データを蓄積するだけでなく、チームで活用し改善に生かしていく姿勢が、案件管理の価値を高める鍵となります。
営業現場における顧客接点や案件情報を一元的に管理したい方には、Sansanの活用がおすすめです。
顧客情報の可視化や部門間でのスムーズな情報共有を通じて、営業活動全体の質とスピードを高めたいと考えている方は、ぜひ下記の資料をご覧ください。
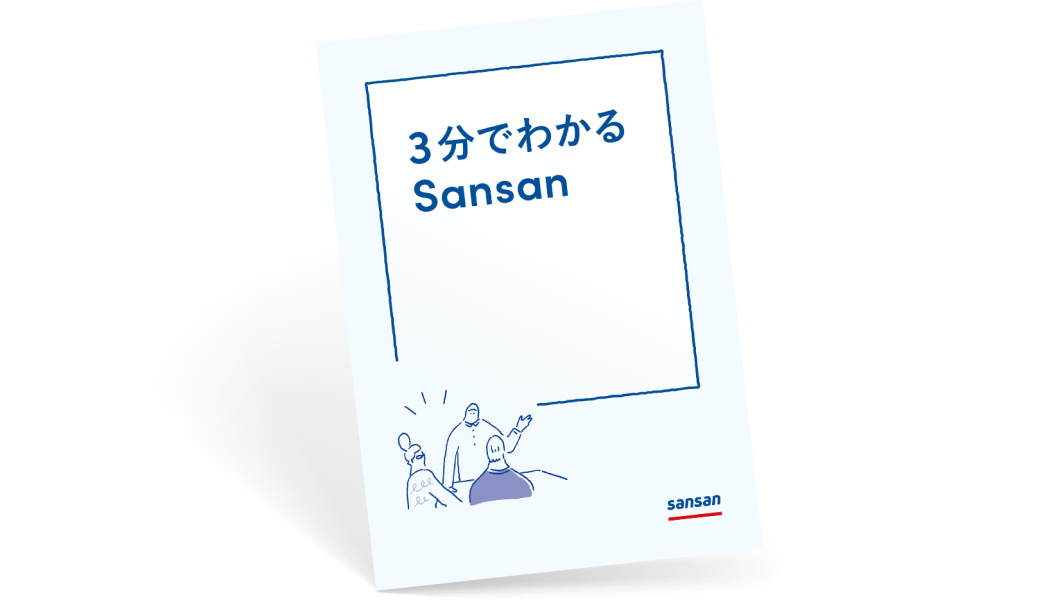
3分でわかるSansan
ビジネスデータベース「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部