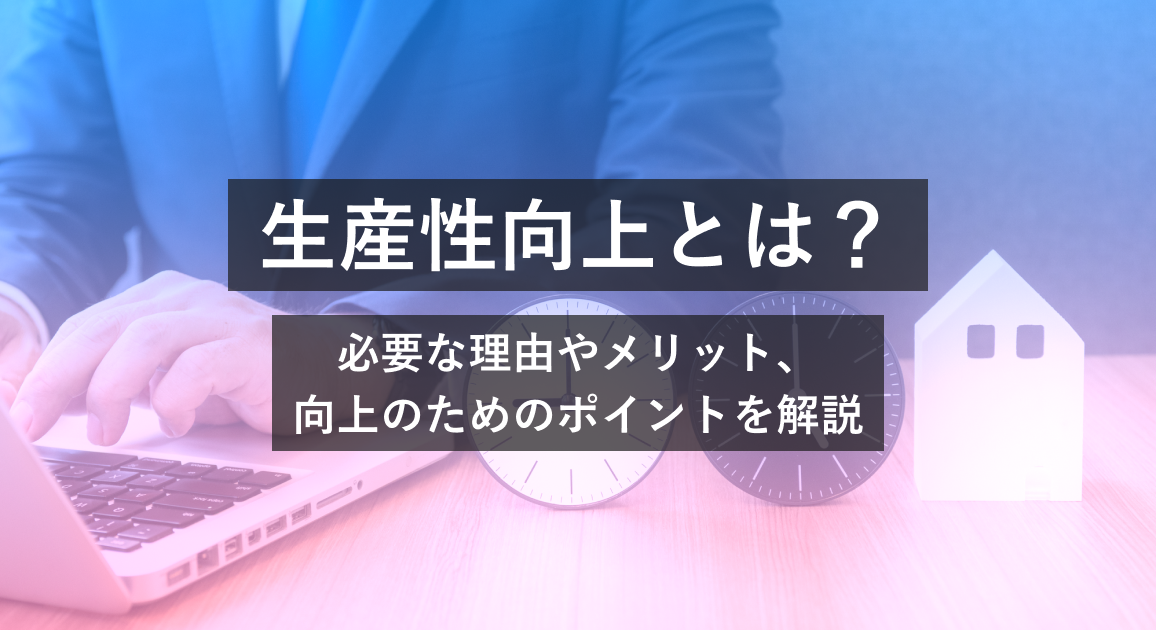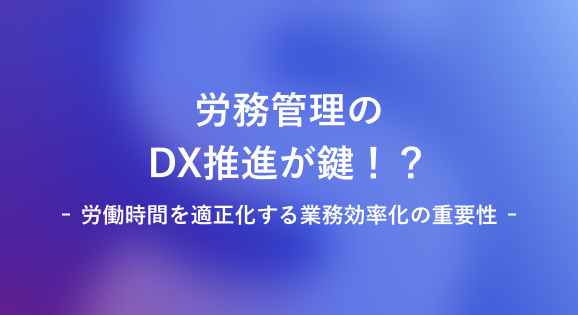- ビジネス全般
情報の共有とは?共有を行うためのプロセスやメリット、うまくいかない原因を解説
公開日:
更新日:
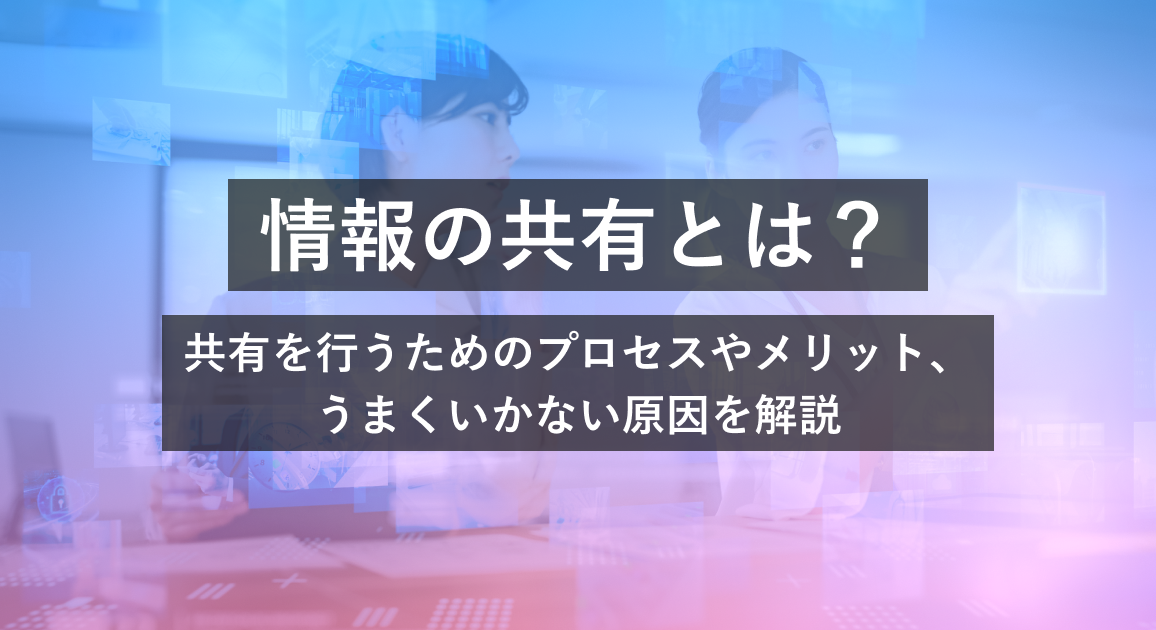
ビジネスにおける情報共有は、業務の効率化や、サービスの質向上をもたらします。しかし、情報共有の仕組みが整っていなかったり、従業員が情報共有のメリットを理解していなかったりすると、業務の無駄や属人化につながりかねません。
今回は、情報共有を行うためのプロセスやメリット、うまくいかない場合の原因を解説します。情報共有のあり方を見直したい方は、ぜひご一読ください。
情報共有で全社の営業力強化を後押しする
情報の共有とは

情報共有とは、各自が持つ情報を、他者と共有することを意味します。また、情報共有が適切に行われる状態を作ることを、情報の共有化といいます。
ビジネスにおいては、顧客情報や競合他社の動向、市場変化、技術といった事柄を共有することが重要です。各自が持っている情報を共有化することで、業務レベルが上がり、サービスや商品の質の向上につながるでしょう。
情報共有を行うためのプロセス
スムーズに情報共有を行うためには、以下のプロセスで進めていきましょう。
- 情報を収集・精査する
- 精査した情報を共有する
- 組織内で活用する
取り組む内容を一つずつ解説します。
情報を収集・精査する
まずはじめに、情報収集を行います。情報収集の方法としては、インターネットや書籍、関係者への聞き込みなど、さまざまな方法があります。
情報収集を実施した時点で、組織には膨大な情報が集まっていることでしょう。すべてを共有することは現実的ではないため、共有する情報を精査する必要があります。精査する際の手順は以下の通りです。
- その情報が正しいことを確認する
- 情報のカテゴリや時系列にしたがって整理する
- 短時間で価値がなくなるフロー情報と、時間が経過しても価値が変わらないストック情報に分ける
精査した情報を共有する
続いて、精査した情報を共有していきます。
情報共有は、単に情報を伝達するだけではなく、業務やプロジェクトなどの進捗を把握するという役割もあります。そのため、情報は常に更新し、最新の状態にしておくことが大切です。
各従業員の進捗を含めた情報を適切に共有するには、情報を管理し、伝達するための手段を検討しておく必要があります。そこでおすすめなのが、専用のシステムやツールの活用です。情報共有ツールを活用すれば、従業員の閲覧状況も確認できるため、社内での情報共有の状況を把握することもできます。
組織内で活用する
「情報収集・精査」「共有」までのステップによって、組織内で情報を活用できるようになります。共有された情報は、新たな情報を生み出し、それがさらに共有される好循環を作ります。結果として、組織全体の業務レベルの向上につながるでしょう。
情報共有のプロセスを運用し組織内で情報がうまく活用されない場合は、「収集・精査」のステップから見直す必要があります。
情報共有を行うメリット

組織で情報共有を行う主なメリットとしては、以下の5つがあげられます。
- 属人化を防げる
- 業務効率化や生産性の向上につながる
- 信頼関係の構築や維持につながる
- 新たな発見につながる
- 人材育成にかかる時間を短縮できる
一つずつ見ていきましょう。
属人化を防げる
情報共有を行うことで、属人化を防げるようになります。
属人化してしまうと、組織内で知識やノウハウが共有されないため、特定の担当者しかその業務に対応できない「属人化」の状況に陥ってしまいます。属人化の状況は、担当者の退職や不在時に業務が停滞してしまうため、事業活動において大きなリスク要因です。
一方で、組織内にナレッジを共有できれば、スキルや経験を広く浸透させることができ、チーム全体で業務に対応できるようになります。また、情報が均一化し、組織全体の業務レベルの向上や、トラブルの回避にもつながるでしょう。
業務効率化や生産性の向上につながる
情報共有によって、業務効率化や生産性の向上を図れます。必要な情報をすぐに共有できる環境が組織内で構築できていれば、必要な情報にたどり着くまでの時間を短縮し、意思決定の高速化や機会損失の回避が可能になるでしょう。
また、資料作成の際に誤った情報を用いたり、複数の部署間で伝達を行ううちに情報がゆがんでしまったりするミスを未然に防げます。
信頼関係の構築や維持につながる
情報共有によって、組織内における信頼関係の構築や維持にも期待できるでしょう。
部署内や従業員同士で情報共有ができていないと、認識のズレなどからいざこざが起きやすくなり、関係性の悪化につながる可能性があります。人間関係が悪くなると、業務がスムーズに進まなくなり、トラブルも起こりやすくなります。
従業員が普段から情報共有する意識を持っていれば、業務でのすれ違いを防ぎ、お互いの業務をフォローしやすくなるため、信頼関係の構築につながります。
新たな発見につながる
新たな価値を生み出すためには、既存の情報とこれまで知見がなかった情報をかけ合わせることが必要です。情報共有によって、これまで知らなかった知識を得ると、新たなアイデアを創出するきっかけになる可能性があります。
部署内はもちろん、異なる部署、あるいは社外とも情報共有を実施することで、今までにない視点からのアプローチが可能となり、新たな事業機会の創出につながるかもしれません。
人材育成にかかる時間を短縮できる
情報共有によって、業務の引き継ぎや人材育成に必要な時間を短縮することができます。
例えば、キャリアがある社員のノウハウをマニュアル化して共有すれば、新人の教育に役立てられるでしょう。
また、情報の共有化により、誰もが人材育成ができる体制が構築できれば、教育担当者がおらず、新任の育成が滞ってしまうといった事態を防ぐことができます。
情報共有がうまくいかない原因
組織内で情報の共有化がうまくいかない場合の原因としては、以下のようなものが考えられます。
- 情報の共有方法に関する仕組みが整っていない
- 従業員が情報共有する時間がない
- 情報共有のメリットが共有されていない
- 社内の雰囲気が悪い
一つずつ確認しましょう。
情報の共有方法に関する仕組みが整っていない
組織内で仕組みが構築できていなければ、情報の共有化を図ることが困難です。
例えば、スプレッドシートへの入力やメールでの情報共有は、入力作業や対応に手間や時間を要するため、従業員の負担が大きいです。従業員の負担が大きい共有方法では、情報の鮮度を保てなかったり、共有し忘れてしまったりという事態が生じやすくなります。
情報共有を活性化するためには、業務の隙間時間などに情報を入力できるよう、入力作業の負担を削減し、いつでも情報にアクセスできる仕組みの構築が欠かせません。タイムリーな情報の取りこぼしを防ぎ、情報共有を図るための手法やルールを選定することが重要です。
従業員が情報共有する時間がない
情報共有がうまくいかない原因として、従業員が多忙で、情報共有に充てる時間を作れないことがあげられます。たとえ情報共有の目的や重要性を理解していたとしても、時間の確保ができないと対応できないでしょう。
情報共有のルールや運用整備のほかに、従業員の業務作業の効率化や負担軽減、労働環境の改善などにも取り組む必要があります。情報共有の時間を確保できるような環境作りも欠かせません。
情報共有のメリットが共有されていない
従業員が重要性やメリットを理解できていないと、情報の共有化がうまく進みません。その場合、まずは情報共有に対する認識を変える必要があります。
組織で情報の共有化を推進する際に、マネジメント層やある一部の部署のみが重要性を理解しているものの、組織全体に浸透できていないことも少なくありません。従業員一人ひとりに情報共有を意識づけるためには、社内研修などを行うと良いでしょう。
すでに情報を共有するツールを活用している場合は、定期的に新しい機能や効果的な使い方などをレクチャーする勉強会などを開催するのも一つの方法です。ツールの活用性を高められるだけでなく、情報共有の重要性を再認識させることもできるため、さらなる生産性の向上が期待できるでしょう。
社内の雰囲気が悪い
そもそも社内の雰囲気が悪く、従業員間のコミュニケーションで問題が起きている場合も、情報の共有化が滞りがちです。
将来的なトラブルを防ぐためには、失敗やミスを報告することが重要です。しかし組織内で信頼関係が築けておらず、失敗を責められる風潮がある場合は、ミスやトラブルを隠そうとする心理が働いてしまう恐れがあります。
また、従業員同士でお互いをライバル視する雰囲気があると、有用な情報を手に入れても、共有せずに自分のみでとどめてしまう可能性もあるでしょう。
情報共有を効率化させるポイント

会社内で情報共有を効率化させるには、以下の6つのポイントを意識しましょう。
- 情報共有を従業員の評価に含める
- 社内のコミュニケーションを活発化する
- 情報共有のルールや仕組み作りを行う
- 情報共有の重要性について社内教育を行う
- 情報共有の時間を確保する
- ツールを導入する
それぞれ紹介します。
情報共有を従業員の評価に含める
従業員に情報共有を促す方法としては、情報共有を評価項目に含めることがあげられます。
例えば、情報共有した回数を評価項目の一つにすれば、情報共有する動機を作ることができるでしょう。情報共有を評価対象とする場合は、情報の中身や質ではなく、共有した行動そのものを評価することがポイントです。
積極的に情報共有を行ったことを評価すれば、ささいな情報や、自身の失敗についても共有されるようになり、結果として効率よく多くの情報を収集できます。従業員が情報共有によってメリットが得られる仕組みを作り、情報共有の効率化を図るのも一つの手段です。
社内のコミュニケーションを活発化する
社内のコミュニケーションが活発化することで、情報共有しようという雰囲気が生まれやすくなります。コミュニケーションを活発化するには、部署や会社全体でのイベントやチームなどでミーティングを実施するのがおすすめです。例えば、部署内で定期的にミーティングを行ったり、上司との1on1ミーティングを行ったりすると良いでしょう。
失敗やミスが許されず報告しづらい環境や、同僚を競争相手と認識して情報を遮断する雰囲気がある場合は、まず社内の環境を変えるように意識することが大切です。チーム全体のコミュニケーションが取りやすくなれば、ミスやトラブルも気軽に話せるようになり、情報共有も活発化するでしょう。
情報共有のルールや仕組み作りを行う
効率的に情報を共有するには、ルールや仕組みを明確化する必要があります。
例えば、「どのような情報を共有すべきか」「どのフォルダーに情報を格納して共有するのか」「情報を共有するタイミングはいつか」といったルールを詳細に設定し、社内に周知しましょう。
また、報告すべき内容か判断に迷ってしまうと、情報の共有漏れや情報の鮮度も低くなってしまいます。情報共有のルールを策定したら、運用や仕組みに対する不明点を質問できる問い合わせ先を用意しておきましょう。
情報共有の重要性について社内教育を行う
情報の共有化を図るには、すべての従業員に重要性を理解してもらうことが欠かせません。情報共有に対する理解を深めるには、社内教育を行うのも一つの手段です。
情報共有しやすいシステムを導入し、仕組み化を推進したとしても、従業員が重要性を把握していなければ、効率的に情報共有することができません。重要性を認知させるためには、市内教育をとおして、情報共有を行う目的や、実施する具体的な効果を伝えましょう。
情報共有の時間を確保する
業務過多など従業員が情報を共有する時間を確保できていない場合は、各従業員の業務状況を把握し、改善する必要があります。「業務量に偏りがある」「業務の圧迫でルール通りに運用できていない」など、情報の共有化を妨げている課題を洗い出しましょう。
発見した課題や原因にあわせて、業務フローの見直しや人員の補充、運用方法の改善などの対策を講じることが大切です。場合によっては、組織の体制や労働環境の見直しが必要となります。
ツールを導入する
情報共有を円滑に行うには、ツールの導入が効果的です。ツールを導入することで、情報を集約し、一元管理できるようになります。情報へのアクセスが容易となり、鮮度の高い情報をスピーディーに共有することが可能です。
情報の共有を図る際に役立つツールとしては、以下の5つがあげられます。
- ビジネスチャット
- SFA・CRM
- マニュアル作成ツール
- タスク管理ツール
- 名刺管理ツール
これらのツールを使えば、蓄積した情報の中から、必要な情報を検索機能で抽出できるので、効果的に情報をビジネスで活用できるようになります。また、編集制限機能や保護機能を活用することで、情報が歪曲して伝わることや、紛失のリスクも回避できます。
まとめ
情報共有とは、従業員が持つ情報を組織内で共有することです。適切に情報共有が行われることで、属人化の防止や業務の効率化、生産性の向上が期待できます。
組織で情報の共有化を図るには、従業員に情報共有するメリットを理解してもらい、共有しやすい風土や環境を構築することが重要です。
ビジネスにおいて情報共有を成功させる方法として、情報共有が簡単にできるツールの導入があげられます。
ビジネスデータベース「Sansan」は、従業員が持っている名刺から顧客情報をクラウド上で一元管理し、常に最新の状態で共有が可能です。メールや電話、商談の情報を全社に共有して活用するといった使い方もできます。密接な情報共有によって業務やサービスの質向上に寄与するため、ぜひご活用ください。
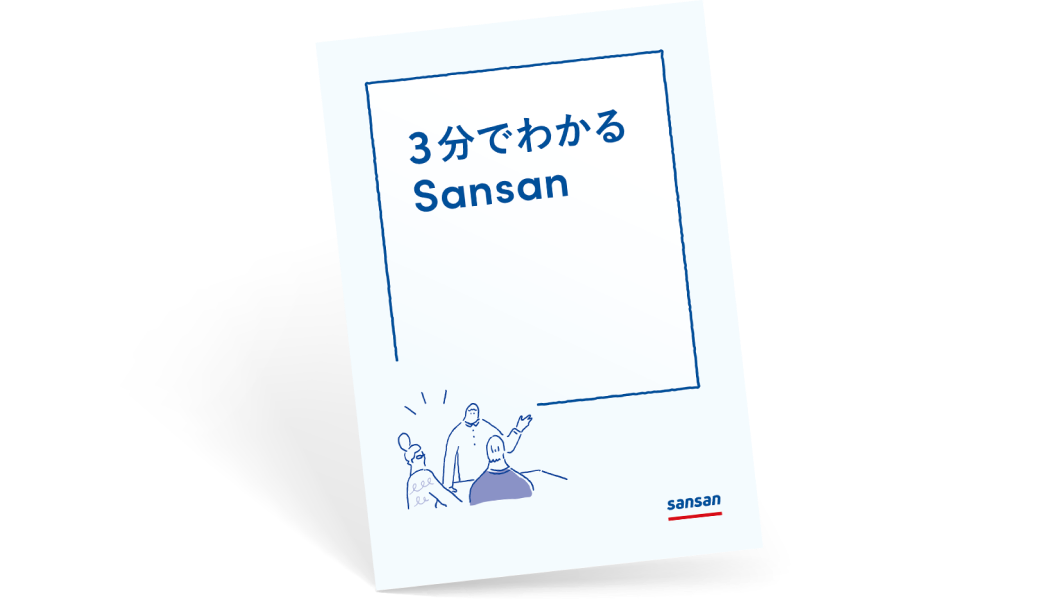
3分でわかる Sansan
ビジネスデータベース「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部