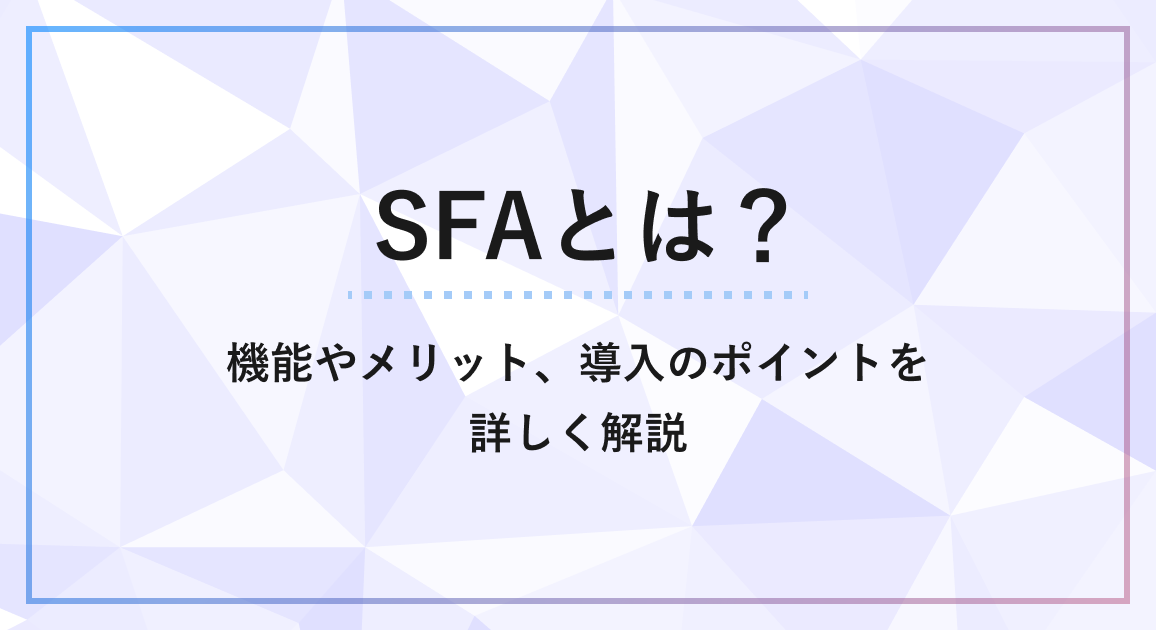- SFA
SFA連携のメリットとは?CRM・MAとの違いやスムーズに連携するコツを解説
公開日:

SFAはCRMやMAなどのシステムと連携することで、より真価を発揮します。しかし、闇雲に他システムと連携しても、入力の手間が増えるだけでビジネスの成果には貢献しません。システムの連携による効果を高めるには、自社に合ったツールの選定やルールの策定などが重要です。本記事では、SFA連携のメリットや、課題ごとに適したシステムの連携方法について解説します。
SFA(営業支援システム)とは
SFA(Sales Force Automation)は、営業活動の可視化と効率化を目的に導入される営業支援システムです。
商談の進捗状況や顧客との接点情報などを一元管理し、顧客対応や案件管理を効率化します。営業データの可視化と共有が進むことで、営業プロセスの標準化やマネジメントの質を向上しやすくなるでしょう。
また、SFAは売上予測や受注確度の把握にも貢献します。
属人化を防ぎ、チーム全体で成果を上げやすい営業体制の構築が可能になるのがSFAの特徴です。
営業部門の生産性向上に加えて、売上予測や受注確度の見える化により、経営層の意思決定にも役立つでしょう。
SFA/CRM/MAそれぞれの違い
SFA、CRM、MAは、いずれも顧客に関わる業務を支援する重要なツールですが、以下のように目的や機能には明確な違いがあります。
- SFA(営業支援システム):営業活動の進捗管理と行動履歴の可視化
- CRM(顧客関係管理):既存顧客との関係性や履歴の管理
- MA(マーケティングオートメーション):見込み顧客の獲得・育成の自動化
SFAは、営業プロセスの進捗管理に特化したシステムです。
商談活動やアポイント履歴といった営業現場の行動データを可視化・記録する役割を担い、営業活動の効率化と標準化をサポートします。
CRMは、既存顧客との関係性を深めることを目的とした情報管理ツールです。
問い合わせ対応や契約履歴といった顧客とのやり取りの履歴を管理し、継続的な関係構築や満足度向上に活用できます。
MAは、見込み顧客の獲得から育成を自動化するツールです。
Webサイト訪問やメール開封といった行動データをもとにリードをスコアリングし、最適なタイミングで営業担当者に引き渡す役割を果たします。
SFA連携するのにおすすめのツール

SFAは単体でも営業活動の効率化に役立ちますが、他のツールと連携することで、より大きな効果を発揮します。
ここでは、SFAと組み合わせて活用したい代表的なツールと、それぞれの連携メリットについて見ていきましょう。
CRM(顧客関係管理)
CRM(Customer Relationship Management)は、顧客との関係性を管理・強化するためのツールです。
CRMで管理している顧客の基本情報や問い合わせ対応履歴、SFAの商談履歴などをまとめて管理できるため、情報の更新漏れや重複が発生しにくくなります。その結果、引き継ぎや社内共有が容易になり、営業活動に必要な背景情報を即座に把握できるようになります。
これにより、提案の質や対応スピードの向上が期待できます。
MA(マーケティングオートメーション)
MA(Marketing Automation)は、見込み顧客の獲得や育成を自動化するツールです。
MAで収集したリードの行動履歴やスコアリング情報をSFA側に反映することで、営業は優先的にアプローチすべき顧客を見極めやすくなります。
例えば、資料ダウンロードやメール開封といった行動をトリガーに、タイムリーかつ適切なアプローチが実現可能です。
また、MAとSFAを連携することで、マーケティング部門と営業部門の情報共有が強化され、見込み顧客の育成から成約までの流れがよりスムーズになるでしょう。
名刺管理ツール
名刺管理ツールは、営業担当者が交換した名刺情報をデジタル化し、顧客情報として管理・活用するためのツールです。
営業担当者が交換した名刺情報をSFAに自動で取り込むことで、リード情報の入力漏れや情報の抜けを防止できます。顧客との過去のやり取りや関係性といった接点情報も可視化され、チーム全体での共有が可能です。
リードの初期段階からSFAに記録されるため、分析や再アプローチにも生かせます。
グループウェア・カレンダー
グループウェア・カレンダーは、社内のスケジュール管理や情報共有をサポートするツールです。
商談スケジュールや打ち合わせ予定をSFAと連動させることで、行動履歴や予定の一元管理が可能になります。営業担当の稼働状況や予定をチームで把握しやすくなるため、営業戦略の立案やリソース配分がスムーズになるでしょう。
社内での情報共有も効率化されるため、報告業務の工数削減にもつながります。
チャット・社内コミュニケーションツール
チャット・社内コミュニケーションツールは、社内の情報伝達やコミュニケーションを迅速に行うためのツールです。
SFAの更新情報や案件進捗をチャットツールに自動通知することで、営業活動の変化を関係者に迅速に伝えられるようになります。
意思決定や対応スピードが向上できるため、部門横断での情報連携が強化できます。
SFA連携によるメリット

ここではSFA連携によって得られる主なメリットを見ていきましょう。
情報の一元管理による業務の効率化
SFAを関連システムと連携すると、業務を効率化できるメリットがあります。
名刺情報や商談履歴、顧客の対応状況などが複数のツールに分散している状態では、確認作業やデータ入力に余計な手間がかかり、対応漏れのリスクが高くなりやすいです。
SFAとCRM、グループウェア、チャットなどを連携することで、これらの情報が一カ所にまとまり、必要な情報にアクセスしやすい環境が整います。
その結果、情報収集や転記作業に費やしていた時間を削減でき、営業担当者は本来の業務である顧客対応や商談活動に集中できるようになるでしょう。
営業プロセスの標準化と属人化の防止
SFAを連携すると、営業プロセスの標準化と属人化を防止できるメリットもあります。
営業活動が個人に依存していると、担当変更や異動の際に、重要な情報が失われるリスクがあるでしょう。
SFAに加えて名刺管理やメール履歴などを連携しておけば、誰がどの顧客とどのようなやり取りをしてきたかが可視化され、引き継ぎや共有が容易になります。
個人のノウハウに依存しなくなるため、チーム全体で再現性のある営業プロセスを確立しやすくなるでしょう。
結果として、組織としての営業力の底上げにつながります。
売り上げ・成約率の向上
SFA連携は、売り上げや成約率の向上にも直結します。
SFAと他ツールを連携して営業活動をデータで管理できると、見込み顧客の温度感やアクションの優先度を明確に把握できるようになります。
その結果、ホットリードを見逃すことなく、最適なタイミングで営業アクションを実行でき、成約までのスピードと確度が向上できるでしょう。
また、過去の商談履歴や対応履歴を活用して成果につながりやすいパターンを分析・再現することで、営業活動全体の質向上と売り上げの底上げにも貢献します。
課題別:SFA連携の活用例5つ
ここでは、よくある課題別にSFA連携の具体的な活用例を解説します。
1.既存顧客との関係を深めたいが営業担当ごとに接点履歴が分散している
営業担当が個別に顧客接点情報を管理していると、担当変更や異動のたびに情報が失われ、継続的な関係構築が難しくなるでしょう。
このような状況では、SFAとCRM、名刺管理ツールなどを連携させて、過去のやり取りや顧客接点履歴を一元化するのが効果的です。
情報をSFAで共有しておけば、営業担当が変わっても対応の経緯を把握しやすく、関係性を維持したスムーズな引き継ぎが実現できます。
必要な情報が連携されることで、顧客への継続的な提案や関係構築なども行いやすくなるでしょう。
2.営業活動と請求・在庫管理がバラバラで全体像がつかめない
営業部門とバックオフィスで情報が分断されていると、商談時に正確な納期や在庫状況を確認できず、顧客への提案や社内調整が難しくなります。
このような課題には、SFAとERP(基幹業務システム)や会計・在庫管理システムとの連携が効果的です。
SFAで管理する商談進捗とERP側の在庫・出荷状況を連動させることで、営業は納期を見込んだ正確な提案が可能になります。
受注後の社内連携もスムーズになるため、部門間の情報断絶を解消して業務全体の最適化やミス削減につながるでしょう。
3.リードが増えて管理やアプローチが追いつかなくなってきた
見込み顧客(リード)が増える一方で、どのリードに優先的にアプローチすべきか判断が難しくなり、営業リソースの分散やアプローチ漏れが生じやすくなります。
この場合は、SFAとMA(マーケティングオートメーション)を連携して、対応優先度を明確にするとよいでしょう。
MA側でリードの行動履歴やスコアリング情報を収集し、SFAに反映することで、営業はホットリードに集中したアプローチが行えます。
MAがナーチャリングを担うことで、営業は本来の商談対応に専念しやすい体制を築けるようになります。
4.営業とマーケティングの連携がうまくいかず顧客対応にタイムラグがある
営業部とマーケティング部の情報共有が不十分だと、施策の反応情報が現場に届かず、対応の遅れや二重対応が発生するリスクもあります。
このような課題を解決するには、SFAとMA、チャットツール、グループウェアなどの連携が有効です。
顧客の行動履歴や施策への反応情報をリアルタイムに共有できるようになることで、営業とマーケティング双方が同じ情報基盤を参照して一貫した対応が行えます。
これにより、タイムラグや対応漏れを防ぎ、より質の高い顧客対応を実現できるようになるでしょう。
5.失注した顧客に再提案する機会を逃したくない
失注した顧客に対して継続的なフォローが行われていないと、再検討タイミングでの提案機会を逃すリスクが高まります。
この場合は、SFAとMAやCRMを連携して、失注顧客の情報をマーケティング側で継続的に管理・育成するのが効果的です。
MAで定期的なナーチャリング施策を行い、再検討の兆しが見えたタイミングで営業に自動的に引き渡すことで、自然な形での再提案が可能になります。
こうした仕組みにより、SFA単体では管理が難しい温め中の見込み客も確実に拾い上げ、商談機会の創出につなげられるようになるでしょう。
SFA連携をスムーズに行うコツ

ここでは、SFA連携をスムーズに進めるためのコツを見ていきましょう。
自社に合ったツールを選定する
SFAやCRM、MAなどのツールは多種多様なため、自社に最適な組み合わせを見極めることが重要です。
それぞれのツールには得意領域や連携しやすさに違いがあり、自社の業務フローや既存システムとの相性を考慮せずに導入すると、活用が進まない原因になります。
連携機能が豊富でも、実際の運用で必要な情報が扱えなかったり、現場が扱いにくい仕様だったりすると、現場定着につながりません。
また、機能面だけでなく以下のような要素も含めて判断するとよいでしょう。
- 現場の使いやすさ
- システム管理者の対応範囲
- 社内ITスキルとの相性
複数の側面から判断することで、自社に合ったツールを選定しやすくなります。
各ツールの入力規則やルールを定める
ツール間の連携を効果的に運用するには、明確な入力ルールと情報管理の方針が不可欠です。
SFAとCRM、MAなどを連携する場合、どの情報をどこに入力するのか、更新のタイミングはいつか、といったルールが曖昧だと混乱や二重管理が発生します。
例えば「新規リードはCRMで登録し、商談フェーズ以降はSFAで管理する」といった情報の流れと役割分担を明確に定義しておくとよいでしょう。
また、入力内容に表記揺れがあるとデータの精度が低下するため、表記ルール(部署名や顧客名のフォーマットなど)も事前に統一しておくとスムーズな運用につながります。
社内トレーニングを実施する
ツール間の連携設計が優れていても、現場での理解と運用が伴わなければ定着は難しいです。
SFA連携導入後すぐに活用が進まない原因の多くは、操作方法や連携の意図に対する理解不足にあります。
そのため、連携されたデータがどこに表示され、誰がどのタイミングで参照・入力すべきかを実際に操作しながら学ぶ場(社内トレーニング)を設けることが大切です。
導入時だけでなく、異動者や新メンバーが加わった際にも継続的にトレーニングを実施するとよいでしょう。
これにより、システムが形骸化せず、常に現場で活用される状態を維持できるようになります。
SFA連携に関する注意点
SFA連携は営業活動の効率化に大きく貢献しますが、導入時にはいくつか注意すべきポイントがあります。
ここではSFA連携に取り組む際に押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
はじめから全社に導入しようとしない
SFA連携は段階的に進めるのが成功のポイントです。
導入初期から全社を対象に一斉にSFA連携を進めると、調整範囲が広がりすぎて設計が複雑化し、現場の混乱やコスト超過につながります。
まずは営業部門の中でも特定のチームや、名刺管理ツールとの連携など、スモールスタートから始めましょう。効果を確認しつつ運用の定着を図っていくことが大切です。
初期導入での成功体験を社内に共有することで、他部署への横展開も進めやすくなり、結果的に全社導入もスムーズに行えます。
SFA連携の前にデータをクレンジングしておく
データ品質の整理は、SFA連携成功の土台づくりとして欠かせません。
古い顧客情報や重複データ、表記ゆれのある名刺情報などをそのままSFAに連携してしまうと、営業現場で誤った情報に基づく対応や混乱が発生しやすくなります。
連携前にCRMや名刺管理ツールの情報を整理して、重複排除・正規化・項目統一といった基本的なクレンジング作業を徹底することが重要です。
営業担当者が信頼できる情報だけにアクセスできる状態を整えておけば、SFAの活用度が高まり、システム定着や現場活用の促進にもつながります。
まとめ
SFA連携は、営業活動に関する情報を一元化し、業務効率の向上や組織全体の営業力強化につながる取り組みです。
効果的なSFA連携を実現するには、自社の業務フローに合ったツールを選定して、段階的に連携を進めながら、現場で無理なく活用できる体制を整えていく意識が重要になります。
SFAと連携するツールとしておすすめなのが、ビジネスデータベースのSansanです。
Sansanは名刺管理を起点に、SFAやCRMとの連携を通じて顧客情報の一元化や営業活動の可視化を支援する多彩な機能を提供しています。
SFA連携を進めたいと考えている場合は、ぜひSansanの導入をご検討ください。
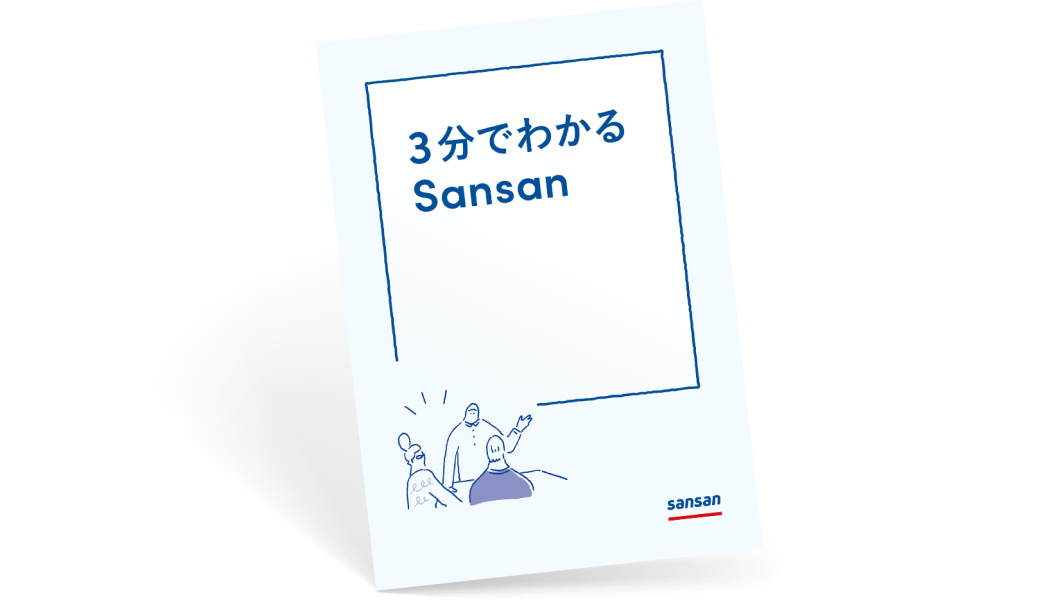
3分でわかるSansan
ビジネスデータベース「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部