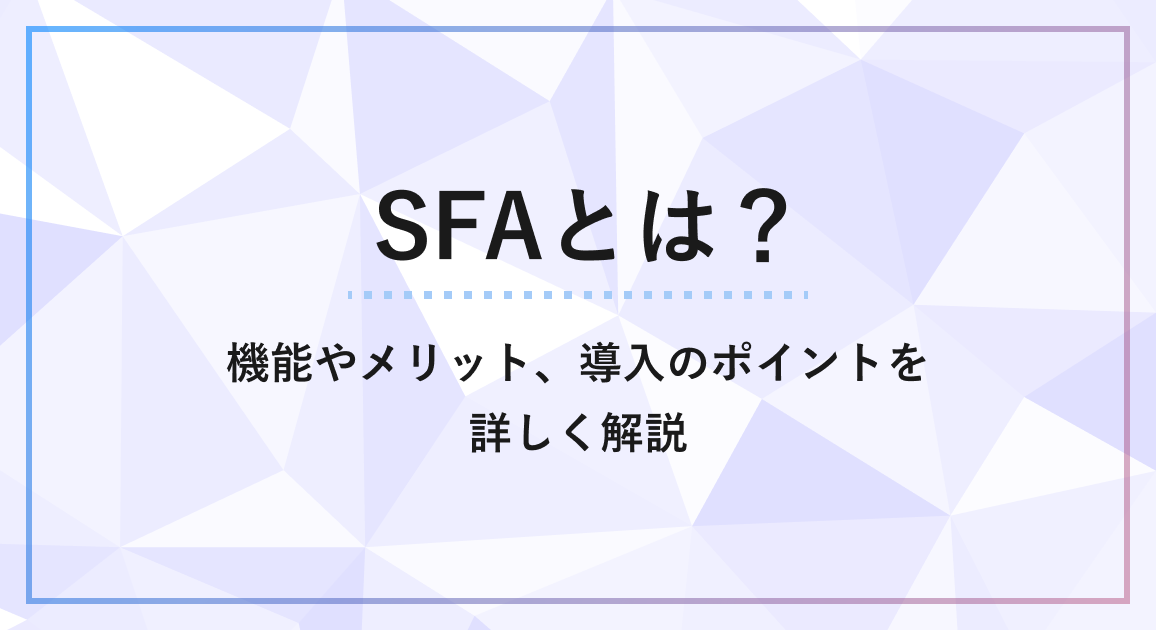- SFA
SFA導入で失敗する原因とは?6つの事例別でわかる対策方法を紹介
公開日:
更新日:
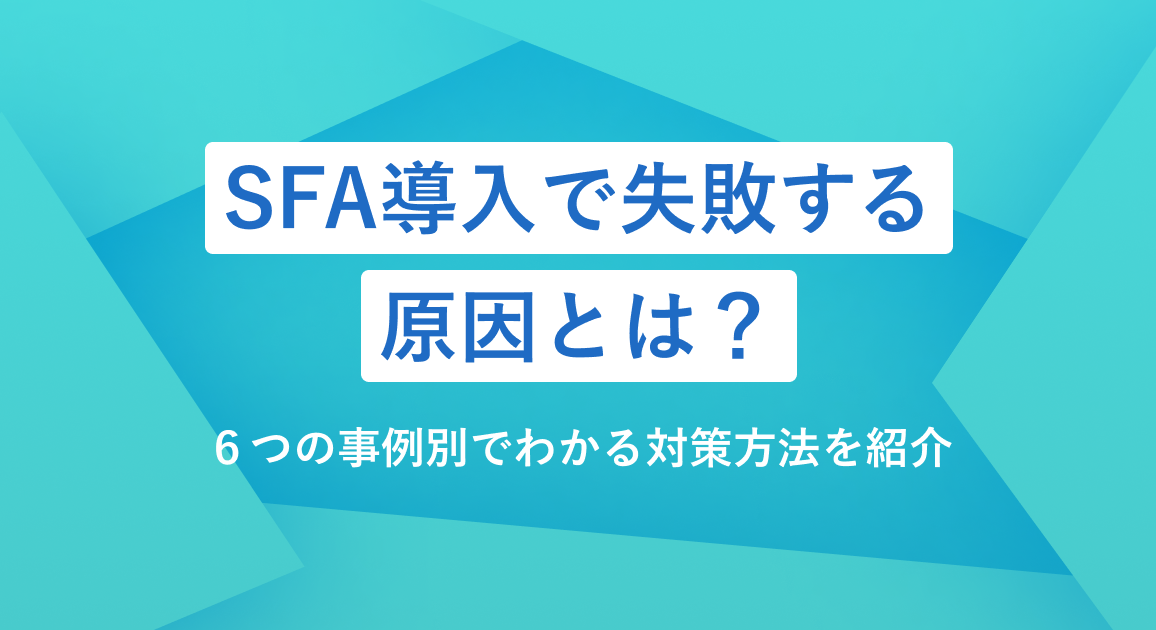
SFA導入の失敗は、明確な目的設定と段階的な導入計画があれば防げます。また、導入後の失敗も適切な対策を講じれば、成功へ導くことも可能です。
本記事では、SFA導入における6つの失敗原因と具体的な対策方法を解説します。ぜひ参考にしてみてください。
営業現場に定着する
SFAとは?
SFAは、営業活動の効率化と業績向上を実現するデジタルツールです。営業担当者の商談管理や顧客情報の一元化、営業部門全体の生産性を向上させます。
他にも、営業活動の可視化やデータに基づく戦略立案、部門間の情報共有が円滑になります。営業マネージャーは部下の活動状況をリアルタイムで把握し、適切な指導やサポートを提供することが可能です。
顧客との商談履歴や提案内容を組織全体で共有し、一貫性のある営業活動を展開できます。
SFA導入で失敗する6つの事例と対策方法

SFA導入の失敗は、不明確な目標設定と現場の連携不足が主な原因です。導入目的を数値化し、現場の意見を取り入れた段階的な実施計画を立案することが重要です。
ここでは、SFA導入で失敗する6つの事例に合わせて、具体的な対策方法を解説します。
事例1.具体的なゴール設定・目的がない
失敗原因として最も多いのは、目的が曖昧なままSFAを導入することです。経営層と現場で期待する効果が異なることが多いため、システムを活用するためには共通の目的をしっかりと決めることが大切です。
例えば、「営業効率を上げる」という漠然とした目的では、具体的な成果が見えないため現場が混乱します。結果として、データ入力が形式的なものとなり、貴重な営業情報が活用されない状態に陥ります。
対策1:導入前に数値目標を明確にする
売上目標や商談件数など、具体的な数値目標を設定すれば、SFAの活用の方向性が明確になります。目標達成までの期間を3カ月・6カ月・1年と区切り、段階的な数値目標を設定しましょう。
数値目標は部門ごとの特性を考慮し、達成可能な水準に設定することが重要です。定期的な進捗確認と目標の見直しにより、現実的な目標管理を実現できます。
対策2:優先順位をつけた段階的な目標設定を行う
最初は基本的な顧客情報管理から始め、徐々に高度な分析機能の活用へと移行しましょう。部門ごとの業務特性に応じて、優先度の高い機能から順次導入を進めることが大切です。
段階的な目標設定により、現場の負担を軽減しながら確実な定着を図ることが可能です。各段階での成功体験を積み重ねれば、組織全体のモチベーション向上につながります。
事例2.データを活用した分析方法が確立されてない
データを集めるだけで具体的な分析方法が決まっていないと、せっかくSFAを導入しても活用できず失敗に終わってしまうかもしれません。
例えば、商談の成功率や顧客の業種別傾向など、基本的な分析すらできていないパターンが多く見られます。分析方法が確立されていないと、営業部門全体の売上予測や戦略立案に必要な情報が埋もれたままとなります。
対策1:データアナリストを配置する
データアナリストと営業部門の連携を進め、実践的な分析結果の活用を進めましょう。
専門知識を持つデータアナリストの配置により、効果的なデータ分析が可能です。定期的なデータ分析レポートの作成と共有により組織全体のデータ活用能力が向上します。
対策2:分析結果を活用した営業戦略の立案を行う
データ分析結果に基づいて、具体的な営業戦略と行動計画を立案しましょう。顧客の購買パターンや商談成功率の分析から、効果的なアプローチ方法を導き出します。
分析結果を営業現場にフィードバックすれば、実践的な活用方法を提案することが可能です。戦略の実行結果を継続的に分析し、PDCAサイクルを回して改善を進めましょう。
事例3.既存の日報との併用で現場の負担が大きい
従来の業務に加えてSFAへの入力作業が発生してしまうと、現場の業務量が増加します。これにより本来の営業活動に支障をきたし、売り上げに悪影響を及ぼす結果となる事例もあるようです。
紙の営業日報とSFAの両方に同じ内容を記入する、といった手間が発生すると、1日の可処分時間が大幅に減少してしまいます。外出先からの入力が困難なため、情報更新が遅れる事態も発生します。
対策1:必要最低限の入力から行う
はじめは基本的な顧客情報と商談記録など、核となる情報の入力に限定しましょう。入力項目を段階的に増やせば、導入後すぐの慣れていないタイミングでは現場の負担を最小限に抑えられます。
現場からのフィードバックを基に、徐々に入力項目の見直しと最適化を進めることが大切です。
対策2:既存の業務フローを見直す
既存の業務フローとSFAの機能を照らし合わせ、重複する作業を特定しましょう。業務フローの見直しにより、効率的な運用体制を構築します。
定期的な業務フローの見直しにより、継続的な改善を実現しましょう。
事例4.運用ルールが整備されていない
データの入力基準が統一されていないことで、正確な情報管理ができません。担当者によって、入力内容や更新タイミングにばらつきが生じる場合もあります。
例えば、商談の進捗状況の判断基準が人によって異なり、案件管理が混乱する事態が発生します。部門間でのデータ共有や分析が困難な状況に陥るため、運用ルールの整備は必須です。
対策1:具体的な運用マニュアルを作成する
データ入力基準や操作手順を明確化したマニュアルを作成しましょう。部門ごとの業務特性を考慮した、実践的なマニュアル内容を整備します。
マニュアルの定期的な見直しと更新により、現場のニーズに対応することが可能です。eラーニングを活用するなどして、効果的な周知と教育を実施しましょう。
対策2:定期的なルール見直しと更新を行う
運用状況のモニタリングにより、ルールの見直しを行います。現場からのフィードバックを基に、必要な改善点を特定します。
定期的なルール更新により、実態に即した運用体制を維持することが可能です。更新内容の周知と教育により組織全体での理解を促進し、ルールの順守を徹底しましょう。
事例5.経営層が関与せず現場任せになっている
経営層のSFA運用への無関心が、システム活用の大きな障壁となります。現場任せの運用では、組織全体での活用が進みません。
例えば、導入後の効果確認や改善活動が行われないと、何のために導入したのかがわからず現場の不満は蓄積するでしょう。
対策1:経営層による定期的なレビューを実施する
月次での進捗確認と課題の把握により、方向性を明確化しましょう。経営層からの定期的なメッセージ発信により、組織全体の意識向上を図ることが大切です。
レビュー結果に基づく具体的な改善指示により、SFAの活用を促進します。成功事例の共有などにより、現場のモチベーション向上を目指しましょう。
対策2:費用対効果の可視化を行う
導入コストと効果を定量的に測定し、費用対効果を明確化しましょう。売り上げの向上や業務効率化など、具体的な数字がわかる成果指標を設定します。
定期的な効果測定により改善点の特定と対策立案を行い、経営層へ成果を報告することで現場任せの体制を変えることが可能です。
事例6.サポート体制が不十分である
社内のSFA推進チームと外部のシステム提供会社のサポート体制が十分に機能しておらず、その結果、SFAの活用が停滞する、といったことも失敗の原因となりえます。現場が困ったとき相談できる窓口が社内外どちらにも明確に設置されていないと、社員は不安を感じ積極的に活用するのを躊躇してしまいます。
例えば、基本的な操作方法に関する質問や、システム提供会社への技術的なトラブル相談への回答が遅いと、日々の業務に支障が出ます。社内外の役割分担が不明確なまま運用を始めると、問題発生時の対応が遅れ、営業活動が停止する可能性もあるため注意が必要です。
対策1:定期的なユーザー研修を実施する
利用する社員のSFAに対する理解の底上げをすれば、そもそもの問い合わせを減らすことができるでしょう。そのために基本操作から応用機能まで、段階的な研修プログラムを実施してみてください。また、共通の使い方のほかにも部門別の目的ごとに特化した、実践的な研修内容の整備もおすすめです。
定期的な研修実施により、スキルの向上と定着を図ることが可能です。さらにオンライン研修ツールの活用により、効率的な教育が実現できるでしょう。
対策2:技術的なトラブルに対応できる人材を雇う
技術的なトラブルに対応するためにも、システム管理とユーザーサポートを担当する専門チームを設置しましょう。技術的な知識と現場理解を備えた人材を配置して、いつでも対応できる体制を整えます。
迅速なトラブル対応により現場の業務効率が維持され、且つ予防的なメンテナンスによりシステムの安定運用を確保することも可能です。
SFA導入に失敗した場合の対策方法
SFAの導入に失敗してしまった、と感じたときは、現状分析と具体的な改善策の実施が必要です。利用範囲の見直しや別システムへの移行を含めた対策を検討しましょう。
ここでは、具体的な対策方法について解説します。
SFAを利用する人を限定し成功例をつくる
利用者を営業部門の一部チームに限定し、成功事例を作ることから始めましょう。限定的な運用により、具体的な課題の特定と改善が容易になります。
少人数での運用実績をもとに、活用方法の最適化と運用ルールの見直しを行います。成功体験を組織全体で共有していけば、段階的にSFAの導入を進めることが可能です。
別のSFAへの移行を検討する
今活用しているSFAがある場合、システムの問題点を明確化しつつ、改善案が見つからない際には新システムへの移行も検討しましょう。利用している社員の意見を収集し、具体的な改善ポイントを特定することが大切です。
新システムの選定では、操作性と既存業務との親和性を重視します。例えば、営業活動の効率化に特化したツールなど、現場のニーズや業務内容に合わせた選択が必要です。
ツール変更時には、データの移行方法と新旧システムの並行運用期間を設定しましょう。利用者への事前説明と教育により、新システムへの移行をスムーズに進められます。
まとめ
SFA導入の成功には、明確な目標設定と現場との連携が不可欠です。段階的な導入と定期的な効果測定により、社内の定着を図ります。
運用体制の整備とサポート体制の充実により、持続的な活用が可能です。顧客データの正確な管理と活用により、営業活動の効率化と成果向上が期待できます。
営業DXツール「Sansan」は、名刺や企業情報、営業履歴を一元管理して全社で共有できるようにすることで、売上拡大とコスト削減を同時に実現できます。
営業活動の可視化やデータ分析機能により、効率的なSFA運用を実現できます。SFAをスムーズに導入したいとお考えの企業は、ぜひSansanの導入をご検討ください。

3分でわかる Sansan
営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部