- マーケティング
オンラインセミナーを成功させるための3つのポイントとは?メリットやデメリットを解説
公開日:
更新日:
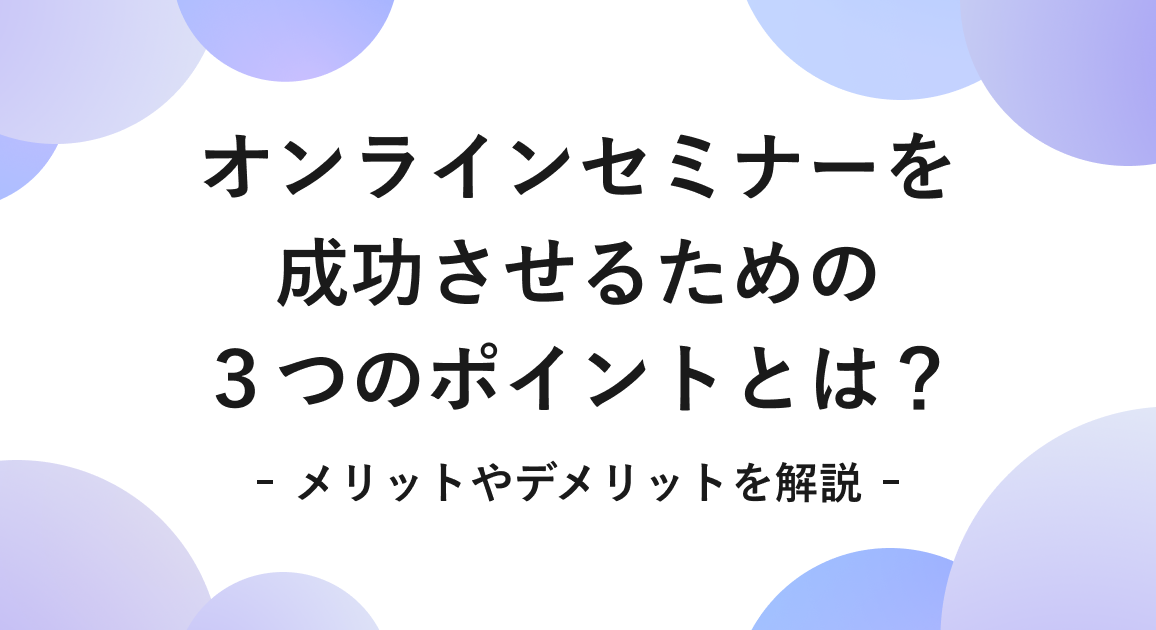
オンラインセミナーは、オフラインセミナーと比較してコストを抑えられるのが特徴です。ただし、事前にメリット・デメリットを把握しないと、期待どおりの成果は得られません。本記事では、オンラインセミナーの主な特徴と、成功に導くためのポイントを解説します。
マーケティング部のSansan活用法
オンラインセミナーとは
オンラインセミナーは、インターネット上で開催するセミナー形式で「ウェビナー」とも呼ばれます。
パソコンやスマートフォンがあれば、場所を問わず参加できるのが特徴です。
従来の会場型セミナーと異なり、移動や設営が不要で、世界中の参加者を集められます。時間や距離の制約を受けにくいため、参加のハードルも低くなります。
オンラインセミナーの配信形式は「ライブ配信」と「オンデマンド配信」の2種類があります。
ライブ配信はリアルタイムで進行し、チャットや質疑応答などで参加者とのやり取りが可能です。一体感や臨場感を演出しやすい配信形式と言えるでしょう。
オンデマンド配信は、あらかじめ録画・編集された動画を配信する方式で、参加者が好きな時間に視聴できる点が魅力です。繰り返し視聴できるうえ、高品質なコンテンツを提供しやすいといったメリットがあります。
このように、柔軟な参加環境と配信形式を備えたオンラインセミナーは、現代的な情報発信の手段として広く活用されています。
オンラインセミナーを開催するメリット
オンラインセミナーを開催する主なメリットを紹介します。
セミナーにかかるコストを節約できる
オンラインセミナーは、会場型セミナーと比べて大幅なコスト削減が期待できます。
オフラインでは、会場費、講師の交通費や宿泊費、資料の印刷代など、さまざまな固定費がかかるうえ、規模が大きくなるほど費用も増えるため、予算を圧迫する要因になります。
一方で、オンライン開催では配信環境を整えるだけで、これらの費用をかなり抑えられます。登壇者も自宅やオフィスから参加できるため、移動に伴う手間もかかりません。
また、録画した動画をオンデマンド配信すれば、追加コストなしで何度も活用できます。情報発信だけでなく、教育コンテンツや営業資料としての二次利用ができるのもメリットと言えるでしょう。
全世界から集客できる
オンラインセミナーは、場所の制約なく集客できる点も強みです。
インターネット環境があれば、国内外を問わず誰でも参加できるため、移動が難しい担当者や、移動時間が取れないビジネスパーソンにとっても魅力になるでしょう。
さらに、多言語対応の配信プラットフォームを使えば、より幅広い層へアプローチできます。
例えば、字幕の自動生成や通訳機能を活用すれば、海外の視聴者とのやり取りもスムーズになります。
グローバル展開を視野に入れる企業にとって、エリアを越えた情報発信ができるオンラインセミナーは有効な手段と言えるでしょう。
参加者と手軽にコミュニケーションが取れる
オンラインセミナーは、視聴者とコミュニケーションを取りやすいのもメリットです。
チャットやQ&A機能を使えば、リアルタイムで質問を受け付けられ、迅速な対応が可能です。オフラインでありがちな質問しづらい空気感も少なく、匿名投稿が可能な場合はさらに心理的なハードルも下げられるでしょう。
また、アンケート機能を使えば参加者の満足度や関心のあるテーマを把握できます。得られたフィードバックは、次回セミナーの改善や営業施策に生かす材料にできるでしょう。
このように、オンラインセミナーは一方通行にならず、参加者との関係構築にもつなげやすい点が魅力です。
オンラインセミナーを開催するデメリット

オンラインセミナーは次のようなデメリットがある点を覚えておきましょう。
通信環境に左右されやすい
オンラインセミナーはインターネットを介して行うため、通信環境の影響を受けやすい点に注意が必要です。
特に主催者側の回線が不安定だと、映像や音声が乱れ、参加者の離脱を招くリスクがあります。せっかく集めた見込み顧客との接点を失う可能性もあるので、安定した通信環境の確保が重要です。
有線LANの利用やモバイルルーターなどの予備回線などを用意すれば、配信トラブルのリスクを軽減できます。
また、参加者側への配慮も重要です。事前に「推奨環境」や「視聴テスト用URL」を案内しておけば、参加時のトラブルを減らすことができるでしょう。
参加者の関心度が把握しづらい
画面越しのコミュニケーションでは、参加者の表情や空気感が読み取りづらく、話の展開を調整しにくいといったデメリットがあります。
対面であれば視線やうなずきといったボディーランゲージで反応を把握できますが、オンラインでは「ながら視聴」やデバイスの通知による中断も起こりやすく、
こうした課題を緩和するには、チャットやリアクション、投票機能などのインタラクティブな仕組みを取り入れるのが有効です。
また、セミナー後にアンケートを実施することで、関心度や視聴態度を把握して次回の改善に生かせるようになるでしょう。
リアルな体験が伝えにくい
オンラインでは、五感に訴えるようなリアルな体験の提供が難しくなります。
特に香りや質感、温度などが重要な商品・サービスの場合、映像や音声だけでは伝えきれないケースも多く、訴求に限界があります。
対策としては、セミナー内で基礎情報を伝えたうえで、体験会やサンプル提供といった別の機会を用意するとよいでしょう。オンラインセミナーで完結せずに、商談やリアルイベントへとつなげる導線を設計すれば、参加者の理解も深まります。
業種やターゲットによっては、オンラインとオフラインを組み合わせた「ハイブリッド型」の活用も有効です。
オンラインセミナー開催の具体的な流れ

オンラインセミナーの開催プロセスを、「事前準備」「当日」「開催後」の3段階に分けて解説します。
事前準備
はじめにオンラインセミナーを開催する前の事前準備について見ていきましょう。
1.目標・ターゲットを設定する
オンラインセミナーの準備を始める際、最初に明確にすべきなのが「目標」と「ターゲット」です。ここが曖昧な場合、構成やコンテンツがぶれ、成果につながりにくくなります。
目標の代表例は以下のとおりです。
- 新規リード獲得
- 既存顧客との関係強化
- 見込み顧客の育成
例えば、新規リード獲得を目的とする場合、幅広い関心を引くテーマや参加特典の設計が効果的です。既存顧客向けであれば、製品活用の事例紹介や導入効果の提示などが有効です。
また、ターゲットを明確にすることで伝えるべき内容・コンセプトが定まります。
経営層と現場担当者では関心のポイントが異なるため、構成やトーンを調整する必要があるでしょう。
目的とターゲットを明確にできれば、セミナー全体に一貫性が生まれて自社のメッセージを届けやすくなります。
2.企画構成を決定する
セミナーの効果を最大化するには、構成の最適化が重要です。
構成が整理されていない場合、参加者の集中力をキープできないリスクがあります。
一般的な構成は、「イントロダクション → メインセッション → Q&A → クロージング」です。BtoB向けには、課題提示から解決策の提示、実例紹介までを流れとして組み立てると理解しやすくなります。
例えば、冒頭で「なぜこのテーマに注目すべきか」を提示して、次に現状の課題を可視化。そのうえで、自社サービスがどのように役立つかを説明すると、納得感のある展開が作れます。
ストーリー性を意識して構成を設計すると、参加者の理解度・関心度ともに高まりやすくなるでしょう。
3.講師・進行役などの担当者を決める
当日の進行を円滑にするには、登壇者の役割分担を事前に明確にしておくことが重要です。
オンラインではタイムラグや音声トラブルなど予期せぬトラブルが発生しやすいため、事前の準備とチーム間の連携が不可欠です。
講師にはテーマに対する専門知識とわかりやすく説明する力が求められます。
進行役(モデレーター)は全体の進行管理と参加者とのやり取りのサポートを担います。
例えば、チャットで寄せられた質問にその場で反応するようなセミナーでは、質問の選定やタイミングを調整する担当者がいると安心です。
誰がどの場面を担当するのかを共有し、チーム全体で進行イメージを持っておくことで、想定外のトラブルにも落ち着いて対応することができるでしょう。
4.配信システムやツールを選ぶ
オンラインセミナーの配信形式に適したツール選定は、運営をスムーズに行うポイントのひとつです。
ライブ配信、録画配信、ハイブリッド型など、目的に合った形式に対応するツールを選びましょう。
代表的な配信システムは以下のとおりです。
- Zoom
- Google Meet
- Microsoft Teams
- Webex
どのツールも基本的な機能は共通していますが、参加人数の上限、画面共有の自由度、チャット機能の使いやすさなどに違いがあります。セミナーの規模や目的に合ったものを選びましょう。
また、参加者の利便性も重視すべきポイントです。
初回でもログインしやすいか、アプリのインストールが必要かといった要素は、参加率に直結します。
業種によっては、社内で使用するコミュニケーションツールが決まっている場合もあります。その場合は、参加者が使い慣れたツールと配信方法を優先するのが基本です。
5.配信環境と機材を準備する
安定した配信と明るく聞き取りやすい映像・音声は、セミナーの評価を左右します。
オンラインセミナーを開催する際は、以下3つのポイントを万全にしておきましょう。
- カメラ
- 外部マイク
- 照明
カメラは、明るく自然に映るものを選びます。
映像が暗かったりピントが甘かったりすると、視聴者の集中が途切れやすくなるからです。
マイクはPC内蔵ではなく、音質の安定した外部マイクがおすすめです。音がこもる、ノイズが混ざるといった問題はセミナーの印象を損ないやすいので注意してください。
また、照明も重要で、顔が暗く映ると表情が伝わらず印象が悪くなります。適切なライトを使って表情が見えるように調整しておきましょう。
通信環境は、有線LANをメインに予備としてモバイルルーターなどのバックアップ回線を用意しておくと安心です。
配信前は必ずリハーサルを行って、画面共有や音声の切り替えなど、機材の動作確認も済ませておきましょう。
6.セミナー資料・トークスクリプトを作成する
オンラインセミナーを円滑に進めるには、資料とトークスクリプトの準備が欠かせません。
スライド資料は、情報を詰め込みすぎず1枚につき1メッセージを意識して構成しましょう。文字サイズや配色にも注意して、箇条書きや図表を取り入れると視覚的に理解しやすいです。
また、登壇者の話す内容をあらかじめまとめておくと、本番中の迷いや脱線を防止できます。どの場面で何を話すのか、要点と事例を明確に整理しておくことが大切です。
内容の準備が整っていれば登壇者側も安心できて、視聴者にも伝わりやすいセミナーになるでしょう。
7.アンケートを作成する
参加者へのアンケートは、次回のオンラインセミナーをよりよくするために重要です。
満足度や理解度に加えて、知りたいテーマや気になった点など、次の施策につながる設問を含めましょう。営業やマーケティングに生かす場合は、業務上の課題や関心分野が見える設問などもおすすめです。
例えば、以下のような自由記述を入れると深いインサイトが得られます。
- 今回のセミナーで印象に残った部分は?
- 次回取り上げてほしいテーマは?
回答率を上げるには、設問数を最小限に絞ってスマートフォンでも簡単に回答できる設計にすると効果的です。
また、セミナー終了後に案内するだけでなく、開催中に記入時間を確保しておくと回収率を向上できます。
8.ターゲットを集客する
どれだけ内容が優れていても、適切なターゲットに届かなければセミナーの効果は期待できません。
集客する際は複数のチャネルを併用するのが基本です。
メールマーケティング、SNS、Web広告、オウンドメディアなどを活用し、ターゲットの特性に応じて訴求メッセージを調整しましょう。例えば、既存顧客にはフレンドリーな案内文を、新規リードには課題を提示するような切り口が有効です。
また、参加登録フォームの設計も重要です。
入力項目が多すぎると離脱の原因になるため、必要最低限の情報に絞りましょう。登録完了までの流れがシンプルであるほど参加率は高まります。
「誰に・何を・どのタイミングで伝えるか」を明確にすると、質の高いリードを獲得しやすくなります。
9.リハーサルを行う
本番の進行をスムーズにし、トラブルを未然に防ぐには、事前のリハーサルが欠かせません。
全体の流れを通して確認しておけば、想定外の事態にも落ち着いて対処できます。
リハーサルは登壇者・進行役・技術担当を含む関係者全員が参加して、以下の点を重点的に確認しましょう。
- 機材の動作確認
- 配信ツールの操作テスト
- 回線状況の確認とバックアップ手段の用意
- 質問対応やトラブル時の役割分担
また、セミナー全体の所要時間も計測しておくと、当日のスケジュール管理がスムーズになるのでおすすめです。
入念な準備が登壇者の安心感を生み、参加者にも信頼感を与えられます。
当日
ここでは、オンラインセミナー当日の流れについて解説します。
1.配信環境の最終チェックを行う
オンラインセミナー当日は、配信環境と機材などの最終確認を行います。
小さな不具合でも参加者の離脱や企業イメージの低下につながる可能性があるので、念入りにチェックしましょう。
主なチェックポイントは以下のとおりです。
- インターネットは安定しているか
- カメラ・マイクの映像/音声は問題ないか
- スライドや画面共有の表示切り替えはスムーズか
また、万が一に備えて予備のPCやモバイルルーターを準備しておくとより安心です。
代替機器の操作方法もあらかじめ確認しておけば、トラブルが起きても慌てず対応できます。
配信の安定性を確保することで、参加者にとってストレスのない視聴体験を目指しましょう。
2.参加者にセミナー開始のアナウンスを行う
オンラインセミナー開始前の案内は、参加者に対してアナウンスを行います。
以下の内容を簡潔に伝えましょう。
- セミナーの流れと所要時間
- 質疑応答のタイミングと方法
- チャットやQ&A機能の使い方
- マイク・カメラの操作ルール
例えば「Q&Aは後半に時間を設けています」や「チャットは自由にご利用ください」といった一言を添えるだけで、参加者の不安が軽減されて場の雰囲気も和らぐでしょう。
丁寧なアナウンスは、運営側への信頼感にもつながりやすく、参加者との関係構築にも有効です。
3.アンケートに回答してもらう
セミナー終了時は、参加者の熱量が高い状態のため、このタイミングでアンケートを案内すれば、より具体的で率直なフィードバックが得られる確立が高まります。
スムーズにアンケートの回答を促すためには、以下の工夫が効果的です。
- チャットでアンケートURLを共有する
- 画面上にQRコードを表示する
- 「2〜3分で完了します」と伝える
「ご意見は今後の企画に生かします」と明記しておけば、参加者の回答率もあがります。
収集した回答は次回セミナーの改善だけでなく、営業やマーケティング施策の素材としても活用可能です。
セミナー終了時は、参加者にアンケート回答を促してフィードバックをもらいましょう。温度感が高いうちに意見を求めることで、次回のセミナーに生かせるリアルな反応が得られます。
開催後
最後に、オンラインセミナー開催後の流れについて見ていきましょう。
1.参加者へフォローメールを送る
セミナー終了後は、参加者との接点を維持するために、できるだけ早くフォローメールを送付します。
関係性が温まっているタイミングでアプローチすることで、次のアクションにつなげやすくなります。
メールに含めるべき主な内容は以下のとおりです。
- セミナー参加へのお礼
- セミナー資料や録画アーカイブの提供
- アンケートの再送(未回答者向け)
- 次回セミナーや関連サービスの案内
営業活動を意識する場合は、アンケート回答や視聴中の反応などから関心度の高い参加者を抽出し、個別のフォローアップメールを送ることも検討しましょう。
セミナーの様子を録画していた場合は、アーカイブを自社サイトやSNSで共有するのも効果的です。オンデマンド配信として活用すれば、新たなリード獲得や接点づくりにもつながります。
2.アンケート結果を分析して改善点を見つける
セミナー後に得られるアンケート結果は、次回の質を高めるための重要な材料です。
感覚的な判断ではなく、データに基づいて改善点を見つけていく姿勢が求められます。
まずは、満足度や理解度、印象に残った点などの回答をもとに、良かった点と改善点を整理しましょう。たとえば「話がわかりやすかった」「資料が見づらかった」といったリアルな声から、改善のヒントが得られます。
営業やマーケティング活動と連動させる場合は、参加者が関心を示したテーマや課題を抽出し、それに対応するコンテンツや提案を企画するのが効果的です。
アンケートのデータは、定量(スコアなどの数値)と定性(自由記述)の両面から分析することで、より実態に近い成果の振り返りが可能になります。
こうしたフィードバックを企画に反映することで、セミナー運営の精度を着実に高めていけるでしょう。
オンラインセミナーを成功させる3つのポイント

ここでは、オンラインセミナーを成功に導く3つのポイントについて紹介します。
1.安定した通信環境を確保しておく
オンラインセミナーを成功させるには、安定した通信環境の確保が大前提です。
配信中に映像や音声が途切れると、参加者の集中が切れて離脱の原因になります。
基本は有線LANによる接続がおすすめです。Wi-Fiのみでは不安定になる場合もあるため、予備としてモバイルルーターなどのバックアップ回線を用意しておきましょう。
カメラやマイクの品質も事前に配信ツールで確認し、本番と同じ環境でテストすることが重要です。
配信の安定性は、セミナー全体の信頼性に直結します。
2.オンラインツールの機能を使って参加者の反応を引き出す
オンラインでは参加者の反応が見えづらいため、意識的に反応を引き出す工夫が必要です。
チャット、リアクションボタン、投票機能などは、参加者の声をキャッチする手段として有効です。講義中に質問を投げかけるだけでも、参加者の受け身の姿勢を崩して、集中を促す効果があります。
また、配信ツールによっては視聴データを確認する機能も利用できます。
離脱が集中する箇所がある場合、テンポや見せ方を調整して改善しましょう。
Q&Aセッションの時間も明示し、質問しやすい雰囲気をつくることで、参加者の満足度向上にもつながります。
3.通常の営業活動と差別化した内容にする
オンラインセミナーが単なる営業プレゼンに見えてしまうと、参加者の関心は薄れやすくなります。
セミナーとしての価値を感じてもらうには「情報提供」と「学び」の要素を明確にする必要があります。商品の紹介を行う場合でも、事例や実演を交えて「どう使われているか」「どんな成果があったか」を具体的に示すと、参加者の理解と共感が得やすくなるでしょう。
業界トレンドや課題解決型のコンテンツを取り入れると「参加する価値がある」と感じてもらいやすくなります。
営業色を抑えつつ自然に商談につなげる流れを意識すると、参加者の負担を最小限にしながらアプローチできるでしょう。
オンラインセミナーで失敗しないための注意点

オンラインセミナーで失敗しないためには、以下の注意点を押さえておきましょう。
参加者にセミナーに必要な環境を伝えておく
参加者がスムーズに視聴できるよう、事前に必要な環境を明確に伝えておきましょう。
例えば、通信環境のトラブルで視聴できなかった場合、セミナー内容以前に信頼を損なうおそれがあります。
また、業務時間中の視聴の場合、企業ネットワークの制限によって特定のツールが使用できないケースも考えられます。
トラブルを避けるために、以下のような事前準備が有効です。
- 推奨環境チェックリストを配布
- 視聴テスト用URLを送信
事前に対策を講じておけば、不要な問い合わせやクレームを防止できるでしょう。
参加者のカメラとマイクのオンオフについて周知しておく
円滑にオンラインセミナーを進めるためには、事前に参加者側のマイク・カメラのルールを共有しておくとよいでしょう。
全員のマイクがオンになっていると、雑音やハウリングが発生し、登壇者の声が届きにくくなる可能性があります。そのため、基本的にはミュートでの参加をルールとして明示しましょう。
一方、質疑応答のタイミングではマイクをオンにして発言してもらうシーンも考えられます。切り替えタイミングや操作方法なども事前に共有しておくと安心です。
カメラのオン・オフについても「顔出しが必須かどうか」をあらかじめ伝えておくことで、参加者の心理的ハードルを下げることができます。
通信・機材トラブルへの対策を準備しておく
オンラインセミナーでは通信や機材トラブルの発生を想定し、事前の対策が重要です。
主催者側は以下の準備をしておくと安心です。
- モバイルルーターなどのバックアップ回線
- 予備のPC・マイク・カメラなどの機材
- トラブル時の対応フローのマニュアル
また、参加者側にも以下のような対処法を案内しておくと混乱を最小限に抑えられます。
- ページの再読み込み
- 別ブラウザでの再接続
- ネットワーク設定の確認
開催中は技術担当者をスタンバイさせておくことで、予期せぬトラブルにも迅速に対応できるようになります。
まとめ
オンラインセミナーは、場所や時間に縛られずに柔軟に開催できる手段として、多くの企業に採用されています。
多くの見込み顧客と接点を持てる反面、「フォローが追いつかず商談化しない」「優先してアプローチすべき相手が分からない」といった課題も生じがちです。
これらの課題を解消するには、ビジネスデータベース「Sansan」の活用がおすすめです。
オンラインセミナーで得た参加者情報をもとに、フォローメールの送信などを行えるため、オンラインセミナーからの営業成果へとつなげやすくなります。
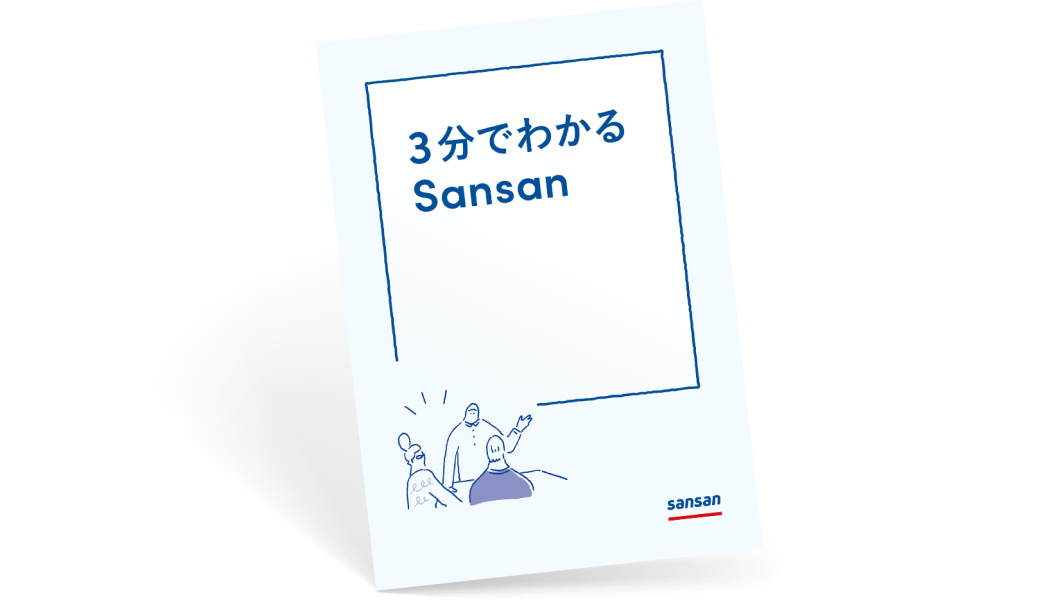
3分でわかるSansan
ビジネスデータベース「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部
