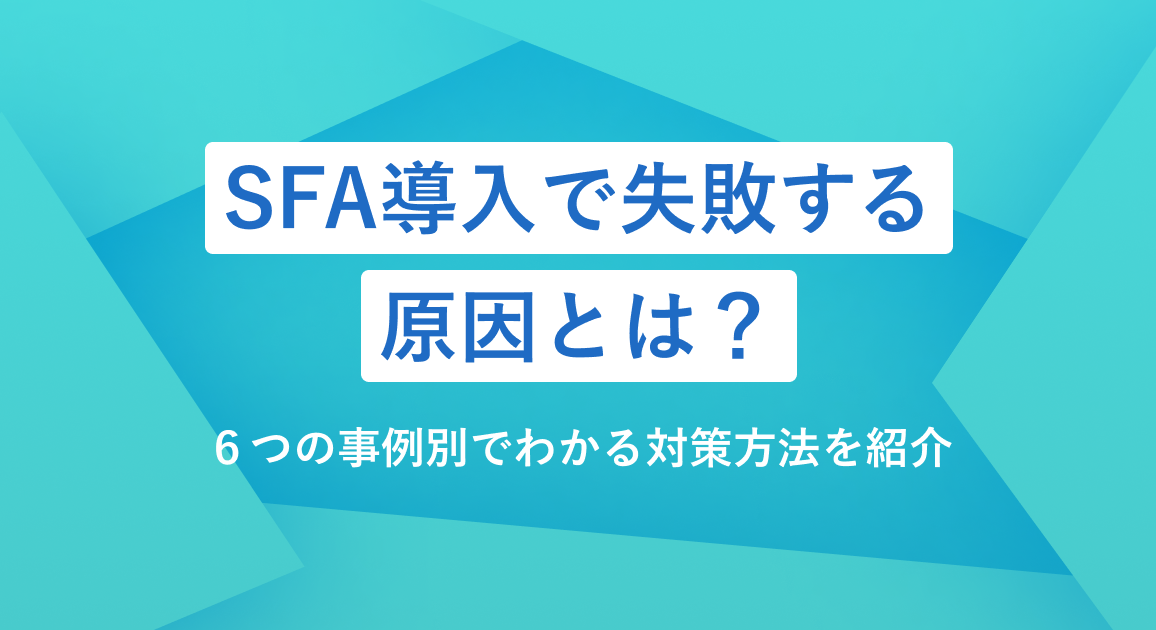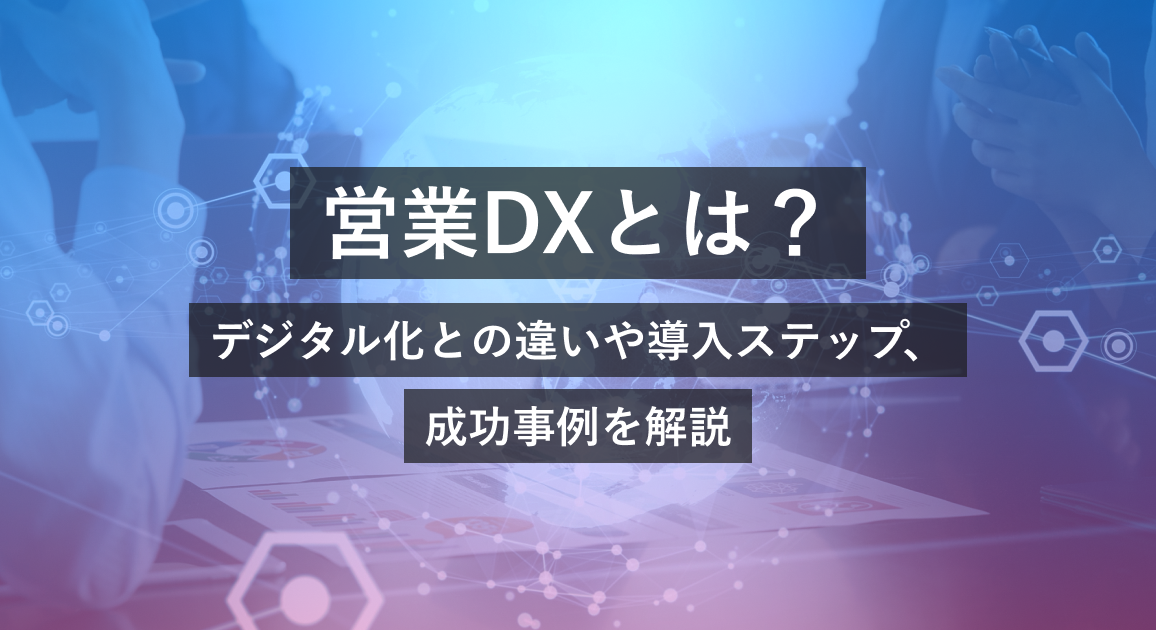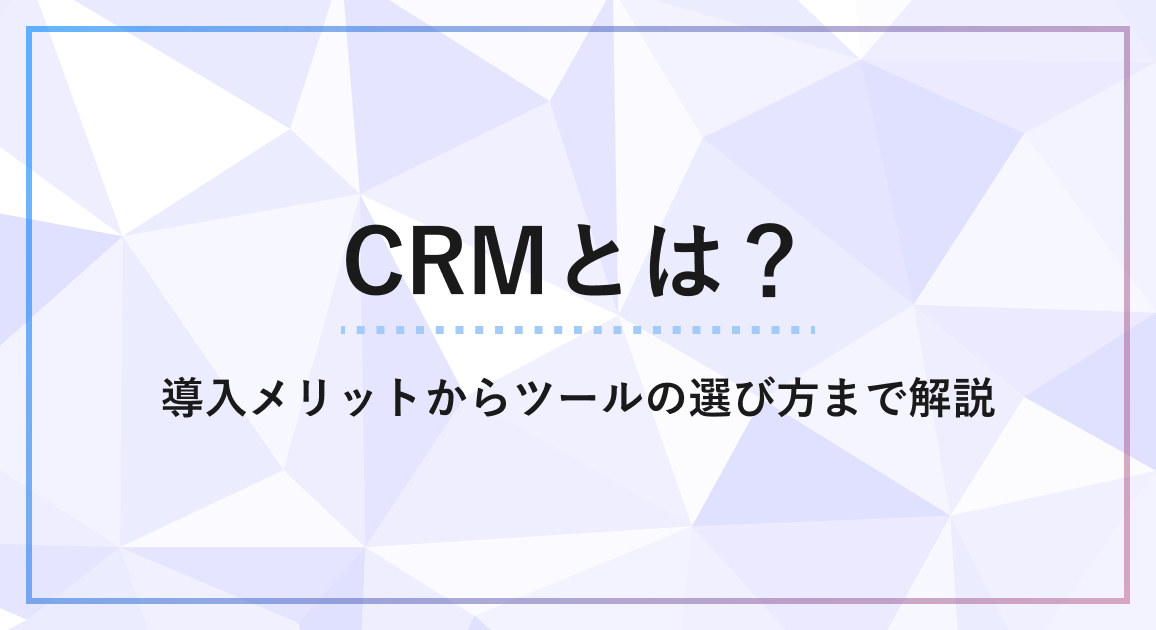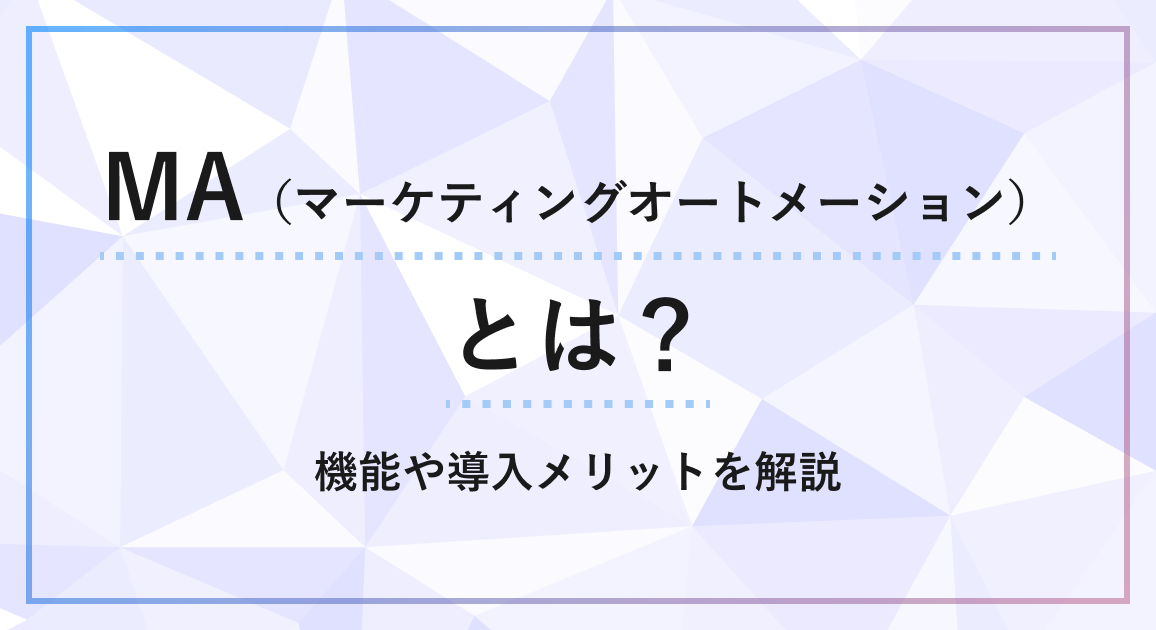- SFA
SFAが定着しない5つの理由とは?対策と効果を最大化するポイントも紹介
公開日:
更新日:
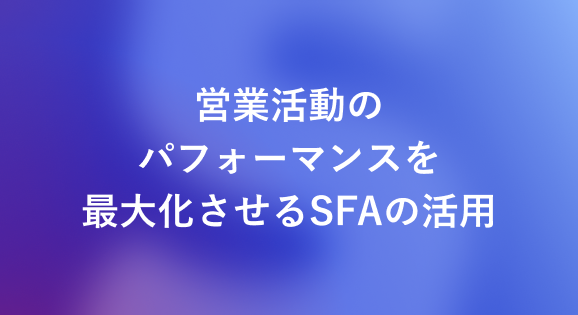
働き方や営業のあり方が大きく変化を迎える中、Sales Force Automation(SFA)が注目を集めています。しかし、導入企業の中には期待される効果を得られず、定着に苦戦する事例も少なくありません。本記事では、まずSFA活用のメリットを整理し、次に導入失敗の要因を掘り下げたうえで、現場で成果を最大化するポイントを分かりやすく解説します。
営業現場に定着する
SFAが定着しない5つの理由
ここでは、SFAが定着しにくい背景とその要因を整理します。
1.導入の目的が現場に共有されていない
SFAが定着しないよくある理由のひとつが、導入する目的や意図が現場まで伝わっていないケースです。
導入目的がトップ層のみで完結していると、現場スタッフは単純に面倒と感じてしまうでしょう。結果として、現場担当者の入力が後回しになったり、積極的に活用されないなどの原因になります。
また、操作の複雑さや入力項目の多さ、ツールの活用イメージが現場で明確に描けないといった意識のズレも、SFAが形骸化してしまう要因です。
SFAの価値を生かした運用を行うには、チーム全体で導入目的を共有し、現場の業務フローとひも付けた戦略設計が求められます。加えて、運用設計や社内ルールの整備、現場との合意形成といった取り組みも欠かせません。
2.入力項目が多く現場の負担になっている
SFAシステムの入力項目が多すぎて現場の負担になっているパターンもあります。
SFAの真価を発揮するには、質の高いデータの蓄積が欠かせません。しかし、入力項目を増やしすぎると営業活動に支障が出てしまいます。
結果として営業担当者が商談に集中できない、といった逆効果につながる可能性もあるでしょう。
特に外回りの営業活動がメインの場合、移動中や帰社後にまとめて入力するケースも多いです。この際、入力作業が複雑だとSFAが定着しない原因になります。
営業担当者の負担を増やさないためにも、入力項目を絞ったり、スマホでも入力しやすい設計のシステムを選んだりといった対応が重要です。
3.操作が直感的でなく使いづらい
複雑な操作が必要なSFAシステムは、現場に定着しない原因になりやすいです。
直感的に操作できないSFAシステムは、営業担当者のストレスになります。メニュー構成が複雑だったり、メインの機能にアクセスしにくかったりすると、SFAシステムの利用を敬遠されてしまうでしょう。
どんなに高機能でも、担当者にとって使いにくいシステムは定着させるのが難しくなります。
業務フローに即したUI設計や、使用頻度の高い機能にすぐアクセスできる導線づくりなど、自社に合ったシステムの選定が鍵を握っています。
4.社内の運用ルールが定まっていない
社内の運用ルールが定まっていないことがSFAが定着していない原因になっているケースもあるでしょう。
- 誰が
- いつ
- どのタイミングで
- 何を入力するのか
このような運用ルールが曖昧になっていると、SFAシステムに蓄積されるデータもバラバラになってしまいます。
たとえば、取引先企業の名前を入力する際も、「株式会社A」と「(株)A」では、別の企業として登録されてしまいます。
また、いつまでにどのフェーズを更新するかといったルールが決まってなければ、最新状況が反映されず、SFAシステムを生かした営業活動は難しいです。
明文化されたルールをチーム内で共有し、定期的な運用レビューを行う体制づくりが重要と言えるでしょう。
5.導入後の教育や研修が不足している
SFAシステムを導入したものの、教育や研修が不足しているために定着しないパターンもあります。基本的な操作方法や活用方法についての教育が不十分だと、自己流で運用する原因になり、誤った運用や誤入力が発生する可能性が高いです。
わからないことが放置されてしまうと、徐々にシステムを利用しなくなってしまいます。初期研修だけでなく、定期的な振り返り研修や、異動・新入社員への再教育体制の整備も必要です。
また、マニュアルや社内FAQサイトなども活用し、継続的にサポートする仕組みを整える対策がSFA定着の鍵となります。
SFAを定着させるための対策方法5つ
ここでは、SFAを定着させるためにすべき対策方法について見ていきましょう。
1.社内で導入の目的を共有する
SFAを定着させるためには、まず社内全体に導入目的を共有しましょう。
「なぜSFAを導入したのか」と「SFAによって自分にどんなメリットがあるのか」を共有できれば、システムを積極的に活用しやすくなります。たとえば、営業成績の可視化や業務の効率化など、導入する価値をシェアすることが大切です。
トップダウンで一方的に押し付けるのではなく、現場の業務や課題と関連付けて伝えるとよいでしょう。
導入目的を忘れてしまわないように、定期的にリマインドすることも重要です。
SFAシステムの利用価値が理解されていけば、自然に定着するでしょう。
2.入力項目を最小限に絞る
SFAを導入する際は、最小限の入力項目でスタートするのがおすすめです。
入力する情報が多すぎると記録作業に時間がかかり、担当者の負担になります。
「SFA=面倒」というイメージがつくと定着させるのは難しいため、まずは必要最小限の必須項目のみに絞りましょう。
質の高いデータを求めるのは当然ですが、定着させるためにまずは入力率や更新頻度を向上させる対策が重要です。定型化できる項目はチェックボックスやプルダウン形式にすることで、手入力の負担を軽減できます。
他システムと連携する場合は、営業担当者の手間を最小限に抑える設計を意識しましょう。
3.担当者にとって使いやすいシステムを選ぶ
営業担当者にとって使いやすいSFAシステムを選ぶのも対策のひとつです。
システムの操作性は定着率に直結します。自社の営業スタイルや人員構成に適したSFAシステムは、担当者のストレスを最小限にできるでしょう。
たとえば、ワンクリックで必要な情報にアクセスできたり、スマホやタブレット端末からでも入力・閲覧しやすい設計になっていたりなど、使う人間目線の利便性が求められます。
無料で試せるトライアル期間が設けられたSFAなどを実際に社内に導入して使用感を試しながら、自社に合ったシステムを選ぶようにしましょう。
4.運用ルールを明確にする
SFAを定着させるには、社内での運用ルールを明確にすることも大切です。
「何を誰がいつどのような粒度で入力するか」を決めておけば、均質なデータを蓄積できるようになり、分析や活用が容易になります。会社名や担当者名の表記ルール、記録内容などは、あらかじめ定義しておくとよいでしょう。
また、データの質を保つには、管理者を設けて定期的にチェックする仕組みを作っておくと効果的です。
検証と改善を繰り返し、現場の声を反映した運用ルールづくりを行いましょう。
5.教育マニュアルや研修サポートを整備する
社内の担当者に対して教育マニュアルや研修サポートを行うことも、SFAの定着に役立ちます。
特に、SFAの導入がはじめての場合は、操作方法や利用価値についても半信半疑な場合が多いため、社内にSFAが定着するまでは内製化のプロに依頼し、わかりやすいマニュアルや研修を行ってもらうことも検討しましょう。
また、動画マニュアルやFAQ、チャット形式で質問できる窓口などを用意しておくと、現場担当者のストレスを軽減できるため、定着率の向上にも寄与するでしょう。
SFAが注目される理由
SFAが注目される理由としては、ビジネス環境の変化、複雑化・膨大化するデータ管理の限界、購買プロセスの変化の三つが挙げられます。
目まぐるしく変化するビジネス環境
新型コロナウイルスによる市場の混乱を経て、企業には不確実性への迅速な対応力が求められています。特に営業部門では、日々変動する売上データや商談進捗、顧客接点の情報をリアルタイムで把握し、柔軟に戦略を見直すことが重要です。
AIやIoTの進展に伴い、ビジネス環境はさらに複雑化しており、このような状況下で情報を一元管理できるSFAの導入意義が一層高まっています。
複雑化・膨大化するデータ管理の限界
ビジネスの現場では、顧客との接点や営業活動のあらゆる情報がデジタル化され、扱うデータ量は増え続けています。
商談の内容や所要時間、提案資料の閲覧履歴、失注の理由など、商談ひとつを取っても蓄積される情報は多くあります。しかし、こうした膨大なデータを紙やExcelなどで個別に管理しながら、リアルタイムに整理・分析して活用するのは、もはや現実的ではありません
情報が分散したままだと、欲しいデータがすぐに見つからない、誰がどこまで入力しているかわからない、といった非効率が生まれます。営業活動に関するデータ管理を容易にして、適宜活用できる仕組みを作るにはSFAの活用が欠かせないと言えるでしょう。
購買プロセスの変化
かつてはマスメディア中心の「プロダクトアウト型」が主流でしたが、インターネットとSNSの普及に伴い、顧客は事前に自ら情報収集し、口コミやレビューで商品・サービスを比較検討するようになりました。
企業との初接触前に意思決定が進む事例も増えており、従来型のアプローチだけでは機会損失が懸念されます。そのため、顧客の行動履歴や関心変化をリアルタイムで把握し、最適なタイミングでアプローチできるSFAの導入が不可欠です。
結果として、受注率の向上や効率的な営業プロセスの実現につながります。
SFAを活用するメリット
SFAを活用すると、どのようなメリットが得られるのでしょうか。
営業活動の効率化
営業で意外と時間をとられるのが日報業務です。株式会社ビーブレイクシステムズの調査では、日報業務にかかる時間は5分未満が21%、5〜10分未満が16%、10分以上30分未満が10%であることが分かっています。5分はほんのわずかな時間に感じますが、積み重なれば1カ月で1時間半、1年で20時間であり、けっして軽視できる数字ではないでしょう。
SFAでは、チェックボックスやプルダウン方式で日報の記入フローを簡略化できたり、オフィスに戻らずに外出先からでも簡単に日報作成が可能です。そのほか、営業成績や案件進捗などの各データをクロス集計したレポートも自動作成できるなど、データ分析やレポート作成業務の効率化にもなります。
株式会社ビーブレイクシステムズ「【番外編2】社内業務に関する実態調査(1)~日報・週報~」(2016)
営業の属人化の解消
一部のトップセールスの売上に依存してしまうと、トップセールスはマネジメント側に立てずに、現場に出続けて若手の営業が育たない状態になってしまいます。万が一、この状況でトップセールスが会社を離職した場合、会社は大きな損害を被るでしょう。SFAを使えば案件進捗状況や売上金額など営業に関するデータが蓄積されるだけでなく、お礼メールを送るタイミングや、初回商談のスクリプトなど今までブラックボックス化されていた成功要因も蓄積でき、営業全体のレベルを高めることができます。
営業活動の進捗管理が可能
紙やエクセルベースでも営業進捗を可視化できますが、営業メンバーが多いと、マネジャーは各担当の日報や報告書を全て読む必要があります。SFAを使うことで、メンバー一人ひとりの営業活動の進捗が一覧で可視化されるシステムもあるため、容易に停滞案件の発見・対策ができるようになります。
SFAをフル活用するポイントは、他システムとの連携

SFAを導入するだけでは、営業活動の効率化や成果の向上には直結しません。
重要なのは、SFAで得たデータを戦略的に活用して、実行可能なアクションへと落とし込むことです。
SFAの導入目的や運用ルールを明確にし、現場の営業担当者が「使う意味」を理解していれば、一定の成果は見込めます。
しかし、SFA単体では限界があるのも事実です。
CRMやMAといった他のシステムと連携することで、SFAの活用範囲はさらに広がります。
実際に、エレコム株式会社ではSansanを軸にSFAとMAのデータを整備し、営業とマーケティングを横断する情報基盤を構築。
見込み顧客の動きを部門を超えて把握できるようになり、受注率を約1.75倍にまで向上させています。
Sansan Data Hubの導入により、顧客情報のリッチ化が進み、連携先システム全体の価値も高まりました。
SFAを他システムと連携することは、点で存在していた顧客情報を線でつなぎ、営業の質とスピードを飛躍的に高める鍵となります。
まとめ
SFAは非常に有用なツールですが、導入が目的化しないよう、SFA導入後の運用方針を明確にすることが大切です。また、行動を監視するためではなく、業務を効率化するために活用するという導入意義を営業部署に伝えることで、スムーズに定着させることができるでしょう。
さらに、CRMやMAなどの他システムと連携させれば、より大きな効果を出すことができます。ただし、他システムの導入にはコストがかかり、システムに合わせた業務フローの見直しが必要になるため、事前に既存のシステムとの連携や、運用体制の整備など、導入計画を明確にしておくことが重要です。
運用方針と導入計画をしっかりと固めることで、SFAは営業現場の頼れるパートナーとなります。自社の現状と目標に合わせた運用体制を見直し、ぜひSFAのポテンシャルを最大化してください。
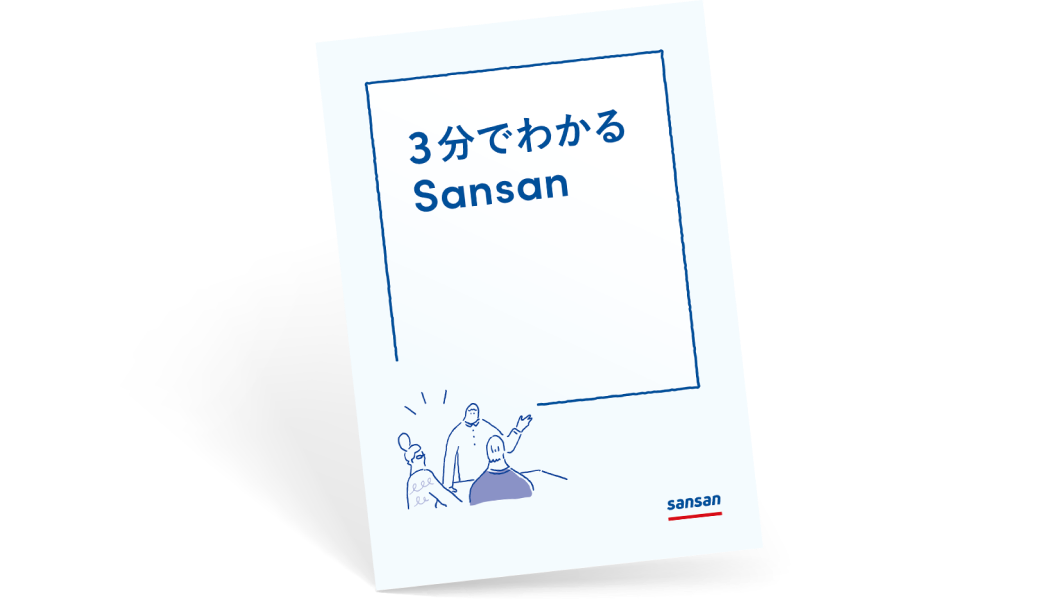
3分でわかる Sansan
営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部