- DX推進
SFAで案件管理を行うメリットは?導入方法や失敗しないためのポイントを紹介
公開日:
更新日:

SFAを活用した案件管理では、営業活動の可視化や業務効率の向上が実現できます。適切な導入計画と運用体制を整備すれば、失敗のリスクを大幅に軽減できます。
本記事では、SFAを活用した案件管理のメリット・デメリット、ツールの選び方を解説します。導入から運用までの各段階で注意すべきポイントもまとめているため、ぜひ参考にしてください。
営業現場に定着する
案件管理の基本

案件管理は、営業活動における顧客との商談や提案の進捗状況を一元的に把握する際に必要です。ここでは、案件管理とはどういったものなのか、また目的についても解説します。
案件管理とは
案件管理とは、商談や提案などの営業活動に関する情報を体系的に管理する手法です。顧客情報や商談履歴、見積情報などを一元管理し、営業活動の効率化を図ります。
営業担当者の経験やスキルに依存しない、標準化された管理方法を確立できます。組織全体で案件情報を共有することで、戦略的な営業活動の推進が可能です。
案件管理の目的
案件管理の主な目的は、営業活動の可視化と効率化を実現することです。営業担当者の行動履歴や商談進捗状況を正確に記録し、組織的な営業活動を展開します。
案件管理を通じて、売上予測の精度向上や営業戦略の最適化を図ることができます。経営判断に必要な情報を適切なタイミングで提供し、企業の成長を支援します。
SFAで案件管理を行うメリット
SFAによる案件管理を行えば、営業活動の効率化と生産性向上を実現します。ここでは、SFAで案件管理を行う具体的なメリットについて解説します。
営業活動の可視化につながる
案件の進捗状況や商談履歴をリアルタイムで把握し、組織全体で共有することが可能です。営業担当者の活動履歴や顧客とのコミュニケーション記録は、自動的に蓄積されます。
商談のステータスや成約確度を視覚的に確認できる点は、適切な判断と行動につながる重要な要素です。管理職は部下の活動状況を即座に把握し、サポートできます。
営業管理の手法やポイントについては、以下の記事を参考にしてください。
案件情報をもとに多角的な分析が期待できる
蓄積された案件データを活用し、商談の成功パターンや失敗要因を分析することが可能です。また、AI活用による売上予測や受注確度の算出は、精度の高い事業計画の立案に役立ちます。
過去の案件情報から、最適な提案手法や価格設定を導き出すやり方は非常に有効です。データに基づく戦略立案により、営業活動の質が向上するでしょう。
外部システムと連携できる
CRMやMAツールとの連携は、顧客情報の包括的な管理を実現します。また、会計システムとの連携により、受注から請求までの業務を自動化できます。
グループウェアとの連携は、スケジュール管理や情報共有を円滑にします。各システム間のデータ連携により、二重入力の手間を削減することが可能です。
一元管理で情報確認の手間を削減できる
案件に関するすべての情報を一元管理すれば、必要な情報に素早くアクセスできます。権限設定により、適切な情報アクセス制御を実施できます。
他にも、部門や担当者を越えた情報共有は、チーム全体の生産性向上につながります。データベースの一元化により、情報の整合性を維持できます。
対応漏れや二重対応を防げる
自動通知機能によって重要な案件の進捗や期限を確実に管理でき、担当者間の情報共有により顧客対応の重複を防げます。
タスク管理機能を活用することでフォローアップの漏れを防止し、適切なタイミングでの対応が可能になります。SFAのアラート機能を活用すれば、案件の停滞や異常を早期に発見できます。
SFAで案件管理を行うデメリット
SFAによる案件管理には、導入から運用まで複数の課題点が存在します。SFAで案件管理を行う具体的なデメリットについて解説します。
導入・運用に費用が発生する
SFA導入には初期費用と月額費用、カスタマイズ費用などが発生します。導入時の初期費用は無料のものから高額なものまで幅広い選択肢があり、月額費用は利用人数に応じて変動します。
費用対効果を最大化するには、必要最小限の機能から始め、段階的に拡張する方法が有効です。利用規模や期間に応じた料金プランを選択することで、コストを最適化できます。
日々の情報入力作業が負担になる
営業担当者は顧客情報や商談進捗を日常的に入力する必要があり、作業負担が大きな課題です。入力作業の負担軽減には、必要最小限の項目設定と入力手順の簡略化が重要な要素となります。
外部システムとの連携機能やデータ自動取り込み機能の活用は、手入力の作業量削減に効果的です。モバイル対応により外出先からの入力が可能となり、業務の柔軟性が向上します。
社内浸透に時間がかかる場合がある
SFAの本格運用までには、一定の準備期間が必要です。導入初期は特に若手とベテラン間で操作習熟度に差が生じやすく、運用の障壁となることがあります。
そのため、eラーニングや段階的な研修プログラムを実施し、全社員の理解度を均一化することが重要です。キーユーザーを育成し、部門別の運用ルールを策定することで、円滑な導入体制を構築できます。
Excel(エクセル)による案件管理には課題がある
Excelによる案件管理も可能ですが、リアルタイムな情報共有や分析が困難です。複数の営業担当者が同時に情報を更新すると、データの整合性が取れなくなる恐れがあります。
また、データの入力ミスや更新漏れによって、案件状況の正確な把握が難しくなります。案件情報の検索や分析にも時間がかかるため、迅速な意思決定を妨げる要因となります。そのため、SFAを活用した案件管理への移行が推奨されます。
案件管理で活用するSFAの選び方
SFA選定では自社の営業スタイルに合わせた機能要件の定義と、長期的な費用対効果の検討が必要です。ここでは、具体的なSFAの選び方について解説します。
必要最低限の機能を備えている
案件管理に必要な基本機能を備えているか、事前に確認することが重要です。必要最低限の機能は以下の通りです。
- 顧客情報管理
- 商談進捗管理
- 分析レポート機能
将来的な拡張性を考慮しながら、現状必要な機能を優先的に選定することが大切です。機能の取捨選択では、営業現場の意見を重視し、実務に即した要件定義を行いましょう。
無駄な機能を省いたシンプルな構成にすることで、導入後の運用負荷を軽減できます。
コストバランスが取れている
SFAの総保有コストは、導入費用や月額利用料、保守費用の合計で算出します。利用期間とユーザー数を考慮し、長期的な費用対効果を試算する必要があります。
機能と価格のバランスを見極め、自社の予算規模に適したプランを選択しましょう。無料トライアル期間を活用し、実際の使用感と効果を検証することが重要です。
サポート体制が充実している
導入支援からアフターフォローまで、一貫したサポート体制を持つベンダーを選択しましょう。導入実績や継続率の高さは、サポート品質を判断する重要な指標です。
マニュアルや研修プログラムの充実度、問い合わせ対応の迅速さを確認します。カスタマイズ要望への柔軟な対応力も、長期的な運用において不可欠な要素です。
SFAによる案件管理を実施するまでの6ステップ

SFAによる案件管理の導入は、6段階の実施手順に沿って進めます。各段階で明確な目標設定と達成基準を定め、計画的に導入を進めることが重要です。
ここでは、具体的な手順について解説します。
STEP1.プロジェクトチームの編成
プロジェクトチームを編成する際には、経営層や営業部門、IT部門から2〜5名程度で構成します。チームリーダーには営業現場を熟知した管理職を配置し、現場の意見を反映できる体制を整えましょう。
経営層からの明確な権限委譲を受け、社内周知を支援する随時メンバーを含めた体制構築が重要です。定期的なミーティングを設定し、進捗状況の共有と課題解決を図ります。
部門を越えた情報共有を実現するため、マーケティング部門とIT部門からの参画者を必ず含めることが必須です。各メンバーの役割と責任範囲を明確にし、意思決定のスピードを向上させます。
STEP2.現状分析と目的設定
現状の営業活動における具体的な課題を洗い出し、売上目標や商談件数目標、成約率目標など定量的な改善目標の設定が必要です。顧客関係性の深掘りなど、多角的な視点での目標設定が重要です。
部門別のヒアリングを実施し、現場の要望と課題の明確化が不可欠です。目標達成までの期間と具体的な施策を設定し、実行計画を策定しましょう。
データ分析による戦略立案を可能にするため、必要なデータ項目と収集方法の定義が重要です。各部門の業務フローを見直し、データ入力の負担を最小限に抑える運用ルールを確立します。
STEP3.必要機能の洗い出し
顧客情報管理や商談プロセス管理、活動履歴管理など基本機能の優先的な選定が必要です。既存システムとの連携可否を事前に確認し、開発費用や導入時期への影響を考慮します。
将来的な拡張性を考慮したシステム要件の定義が重要です。現場の意見を重視し、実務に即した要件定義を行いましょう。
データの統合と名寄せ機能を重視し、企業情報のリッチ化や外部データベースとの連携機能の検討が必要です。部門間でのデータ共有とアクセス権限の設計も、必須要件として含めます。
STEP4.運用準備
運用ルールと業務マニュアルを作成し、全社員への周知を図ります。既存データの移行計画を立て、データクレンジングと整備を実施しましょう。
テスト環境でのデータ移行を実施し、データの整合性を確認します。運用開始後のサポート体制を整備し、問い合わせ対応の準備を行いましょう。
既存データのクレンジングと標準化を行い、高品質なデータベースを構築します。部門別の運用手順書を作成し、データ入力の標準化と品質維持の仕組みを確立しましょう。
STEP5.システムの導入
システム環境の構築とテスト運用、動作確認を行います。部門別の研修プログラムに沿って、操作方法の習得を目指しましょう。
実施する際には、テスト期間中の課題を収集し、必要な改善を行うことが大切です。本番環境への移行計画を立て、段階的な切り替えを行います。
データの正確性と活用度を高めるため、部門横断的なワークショップを開催し、最善の方法の共有と定着を図りましょう。運用状況のモニタリング体制を構築し、継続的な改善を推進します。
STEP6.運用の実施
本格運用開始後は、利用状況と効果測定を定期的に行います。運用上の課題を収集し、必要な改善策を実施しましょう。
運用中はユーザーからのフィードバックを収集し、システムの改善に活用します。定期的な研修と情報共有により、継続的な活用を促進しましょう。
データ品質の維持とユーザーの活用度向上のため、定期的なレビューを実施することが大切です。
SFAによる案件管理で失敗しないためのポイント
SFA導入の成功には、明確な目的設定と組織全体での理解が不可欠です。ここでは、SFAによる案件管理を行う際の重要なポイントについて解説します。
導入目的を組織全体で共有する
SFA導入の目的と期待される効果を全社員が理解し、共有する必要があります。経営層からの明確なビジョン提示と、現場からの具体的な課題提起を組み合わせましょう。
定期的な進捗報告会や成功事例の共有により、組織全体での活用意識を高めることが可能です。数値目標の設定と達成状況の可視化により、具体的な成果を実感できます。
マーケティングやインサイドセールス、カスタマーサクセスなど、部門を越えた情報共有と連携体制の構築が重要です。
効率的なデータ入力が可能な設計にする
営業活動の本質に集中できるよう、データ入力の負担を最小限に抑えた設計が重要です。顧客基本情報や商談進捗状況、成約見込みなど、必須となる項目を現場の意見を取り入れながら決定しましょう。
データ入力の負担を最小限に抑えることで、営業担当者の本来の業務に注力できる環境を整えます。外部システムとの連携機能やデータ自動取り込み機能を活用し、手入力の作業量を削減することが効果的です。
部門別の運用手順書を作成し、データ入力の標準化と品質維持の仕組みを確立します。段階的な項目追加のアプローチを取ることで、運用負荷を抑えながら必要な情報を着実に蓄積できます。
サポート体制を充実させる
導入初期から運用定着まで、専門チームによる継続的なサポート体制を整えましょう。操作方法の研修やマニュアルの整備により、利用者の不安を解消することが可能です。
eラーニングや段階的な研修プログラムの実施により、全社員の理解度を均一化できます。部門別の運用手順書を作成し、データ入力の標準化と品質維持の仕組みを確立しましょう。
ヘルプデスクの設置や定期的なフィードバック収集は、問題点の早期発見と改善に役立ちます。ベンダーのサポートサービスを活用することで、専門的な支援を受けられる体制を構築できます。
まとめ
SFAによる案件管理は、営業効率の向上と成果の最大化を実現する手段として有効です。
ツールを段階的に導入し、継続的に改善を図ることで、営業ノウハウの標準化と営業力の強化が期待できます。加えて、データに基づいた戦略の立案と実行により、競争優位の確立と収益性の向上が見込まれます。
Sansanは、名刺管理を超えたビジネスデータベースです。スキャナやスマートフォンから名刺を取り込むだけで、正確に名刺情報がデータ化されるため、改めて顧客情報の入力をする必要がなく、営業現場の業務の効率化に役立てることが可能です。詳しくは、下記資料をご覧ください。
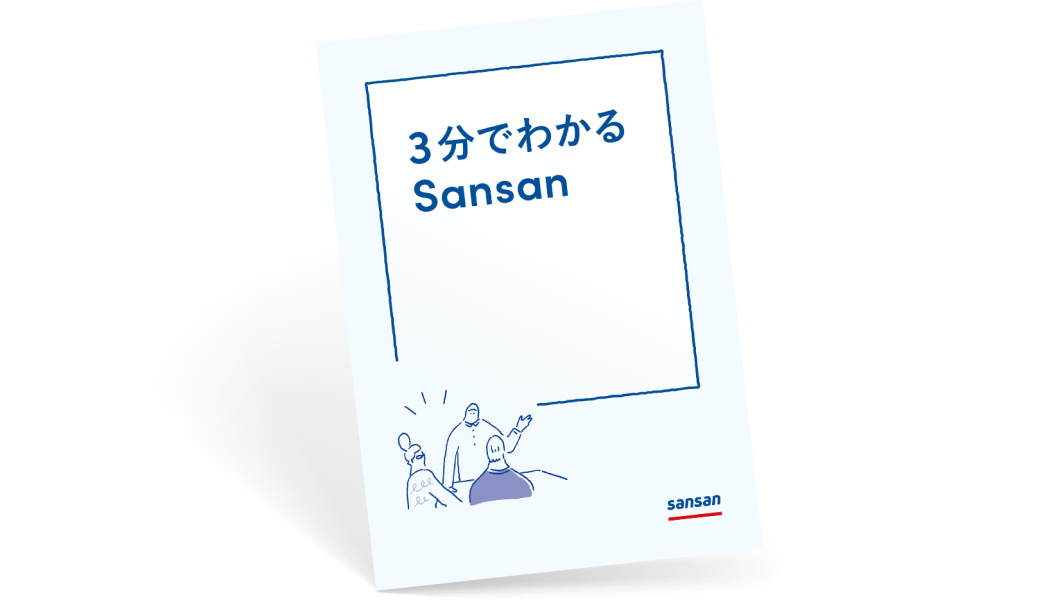
3分でわかるSansan
ビジネスデータベース「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部
.png)
