- 経営・ビジネス全般
データ統合とは?企業が取り組むべき理由と進め方・活用事例を解説
公開日:
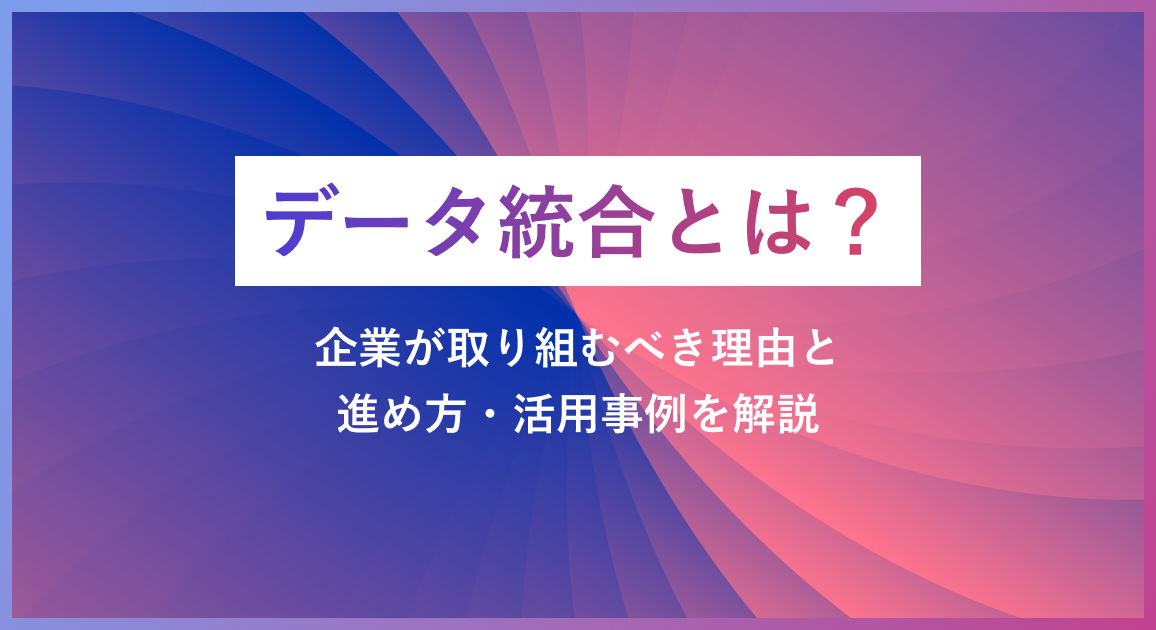
データ統合は、企業がDXを進める上で欠かすことのできない取り組みです。正しくデータを統合できれば、ビジネスの生産性や売上アップなどにつながります。しかし、自社に散らばったデータを精査してビジネスに活用するには、事前にルールを決めて必要な情報に絞り込むことが大切です。本記事では、データ統合の目的やメリット、進め方などを事例つきで解説します。
データ統合とは
データ統合とは、企業内外に点在するさまざまな形式や保存場所のデータをひとつにまとめて、共通のルールやフォーマットで一貫して扱えるようにする取り組みです。
部門やシステムごとに分かれて管理されていた、顧客情報や取引履歴、業務データなどを横断的に整理して、全社で活用できる状態に整えるのが目的です。
統合されたデータは、営業・マーケティング・経理など複数部門の意思決定を支える基盤となり、DX推進の土台にもなります。
リアルタイムかつ正確なデータ活用が進むことで、業務の生産性向上や売上拡大、経営判断の質向上につながるでしょう。
データ統合の目的

では最初に、データを統合する理由、目的についてを詳しく解説します。
DXを促進するため
DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するには、部門やシステムを越えて情報をつなげる取り組みが重要です。
データ統合はそのための基盤となり、企業全体のデジタル活用を支える役割を果たします。
従来は個別最適で運用されていた業務プロセスも、データを統一的に管理すれば、全体最適化の視点から再設計が可能になります。分散した情報を整理し、リアルタイムで活用できる環境を整えることが、DX施策のスピードと精度を高める重要なカギとなります。
生産性を向上させるため
データ統合によって、必要な情報をすぐに探し出せる環境が整えられると、業務の入力・検索・確認作業の手間を大幅に削減できます。
情報共有に伴うミスや重複作業も減らせるため、業務全体のスピード感が向上できるでしょう。結果として、現場での判断や業務遂行の能力が底上げされ、組織全体の生産性向上につながっていきます。
保有データを可視化するため
データ統合は、企業が保有する情報資産の可視化するうえでも大きな効果を発揮します。
複数のシステムや担当者に散らばっていた情報を整理・統一することで、データの可視化が進み、属人化の排除やリスクの早期把握にもつながります。
全体像が見えることで、新たな戦略立案やデータ分析の基盤が整い、経営判断の質とスピードを高められるでしょう。
データ統合4つのメリット
次に、データ統合を実現することで得られるメリットについてそれぞれ見ていきましょう。
1.データを迅速に取得できる
複数のシステムに分散していた情報が統合されると、必要なデータにすばやくアクセスできるようになります。
迅速にデータを取得できれば、営業活動や経営判断のスピードも上がります。その結果、機会損失リスクを低くできるでしょう。今まで眠っていたデータを活用する機会も増えるため、業務の生産性や効率化なども可能です。
2.データ活用が全社で可能になる
データが統合されることにより、部門を超えて共有できるようになります。
営業部門、マーケティング部門、管理部など、多様な部署で横断的にデータが活用できるので、組織としての一貫性を保つためにも役立ちます。
データ統合によって、特定の担当者や部署に依存しない環境の構築が可能になるでしょう。
3.セキュリティ対策がしやすくなる
データ統合は、セキュリティ対策の面でもメリットがあります。情報が統一された環境で管理されると、アクセス権限やログ管理を一元化できます。
これにより、分散管理による漏洩や管理漏れのリスクが減少して、情報の取り扱いルールも整備しやすくなるでしょう。ガバナンス強化やコンプライアンス対応の観点からも、セキュリティレベルの向上につながります。
4.運用コストを削減できる
複数のツールやデータベースを管理する手間が減ることで、システム運用にかかる重複コストを抑えられるのもメリットです。
手作業や属人的なデータ処理を減らせると、業務効率が改善して人件費の削減につながるでしょう。データの整備・連携・保守といった作業の負担が軽減され、IT部門のリソースも最適化できます。
データ統合の進め方

データ統合は一度にすべてを完了させるものではなく、段階的かつ着実に進めていく意識が大切です。
ここでは、実際に取り組む際の基本的なステップを5段階に分けて解説します。
ステップ1:統合の目的を明確にする
データ統合を始める前に、まず「なぜ統合を行うのか」という目的を具体的に定めることが不可欠です。
例えば、以下のような目的があげられます。
- 営業効率を向上したい
- 経営判断を迅速化したい
- ガバナンスを強化したい
目的が曖昧なまま統合プロジェクトを進めると、統合後の運用が定着せず、期待した効果を得にくくなります。
また、目的によって統合の範囲や対象データの選定も変わります。
そのため、関係する部門と目的を共有し、全社的な合意形成を行ったうえで、プロジェクトの方向性を明確にする取り組みが重要です。
ステップ2:統合するデータを洗い出す
目的が定まったら、次に統合対象となるデータを洗い出します。
現状、社内外にどのような情報が存在しているのか、どのシステムや担当者が管理しているのかを整理しましょう。
統合対象になるデータの例は以下のとおりです。
- 顧客情報
- 取引履歴
- 請求・入金データ
- サポート対応履歴
- マーケティングデータ
各部門に分散している情報を一覧化することで、統合の全体像が見えてきます。
統合するデータの洗い出しを行うと、情報の重複や不足といった課題にも気づけるため、データ整備や連携設計の質を高めるうえでも有効です。
ステップ3:データを整備・加工する
統合する情報が定まったら、データの整備と加工を行います。
表記揺れや欠損、古い情報が混在している場合、そのままでは正確な分析や活用が難しいです。適切にデータを生かせるようになるには、名寄せやクリーニングといったデータ整備が欠かせません。
データを整備する際は、ETLツールを使うのがおすすめです。
ETLツールは、抽出・変換・格納のステップを自動化できるシステムで、社内に散財するデータを連携しやすいように自動で処理します。データの形式や表記の統一、不要データの除外を行い、統合後のデータ品質を高めることが可能です。
各データを自社にとって使いやすい形に整えておき、活用できる体制を整えておきましょう。
ステップ4:統合方法と基盤を選定する
整備したデータをどのように統合し、どのプラットフォームで運用するのかを選定するステップです。
代表的な選択肢には、以下のようなものがあります。
DWH | 大量のデータを蓄積し、分析用途に特化したデータベース。主に経営層や分析担当者が使うBIツールとの連携に適しています。 |
|---|---|
CDP | 顧客データを一元化し、マーケティング施策やパーソナライズの基盤として活用する仕組み。マーケティング部門での活用性が高い。 |
仮想統合 | データを物理的に移動せず、既存システムに残したまま仮想的に統合して見せる手法。システム改修を抑えつつ迅速に統合を実現したい場合に有効です。 |
これらの基盤は、それぞれ特性や得意領域が異なります。
データ統合を実現するには、現行システムとの親和性や運用負荷、将来的な拡張性なども考慮して、目的に合った方法を選択することが大切です。
まずはスモールスタートとして一部のデータや部門から段階的に展開し、実績を積みながら全社展開へと進めるアプローチが現実的と言えるでしょう。
ステップ5:活用と改善の体制を整える
データ統合は導入した時点がゴールではなく、そこからが本当のスタートです。
真価を発揮するには、データが活用される仕組みと、継続的な改善サイクルを組織に根付かせる取り組みが求められます。
具体的には、アクセス権限や運用ルール、データ分析のフローなどを明確化して、各部門が責任を持って運用できる体制の構築を目指しましょう。
また、データの精度や活用状況を定期的に見直すことで、企業全体としてのデータ活用文化が根づいていきます。
継続的な改善が定着すれば、データ統合の効果はより大きな成果へとつながっていくでしょう。
データ統合の活用事例

ここではデータ統合の活用事例を紹介します。
データの正規化・統合によってビジネスの効率性や正確性が向上した事例
日本ビジネスシステムズ株式会社では、名刺情報の手入力による工数やミス、顧客データの重複・散在などが課題となっていました。
Sansanを全社導入し、Microsoft Dynamics 365とのAPI連携により、名刺をスキャンするだけでCRMに最新の顧客情報が自動反映される環境を構築しました。その結果、データ入力の手間と時間が大幅に削減されました。
また、Sansan Data Hubの活用により、約4,200件の重複データを短期間でクレンジング。表記揺れや古い情報も正規化され、顧客データの正確性が大きく向上しました。
営業担当者は顧客接点を即座に把握できるようになり、適切なアプローチや組織横断的な連携が実現しました。
昇進や転職といった最新情報の自動通知も、継続的な関係構築や機会損失の防止に貢献しています。
データ統合でよくある課題と注意点
データ統合は多くのメリットをもたらす一方で、進め方を誤ると期待した効果を得られないケースも少なくありません。
ここでは、よく見られる課題と、それを防ぐためのポイントを解説します。
課題1.目的やスコープが曖昧なまま統合を進めてしまう
「とにかくすべてのデータをまとめよう」と、目的が曖昧なままで統合を進めると、どのように活用するのかが不明確になりやすいです。
例えば、営業業務の効率化を目的としていたはずが、最終的に経理系データまで統合対象に含めてしまい、整備コストばかりかかって活用が進まないといったケースもあるでしょう。
こうした事態を防ぐためには、データ統合のゴールを明確に定義したうえで、必要なデータのみを対象とすることが重要です。
課題2.現場で使いにくいデータになってしまう
データ統合そのものは完了しても、現場で使いづらい設計になっていると、せっかくのデータが活用されずに終わってしまうこともあります。
営業部門からは「案件ごとの最新担当者がすぐに把握できない」といった声がある一方、マーケティング部門からは「セグメント抽出のための検索項目が足りない」といった声が上がるといったケースも珍しくありません。
また、システムの更新フローが複雑すぎて、現場で運用が回らなくなることもあります。
こうした問題を防ぐには、導入前から利用部門のニーズを把握して、実務に沿った形で設計・運用を行う取り組みが大切です。
課題3.全社導入を急ぎすぎてコストが増大してしまう
はじめから全社導入を目指すと、調整範囲や合意形成にかかる時間が大きくなります。
その結果、システム構築や教育にかかるコストも膨らみやすくなるため注意が必要です。
特に、多部門を一度に巻き込もうとすると、部門間で求める要件や優先順位にズレが生じやすく、プロジェクトの遅延や設計変更につながるケースが少なくありません。
こうしたリスクを避けるためには、まず一部の部署やプロジェクト単位でスモールスタートを切り、効果やノウハウを蓄積しながら段階的に展開していくのが現実的です。
初期フェーズの成功事例が社内で共有されれば、他部門への展開もスムーズに進めやすくなります。
まとめ
データ統合は、企業全体でのデータ活用を可能にし、DX推進や業務の生産性向上を支える重要な取り組みです。
一方で、目的や活用範囲が曖昧なまま進めたり、現場の使い勝手を考慮せずに設計したりすると、期待した効果が得られないケースもあります。
効果的なデータ統合を実現するには、明確なゴールを定めたうえで必要なデータに絞って統合を進め、実務フローに即した設計・運用を行うことが大切です。
散らばった顧客データを統合したいときにおすすめなのがビジネスデータベースのSansanです。
Sansanは顧客情報の一元管理や営業活動の可視化、データ分析機能など、業務を効率化する多様な機能を提供しています。
データ統合について考えている場合は、ぜひSansanの導入をご検討ください。
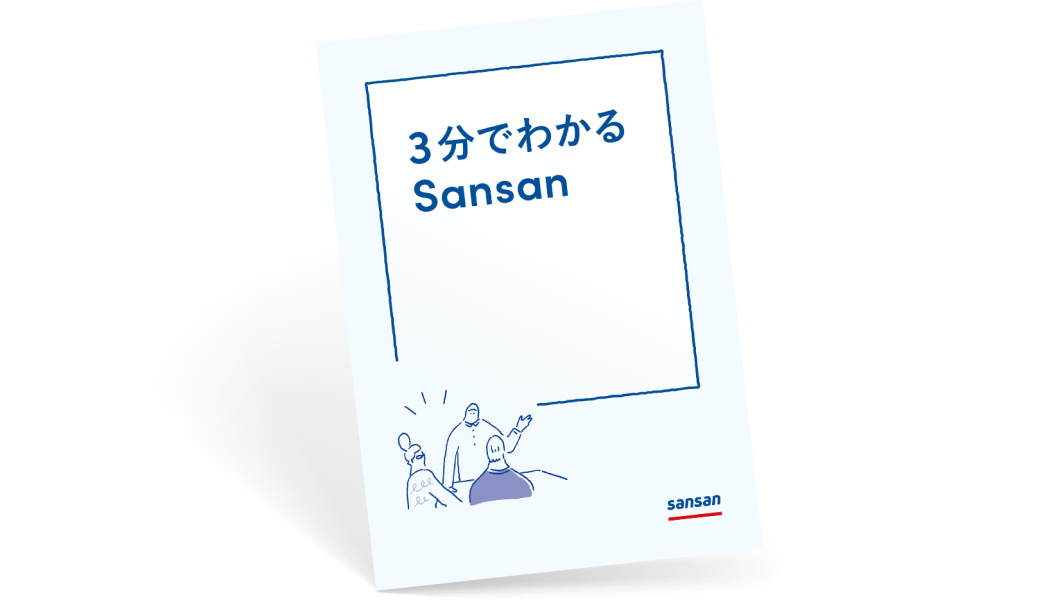
3分でわかるSansan
ビジネスデータベース「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部
