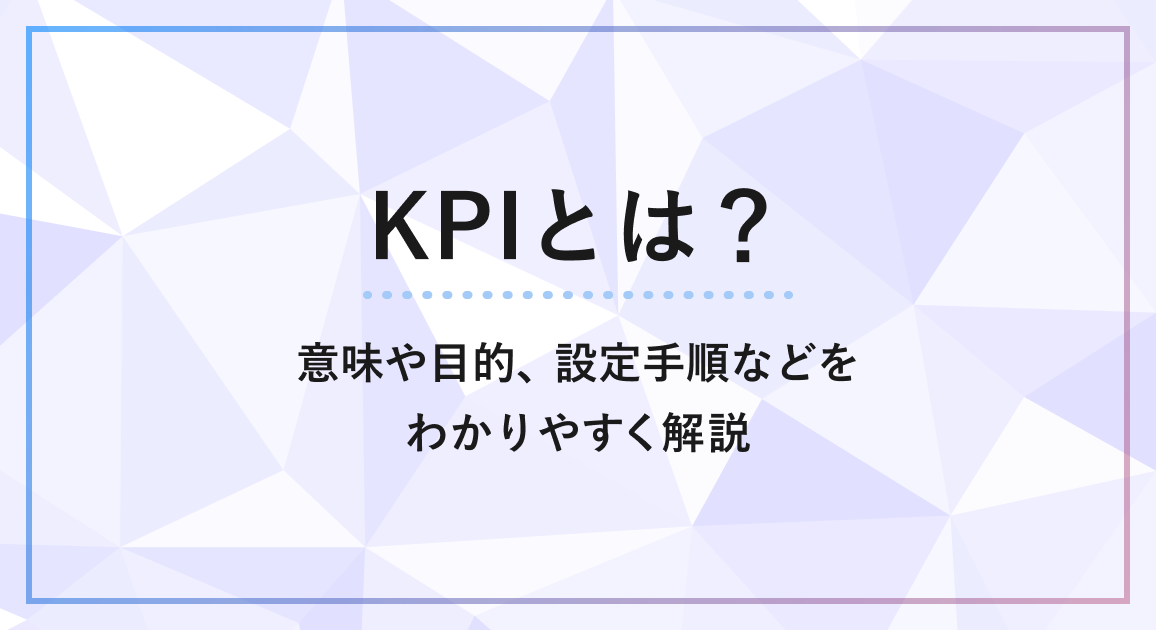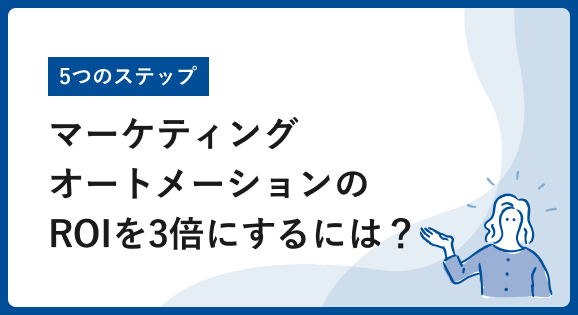- マーケティングノウハウ
展示会マーケティングとは?具体施策や成功のためのポイントを徹底解説
公開日:
更新日:
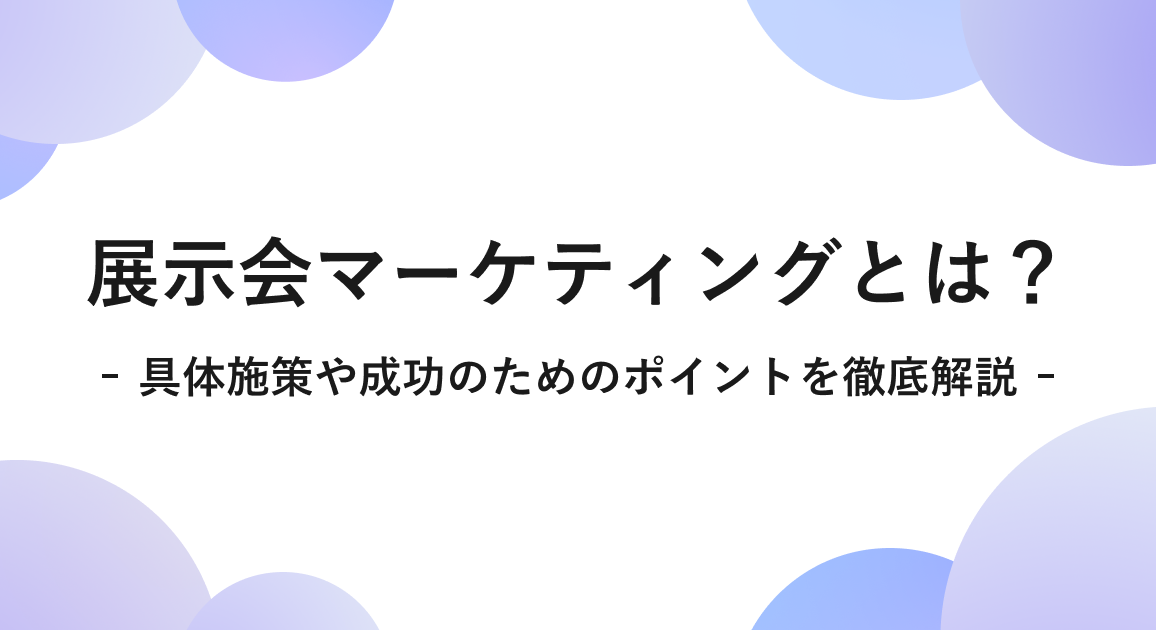
近年、多くの企業が効果的なマーケティング戦略の一環として展示会を活用し始めています。展示会マーケティングは、直接顧客と接点を持てる貴重な機会ですが、単に出展するだけでは十分な効果は得られません。成功には戦略的なアプローチが不可欠です。本記事では、展示会マーケティングの基本から効果的な実施方法、そして成果の測定まで、詳しく解説していきます。
展示会マーケティングとは
展示会マーケティングとは、展示会という場を活用して行うマーケティング活動のことです。展示会とは企業出展者が自分たちの商品やサービスを紹介し、顧客を獲得する場を提供しているイベントを指します。
展示会マーケティングは、他のマーケティング活動と比較すると、顧客との直接的なコミュニケーションが可能であり、製品やサービスを実際に体験してもらえるという特徴があります。また、業界関係者との交流や、顧客の反応をその場で確認できるという即時性も大きな魅力です。
このように、展示会マーケティングの効果は多岐にわたります。ブランド認知度の向上はもちろん、質の高いリードの獲得など、さまざまな面でビジネスに貢献するのです。さらに、競合他社の動向把握や市場トレンドの学習にも役立ちます。
展示会出展の主な目的

展示会に出展することは、さまざまな目的で多くの企業が行っています。
主な目的は以下の4点です。
- 企業ブランディングの強化
- 質の高いリード獲得
- 製品・サービスの認知度拡大
- 既存顧客との関係深化
1.企業ブランディングの強化
展示会は、企業イメージを向上させ、業界における認知度を高める貴重な機会です。特に新規参入企業や知名度の低い企業にとって、展示会は自社の存在をアピールする絶好の場となります。
効果的なブランディングと認知度向上を図るためには、まずブースデザインに注力することが重要です。企業カラーやロゴを効果的に使用し、印象的な装飾を施すことで、来場者の目を引くことができるでしょう。
AR/VR体験コーナーを設置したり、環境に配慮した素材を使用してSDGsへの取り組みをアピールしたりするのも効果的です。これらの工夫により、知名度に関わらず、来場者の興味を引きつけることが可能となります。
プレゼンテーションも重要な要素です。定期的なミニセミナーの開催やデモンストレーションの実施、専門知識を持つスタッフによる丁寧な説明など、さまざまな方法で自社の強みを伝えることができます。
これらの取り組みにより、業界内での存在感を高め、ターゲット顧客に直接的にブランドメッセージを伝えることが可能となります。また、長期的かつ継続的な出展を通じて、徐々に業界における認知度と信頼性を構築していくこともできるでしょう。
2.質の高いリード獲得
展示会では、自社の製品やサービスに興味を持つ見込み客と直接対話する機会が豊富にあります。この対面でのコミュニケーションを通じて、より深い関係を構築し、具体的なニーズや課題を把握することが可能です。
例えば、来場者とのヒアリングを通じて、「現在使用している製品の課題点」や「今後導入を検討している技術」などの情報を収集できます。こうした情報は、その場での提案に活用できるだけでなく、展示会後のフォローアップにも役立つでしょう。
また、展示会では業界の意思決定者や影響力のある人物と接触できる可能性が高いため、通常のマーケティング活動では得られないような質の高いリードを獲得できる可能性があります。
3.製品・サービスの認知度拡大
展示会は、新製品や新サービスのローンチの場としても最適です。多くの来場者や業界関係者が集まる展示会で新製品を発表することで、一度に大きな注目を集めることができます。
実際のデモンストレーションを通じて、製品の価値を直接的にアピールできるのも展示会の強みです。例えば、ソフトウエア企業であれば、実際の操作画面を大型スクリーンに映し出し、リアルタイムで機能を紹介することができます。製造業であれば、製品のプロトタイプを展示し、来場者に実際に触れてもらうことで、その品質や機能性を体感してもらうことができるでしょう。
さらに、展示会はメディアや業界関係者への効果的な情報発信の場としても活用できます。プレスリリースを配布したり、メディア向けの特別セッションを設けたりすることで、自社の新製品や技術革新について広く周知することが可能です。
4.既存顧客との関係深化
展示会は、既存顧客との再接触の機会としても非常に重要です。日々の業務で直接会う機会が少ない顧客とも、展示会という場で改めてコミュニケーションを取ることができます。この機会を利用し、新製品や新サービスの紹介を行うことで、クロスセルの機会を創出できるでしょう。
例えば、すでにある製品を利用している顧客に対して、関連する新サービスを提案するなど、顧客のニーズに合わせた提案が可能です。
また、展示会は顧客からのフィードバックを直接収集できる貴重な機会でもあります。現在使用中の製品やサービスについての感想や改善点を聞くことで、今後の製品開発や顧客サービスの向上に生かすことができるでしょう。このような双方向のコミュニケーションを通じて、顧客との信頼関係をさらに深めることができるのです。
展示会に出展するメリット
ここまで、展示会に出展する目的について解説していきましたが、ここではメリットについて解説していきます。展示会に出展するメリットは、主に以下の4点です。
- 業界のキーパーソンとの直接的な接点創出
- 他のマーケティング施策との相乗効果
- 競合他社の動向把握と市場トレンドの学習
- 製品・サービスの即時フィードバック収集
1.業界のキーパーソンとの直接的な接点創出
展示会の最大の魅力の一つは、企業の重要人物と直接対話できる機会が得られることです。通常のビジネス環境では接触が難しい企業の経営者や役員、製品やサービスの購買担当者、業界のアナリストやコンサルタントなどと対面で交流できます。
例えば、大手企業の調達責任者が各ブースを回り、新たなサプライヤーを探している場合などがあります。このような場で自社の製品や技術をアピールできれば、新規取引につながる可能性が大いに高まるでしょう。また、業界の著名人や見識者などと知り合うことで、将来的な協業や情報交換の機会を得ることも可能になるのです。
2.他のマーケティング施策との相乗効果
展示会マーケティングは、他のマーケティング施策と組み合わせることで、より大きな効果を生み出します。
ソーシャルメディアと連携することで、展示会の前後で効果的なプロモーションが可能となるでしょう。展示会前にはブース来場を促す投稿を行い、展示会中はリアルタイムで情報を発信、展示会後は成果報告や関連コンテンツの共有を行うといった具合です。
また、展示会での出来事や成果は、その後のコンテンツマーケティングの貴重な素材にもなるでしょう。
例えば、展示会で行ったプレゼンテーションを基にしたホワイトペーパーの作成や、来場者の声を集めた事例紹介記事の制作などが考えられます。このように、オンラインとオフラインの両面からアプローチすることで、より包括的なマーケティング戦略を展開できるのです。
3.競合他社の動向把握と市場トレンドの学習
展示会は、競合他社の製品やサービスを直接観察できる絶好の機会です。他社のブースを訪れることで、最新の製品ラインアップや価格戦略、プロモーション手法などを詳しく知ることができます。
例えば、ある IT 展示会で競合他社が AI を活用した新サービスを発表していたことから、自社の製品開発の方向性を見直すきっかけとなったケースもあります。
さらに、展示会全体を通じて業界の最新トレンドや技術動向を把握することができます。基調講演やセミナーセッションに参加することで、業界のリーダーや専門家の見解を直接聞くこともできるでしょう。こうした情報は、自社の戦略立案や製品開発に生かすことができ、市場競争力の向上につながります。
4.製品・サービスの即時フィードバック収集
展示会では、自社の製品やサービスに対する顧客の反応をリアルタイムで観察し、即座にフィードバックを得ることができます。
例えば、新製品のデモンストレーションを行う際、来場者の表情や質問の内容から、製品の魅力や改善点を直接読み取ることが可能です。
開発側が想定していない使い方や、営業パーソンが訴求するつもりではなかったポイントが潜在顧客に刺さる可能性が十二分にあります。展示会で得られる生の声は、製品改善のための重要なインプットとなり、より市場ニーズに合った製品開発につながるのです。
効果的な展示会マーケティングに必要な準備事項

効果的な展示会マーケティングの実現には、必要な準備事項を押さえておくことが重要です。主な準備事項は以下の4点になります。
- 明確なKPI設定と目標の具体化
- 自社商材に最適な展示会の選定
- ターゲット顧客への戦略的な案内状送付
- 魅力的なブースデザインと来場者体験の設計
1.明確なKPI設定と目標の具体化
展示会マーケティングの成功には、明確な目標設定が不可欠です。
具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定することで、展示会の成果を客観的に評価できます。
例えば、以下のような指標が考えられます。
- 名刺交換数:500件
- 新規リード獲得数:100件
- 商談化率:20%
- 成約率:5%
- 展示会特設ページのPV数:5000回
これらの数値目標を設定することで、チーム全体で共通の目標に向かって取り組むことができます。また、目標達成のための具体的な行動計画も立てやすくなるでしょう。
2.自社商材に最適な展示会の選定
展示会への出展は、相当な投資を必要とします。そのため、自社の製品やサービスに最適な展示会を慎重に選ぶ必要があります。選定の際は、以下のような点を考慮しましょう。
まず、ターゲット顧客との適合性を確認します。展示会の来場者プロフィールや展示会のテーマ、対象とする業界などが自社のターゲット層と一致しているかを検討しましょう。
次に、展示会の規模と影響力を評価します。業界内での認知度や過去の来場者数、メディアの注目度などを調査するのがおすすめです。
さらに、費用対効果の予測分析も行います。出展にかかる総コスト(ブース代、人件費、制作費など)と期待される成果(リード獲得数、商談件数など)を比較検討しましょう。
これらの調査・検討を通して、自社の業界や製品特性に合った最適な展示会を選ぶことが準備段階では必要です。
3.ターゲット顧客への戦略的な案内状送付
展示会の成功には、事前の集客活動が重要です。ターゲット顧客に向けて、戦略的な案内状を送付することで、自社ブースへの来場を促すことができます。案内状は単なる開催告知ではなく、顧客にとっての価値を明確に伝えるものでなければなりません。
例えば、展示会で初公開する新製品の情報や、特別セミナーの案内など、来場する意義を具体的に示すことが大切です。
また、パーソナライズされたメッセージを作成することで、顧客の興味を引き出すことができます。過去の取引履歴や問い合わせ内容に基づいて、各顧客に合わせた提案や特別オファーを盛り込むのも効果的です。
案内状を送付した後のフォローアップも忘れずに行いましょう。電話やメールでの再確認を通じて、事前アポイントメントを獲得できれば、より確実な商談機会を確保できます。
4.魅力的なブースデザインと来場者体験の設計
効果的な展示会マーケティングには、視覚的にも機能的にも魅力的なブースデザインが欠かせません。ブースは自社のブランドイメージを体現する空間であり、来場者の記憶に残る体験を提供する場所でもあります。
例えば、テクノロジー企業であれば、最新のデジタルサイネージや創造的な展示を取り入れることで、革新的なイメージを演出できます。一方、環境に配慮した製品を扱う企業なら、リサイクル素材を使用したブース設計で、自社の理念を視覚的に表現することができるでしょう。
また、来場者の動線を考慮したレイアウトも重要です。製品展示エリア、商談スペース、デモンストレーションコーナーなどを効果的に配置し、スムーズな案内ができるよう工夫しましょう。
このような要素を導入することで、来場者の滞在時間を延ばし、より深い製品理解を促すこともできます。
展示会マーケティングで実施すべき効果的な施策
それでは展示会マーケティングで実施すべき効果的な施策を紹介していきます。
特に重要なのは以下の4点です。
- インパクトのあるデモンストレーションの実施
- 注目を集めるプレスリリースの配信
- 展示会の成果を宣伝する記事や動画配信
- 獲得した名刺情報を活用したメルマガ配信
1.インパクトのあるデモンストレーションの実施
展示会では、製品やサービスの特長を視覚的に伝えるデモンストレーションが効果的です。単なる説明ではなく、実際の使用シーンを再現したり、来場者が直接体験できるような工夫を凝らしましょう。
例えば、ロボット技術を扱う企業であれば、実際にロボットを動かしてその精度や技術力をアピールすることができます。ソフトウエア企業なら、リアルタイムでデータ分析を行い、その結果を大画面で表示するといった演出も考えられます。
また、来場者参加型のデモを企画するのも良いでしょう。製品を実際に操作してもらうことで、その使いやすさや効果を体感してもらえます。専門スタッフによる丁寧な説明を組み合わせることで、より深い理解と興味を引き出すことができるでしょう。
2.注目を集めるプレスリリースの配信
展示会での新製品発表のタイミングに合わせたプレスリリースの配信は、メディアの注目を集めることができます。プレスリリースでは、新製品の特徴や市場での位置づけ、開発背景などを明確に伝えることが重要です。
また、業界メディアへの事前情報提供も検討しましょう。独占取材の機会などを設けることで、より詳細な記事掲載につながる可能性があります。
プレスリリースの内容は、技術的な詳細だけでなく、その製品が解決する社会課題や、もたらす価値なども含めると、より広い層の関心を引くことができるでしょう。
3.展示会の成果を宣伝する記事や動画配信
展示会終了後も、その成果を積極的に発信することが重要です。展示会のハイライトをまとめたブログ記事を作成したり、ブースでのプレゼンテーションやデモの様子を動画にまとめたりすることで、展示会に参加できなかった人にも情報を届けることができます。
例えば、「展示会で最も質問が多かった5つのポイント」といった記事や、「新製品デモンストレーション動画」などのコンテンツを制作し、自社ウェブサイトやSNSで公開しましょう。
また、来場者のインタビューや感想を取り入れることで、第三者の視点からの評価を示すこともできます。これらのコンテンツは、展示会後の商談フォローアップにも活用できる貴重な資料となります。
4.獲得した名刺情報を活用したメルマガ配信
展示会で獲得した名刺情報は、その後のマーケティング活動における重要な資産となります。これらの情報を活用し、セグメント別のフォローアップメールを設計しましょう。
例えば、製品に強い関心を示した来場者には詳細な資料や見積もりを送付し、情報収集段階の来場者にはより基本的な製品情報や事例紹介を送るなど、興味の度合いに応じたコンテンツを提供します。
また、展示会特別オファーの案内を行うことで、具体的な商談につなげることもできます。ただし、メール配信の際は必ずオプトアウトの選択肢を設け、受信者のプライバシーに配慮することを忘れないようにしましょう。
定期的な情報提供を通じて関係を維持し、長期的なナーチャリングを行うことが、質の高いリードを育成する上で重要です。
展示会マーケティングの効果を測定する方法

最後に展示会マーケティングの効果を測定する方法について解説していきます。
主な方法は以下の5点です。
- 設定したKPI指標の達成度評価
- 投資対効果(ROI)の詳細な分析
- フォローアップ架電によるアポイントメント獲得率の測定
- 展示会後のメルマガの開封率/クリック率/返信率の追跡
- SNSやWEB上での反響と言及の定性的・定量的分析
1.設定したKPI指標の達成度評価
展示会の効果を正確に把握するためには、事前に設定したKPI指標の達成度を評価することが重要です。例えば、以下のような指標が考えられます。
- 交換名刺数:目標600枚に対して実績700件
- 獲得リード数:目標100件に対して実績120件
- 商談化率:目標20%に対して実績25%
- ブース来場者数:目標500人に対して実績600人
これらの数値を分析することで、展示会マーケティングの成功度合いを客観的に評価できます。また、目標を達成できなかった指標があれば、その原因を探り、次回の改善につなげることが大切です。
KPIについては下記記事で詳しく解説しているので、ご参照ください。
2.投資対効果(ROI)の詳細な分析
展示会への参加には相当なコストがかかるため、投資対効果(ROI)の分析は非常に重要です。まず、展示会関連の総支出を算出します。主な項目としては、ブース出展料、ブース設営費、交通費・宿泊費、人件費、販促物制作費などが挙げられます。
次に、展示会を通じて得られた直接的な売上貢献を測定します。例えば、展示会をきっかけに成立した契約の総額や、展示会後の一定期間内に獲得できた新規顧客からの売り上げなどを集計します。
以下はROIの計算式の例です。
ROI = (展示会による利益 - 展示会への総投資額) / 展示会への総投資額 × 100
例えば、総投資額が500万円で、展示会による利益が700万円だった場合、ROIは40%となります。この数値が高いほど、投資効果が高かったと言えます。
ただし、展示会はリード獲得が目的なことが多いため、直接的な利益につながらない場面もあります。
短期間での効果ではなく、長期的な視野で分析すると良いでしょう。
3.フォローアップ架電によるアポイントメント獲得率の測定
展示会後のフォローアップ活動の効果も重要な指標です。
例えば、フォローアップ架電によるアポイントメント獲得率を測定することで、リードの質や営業アプローチの適切さを評価できます。
この指標は、展示会でのブース来場者の関心度と、その後の営業活動の効果性を直接的に反映します。また、時系列での分析を行うことで、最適なフォローアップのタイミングを特定し、将来の展示会戦略の改善にも活用することが可能です。さらに、アポイントメント獲得率を商談成立率と組み合わせて分析することで、展示会参加の投資対効果(ROI)をより正確に把握することが可能になります。
4.展示会後のメルマガの開封率/クリック率/返信率の追跡
展示会後に配信したメールマガジンの開封率、クリック率、返信率なども追跡しましょう。これらの指標は、コンテンツの魅力度や、リードの温度感を把握する上で有用です。セグメント別に分析することで、より効果的なフォローアップ戦略を立てることができます。
例えば、特定の業種や役職に対して高い反応率が見られた場合、そのセグメントにより焦点を当てたコンテンツ作成や営業活動の優先順位付けをするとよいでしょう。また、時間帯別の開封率を分析することで、最適なメール配信タイミングを特定し、よりリーチ率の高いコミュニケーション戦略を構築できます。
これらの指標の推移を長期的に追跡することで、リードナーチャリングの効果や、展示会後の顧客エンゲージメントの持続性を評価することが可能になるのです。
5.SNSやWEB上での反響と言及の定性的・定量的分析
展示会の効果は、オンライン上での反響からも測定できます。展示会関連のハッシュタグの使用状況や、自社の展示会出展に関するSNSでの言及数などを分析しましょう。また、展示会後の自社ウェブサイトのPV数の変化や、特定のランディングページへのアクセス数なども、認知度向上の指標となります。
メディア掲載やブログ記事の数と内容も、展示会の影響力を測る重要な要素です。これらの定性的・定量的データを組み合わせることで、展示会マーケティングの総合的な効果を把握することができます。
まとめ
展示会マーケティングは、企業ブランディングの強化、質の高いリード獲得、製品・サービスの認知度拡大、既存顧客との関係深化など、多様な目的を達成するための強力なツールです。効果的な展示会マーケティングを実現するためには、明確な目標設定、戦略的な準備、魅力的なブース設計、インパクトのあるデモンストレーション、そして綿密なフォローアップが不可欠です。
特に重要なのは、展示会で獲得した名刺情報やリードを適切に管理し、効果的にフォローアップすることです。その実現のために、多くの企業が名刺管理ツールを導入しています。
また、コンタクトフォロー機能を使えば、活動記録を紹介することができるため、展示会後のインサイドセールスの動きも可視化し、展示会後の動きも漏れなく共有することができます。
展示会での名刺管理や、開催後にユーザーへ効率的なフォローアップをしたいと考えている方は、ぜひSansanをご活用ください。
Sansanは、名刺や企業情報、営業履歴を一元管理して全社で共有できるようにすることで、売上拡大とコスト削減を同時に実現する営業DXサービスです。
Sansanの名刺管理ソリューションを活用することで、名刺情報の迅速な取り込み、一元管理、名寄せなどを効率的に行うことができ、展示化マーケティングの成功に大きく寄与します。
これにより、展示会後の営業活動やマーケティング施策をより効果的に展開することが可能となり、最終的な成約率の向上につながるでしょう。
展示会マーケティングは単なるイベント参加ではなく、総合的なマーケティング戦略の一環として捉えることが重要です。
適切な準備と実行、そして効果測定を通じて、展示会の価値を最大限に引き出し、ビジネスの成長につなげていきましょう。
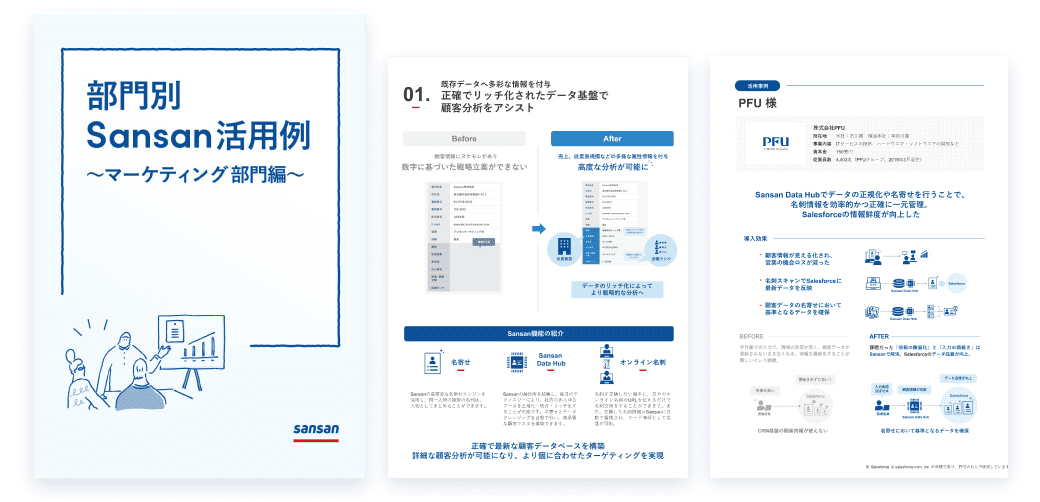
部門別Sansan活用例〜マーケティング部門編〜
Sansanを全社でご利用いただくと、マーケティング部門でどんなメリットを感じるか、具体的にイメージしやすくなる資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部