- コンプライアンス
反社チェックとは?重要性や実施方法、反社に該当した場合の対応を解説
公開日:
更新日:
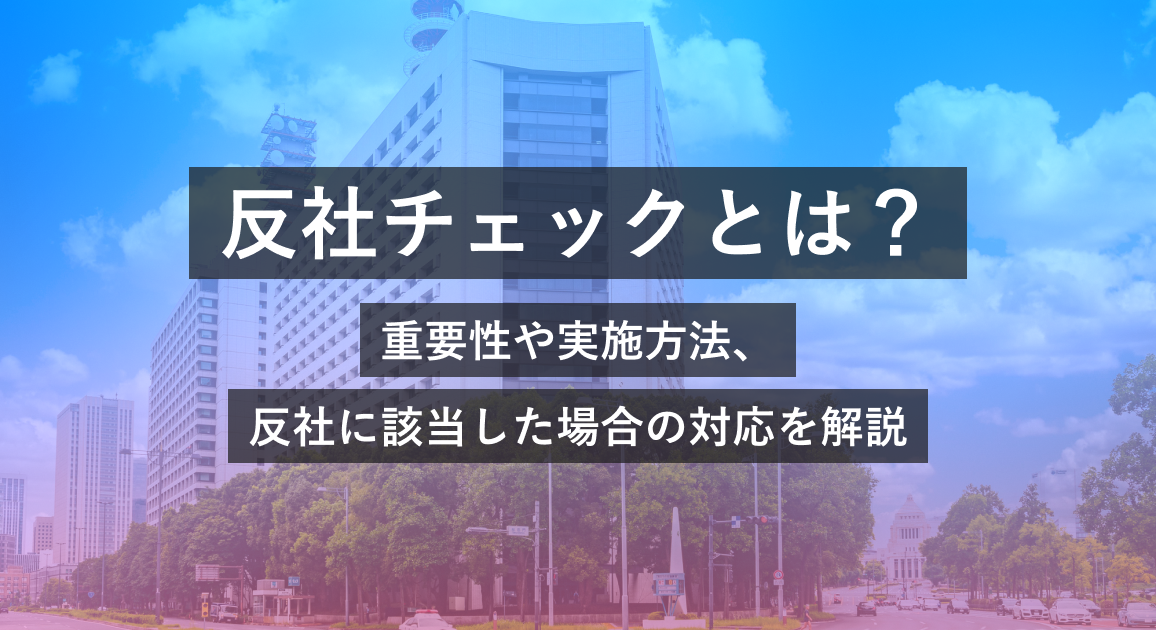
企業活動において、反社会的勢力との関係は信用失墜や法的リスクを招く重大な問題です。そのため、契約締結前や定期的に「反社チェック(反社会的勢力との関係有無の確認)」を行うことは、すべての企業に求められる重要なコンプライアンス対応です。
本記事では、反社チェックの意味や重要性、対象範囲と実施タイミング、実務で使える具体的な調査方法、Sansanが提供するリスクチェック機能による自動化・効率化のポイントまで、実践的に解説します。信頼ある企業体制の構築に、ぜひお役立てください。。
取引リスクを早期に発見できる
反社チェックとは

まずは、反社チェックの定義や条例によって求められている対応、反社チェックの対象者といった基礎知識を紹介します。
企業はなぜ反社チェックを行うべきか?
企業が反社チェックを実施する最大の理由は、「知らぬ間に反社会的勢力と関わってしまうリスク」を排除することにあります。
近年では、反社会的勢力がフロント企業やブローカー、名義貸しなどを利用し、正規の企業活動を装って接近するケースが増加しています。
そのため、契約や採用など重要な判断を下す前に相手の素性を確認し、健全なビジネス環境を維持するための予防策として反社チェックは不可欠なプロセスとなっています。
暴力団排除条例により求められている対応
各都道府県で制定されている暴力団排除条例では、反社会的勢力との取引を防止するために、次のような対応を求めています。
- 契約締結時に相手方が暴力団関係者でないことを確認する
- 契約書に暴力団排除に関する条項を設ける
- 暴力団関係者への利益供与をしない
- 暴力団関係者と疑われる相手は、警察や公的機関に相談する
東京都暴力団排除条例では、「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」「暴力団を利用しない」を基本理念としたうえで、暴力団と交際しないことを呼びかけています。
反社チェックの対象者はどこまで?
企業が反社チェックを行う場合、どこまでが対象者になるのでしょうか。範囲を詳しく見ていきましょう。
企業に関連する関係者や取引先
企業は取引先だけでなく、その役員・株主・親会社・関連会社といった関係者の背後情報もチェックする必要があります。これは、反社が「フロント企業」や「第三者名義」を用いて間接的に関与してくるケースが増えているためです。
従業員・役員
新たに入社してくる従業員と、既存の従業員に対しても反社チェックを行う必要があります。チェックは、アルバイトなど正社員以外の従業員も対象になるため、雇用形態に関係なく実施しましょう。
また、最近では入社前の社員がSNSで暴力団とつながりを持っているケースも考えられます。学生が、強盗傷害事件や詐欺事件に関わっていた事件もニュースで度々報じられているため、注意しなければなりません。役員も反社チェックの対象です。
自社株主
主要な株主が反社だった場合、企業の経営状態に支障をきたします。既存の株主に対して反社チェックを行うだけでなく、株主が増えた場合や、株主に変更があった場合にも確認することが重要です。
株主が法人の場合は、従業員のみならず、顧問弁護士や税理士といった関係者についても調査します。
反社チェックの目的・必要性

ここからは、反社チェックの目的や必要性について解説します。
社会的信用の失墜を防止するため
反社チェックを行う最大の目的のひとつは、企業としての社会的信用を守ることです。
現在、政府や自治体では反社会的勢力の排除を目的とした条例が広く制定されており、企業にもその遵守が求められています。
仮に反社との関係が発覚した場合、行政処分の対象となるだけでなく、顧客や取引先からの信頼を一気に失う可能性があります。どれほど優れた商品やサービスを提供していても、企業としての信用がなければ、顧客は離れていくでしょう。
社会的信用の喪失は、売り上げの減少や契約の打ち切り、損害賠償請求といった経営リスクにも直結します。最悪の場合、経営破綻や倒産につながることも十分に考えられます。
特に上場企業は、上場廃止という重大なリスクも抱えています。反社が短期的に多額の資金を得られる上場企業に接触し、資金洗浄や不正取引に利用する恐れがあるため、上場維持には一層の注意が必要です。
企業・従業員を守るため
反社と関わらないことは、企業や従業員を守るうえでも重要な意味を持ちます。
反社と関わりを持っていると会社が信用を失い、顧客が離れていきます。その結果、会社が倒産の危機に陥り、従業員の生活を守れなくなってしまいます。
また、契約締結後に取引先が反社であることが判明した場合に、契約の解除をめぐって脅迫や不当な要求をされるリスクもあります。脅迫が従業員にまで及ぶことがあるため、そういったトラブル自体に巻き込まれることを防止しなければなりません。
反社会的勢力への資金流出を防止するため
取引先などが反社会的勢力であることを把握していなかったことが原因で、知らないうちに犯罪を助長してしまうケースも考えられます。このような「巻き込まれ」の防止も、反社チェックを行う理由の一つです。
自社の資金や売り上げ、顧客情報といった資産が反社会勢力に流れ、犯罪に使われたことが公になると、会社は社会的信用を失います。
既存の取引先が気付かない間に反社に買収され、監査役などに反社が送り込まれているケースも増えているので注意しましょう。特に継続取引の場合は、既存の契約がそのまま更新されていることが多いため、問題があっても気付きにくいといえます。
反社チェックはいつ行うべき?
反社チェックのタイミングは契約直前になってしまうことが多いですが、本来はファーストコンタクトで行うことが望ましいといえます。
反社会勢力への対策は「いかに対応するか」ではなく、「いかに関係を持たないようにするか」が基本です。実際に、取引がなかったにも関わらず、反社とつながりがあったという理由で倒産に追い込まれた企業もあり、契約直前の対策が意味を持たないことがわかります。
新規の取引先の場合はなるべく早期に反社チェックを行い、既存の取引先に対しても、契約を更新するタイミングでチェックを実施すると良いでしょう。
反社チェックのやり方|実務で使える具体的なステップ

反社チェックは、一度行えば終わりというものではなく、取引開始前と継続中の双方で継続的に行う必要があります。
ここでは、実務で使える具体的な4つのステップをご紹介します。
ステップ1:インターネットと公的記録から調査する
最初に、公的な情報やインターネット検索を活用することで、効率的かつ低コストな調査が可能になります。なぜなら反社会的勢力と関わりのある企業や個人は、公的記録や報道に何らかの痕跡を残していることが多いためです。
また、登記情報は法的根拠に基づいた正確な情報であり、信頼性の高い調査の出発点となります。
主な調査項目は以下の通りです。
- 商業登記簿で「会社の設立目的」「役員名」「履歴」を確認(法務局または登記情報提供サービス)
- 会社名・役員名・電話番号をGoogleやSNSで検索し、「事件」「反社会的勢力」などの関連語と組み合わせて不審な情報がないかを確認
- 電子版新聞(日経・朝日)で対象者の名前を検索し、過去の報道を確認
このように、公的情報とネット検索を組み合わせれば、反社チェックの基礎となる情報を効率よく収集できます。
ステップ2:データベースや反社リストを活用してスクリーニングする
専門的なデータベースや反社リストを使えば、個人では手に入らない情報をもとに、精度の高いスクリーニングが行えます。というのも、これらの情報には、通常の調査では見つかりにくい組織的な関係や過去の処分歴などが含まれているからです。
また、商用ツールを導入することで、作業の効率化とミス防止、継続的なチェックも実現できます。
スクリーニングの具体的な方法は以下の通りです。
- 取引先の会社名・役員名を金融庁や業界団体の反社リスト、暴力団排除条例に基づく情報と照合する
- 無料のリストでは情報に限りがあるため、精度を高めるには商用ツールを活用して網羅的にチェックする
したがって、データベースとリストを組み合わせたスクリーニングにより、より確実な反社チェック体制を構築できます。
ステップ3:疑わしい場合は調査会社に依頼する
グレーゾーンの判断に迷った際は、専門の調査会社に委託することで、客観的かつ詳細な情報収集が可能になります。これは、調査会社は独自のネットワークと調査ノウハウを持ち、一般企業では得にくい情報源にもアクセスできるためです。
さらに、専門的な視点から総合的な判断が加わることで、リスクの見落としを防ぐことができます。
調査依頼時のポイントは以下の通りです。
- 判断が難しい場合は、帝国データバンクや東京商工リサーチなど、企業調査の専門会社に相談する
- 依頼時には「反社会的勢力の懸念があるが情報が不十分」と伝え、調査範囲・報告書の形式・納期を確認する
- 取引先との関係を損なわないよう、連絡内容や対応方法にも十分な配慮をする
専門機関を活用することで、自社の限界を補いながら、より的確なリスク判断が可能になります。
ステップ4:行政・警察に相談する(最終手段)
深刻な反社会的勢力の疑いが浮上した場合、公的機関への相談が最も確実で安全な対応策となります。行政機関や警察は、反社会的勢力に関する最新かつ正確な情報を保有しており、法的な観点から適切な助言を受けることができるためです。
また、万が一のトラブル発生時には、事前相談の記録が企業防衛の有力な証拠にもなります。
相談窓口としては、警視庁や暴力団追放センター、各県警の組織犯罪対策課などが挙げられます。その際には、以下のような資料を準備しておくとスムーズです。
- 契約書
- 特約条項
- 反社会的勢力の疑いに関する証拠資料
このような段階に至った場合は、すでに取引関係の見直しも検討すべき状況といえるでしょう。公的機関の助言をもとに、法的リスクを最小限に抑える対応策を整えることが重要です。
反社チェックの精度を高めるためのポイント
企業が反社チェックを行ううえで重要なのは、「確認体制の強化」と「情報の網羅性・信頼性の確保」です。ここでは、チェック精度を高めるための具体的な取り組みについて3つの視点から解説します。
接点情報をデータ化してチェック体制を強化する
対象者との過去の商談などの接点情報を管理することで、反社チェックの精度と効率が大きく向上します。手作業での情報管理はミスが起きやすく、チェックの精度や一貫性が保たれにくいからです。
多くの企業では名刺やメール署名から得た情報を手入力しているため、リスク情報の見落としが起こる可能性もあります。
例えば、一般的な反社チェックツールでは、以下の対応が可能です。
- 名刺や署名の情報を自動でデータベースに登録し、入力ミスを防止
- 情報の入力作業が不要になり、抜け漏れのリスクを低減
- 登録された情報をもとに、リアルタイムで反社チェックを実施し、継続的な監視も可能に
このようなシステムを導入すれば、反社チェックをより正確に、かつ効率よく行える体制が整います。
複数の信頼性の高いデータベースと連携する
複数の外部データベースと連携することで、単一の情報源では把握しきれないリスクまで広くカバーすることが可能になります。反社チェックの精度は、参照する情報の「質」と「網羅性」によって左右されるため、信頼性の高いデータベースとの連携が成否を分ける要素となります。
また、各データベースが保有する独自情報を組み合わせることで、リスクの見落としを最小限に抑えることができます。
そのため、これらの信頼性の高いデータベースと連携しているチェックツールを活用することが現実的かつ効果的な手段です。
例えば、チェックツールの代表的なものは、以下の通りとなります。
- World-Check(LSEG):制裁リスト、反社会的勢力情報、政治的要人(PEPs)情報などを広範にカバー
- リスクチェック powered by LSEG/KYCC(Sansan):反社会的勢力との関わりやマネーロンダリング、⼈権侵害、組織犯罪などへの関与といった、さまざまなリスクを自動で検知
こうした複数のデータベースに対応したツールを導入することで、反社チェックの信頼性と網羅性を大きく高めることができます。
反社以外のリスクも一括で検知できる仕組みを活用する
包括的なリスク管理体制を構築するには、反社チェックとあわせて他のビジネスリスクも同時に検知できるシステムの活用が不可欠です。というのも、現代のビジネス環境では反社チェックだけでは不十分であり、企業には多様なコンプライアンスリスクへの対応が求められているためです。
また、個別にチェックを行うよりも、情報を一元的に管理することで効率性が高まり、コストパフォーマンスの向上にもつながります。
対応すべき主要なビジネスリスクには以下が含まれます。
- マネーロンダリング(資金洗浄)
- テロ資金供与
- 人権侵害
- 国際的な制裁対象との関係
上記の対策として、反社チェックを含めた包括的なリスク検知システムを導入することで、コンプライアンス体制の強化と業務の効率化を同時に実現することが可能です。
相手方が反社に該当した場合の対処法
反社チェックを実施した結果、相手方が反社に該当した場合は、どのように対処すべきなのでしょうか。いくつか選択肢があるので、順番に解説します。
弁護士に相談する
まずは、顧問弁護士に相談して指示を仰ぐ方法です。弁護士に相談するメリットとしては、法的な対処を含めて相談できる点があげられます。弁護士を通じて、警察や暴力追放運動推進センターと連携をとれる可能性もあります。
警察や暴追センターに相談する
相手方が反社であることが明らかである場合や、問題が起こる予兆が見られる場合は、警察や暴力追放運動推進センター(暴追センター)に相談しましょう。
相談する際は、従業員に対して身を守るなどの注意喚起を行ったうえで、必要なアドバイスもあわせて受けることが重要です。
ただし、警察や暴追センターへの相談は、聞き取りに時間と労力がかかる点は認識しておく必要があります。
取引を中止する
今後トラブルに発展しないように、取引を中止するのも一つの方法です。
自社の混乱を防ぐため、原材料を主力で発注しているような場合は、段階的に仕入れ量を減らしていくなどの対応を行います。
また、自社に危険が及ぶことも回避しなければなりません。反社チェックを行わないまま契約を結び、あとから取引先が反社であることが発覚した場合は、取締役が「善管注意義務違反」に問われる可能性があります。
従業員が動揺したり、業務の進め方にトラブルが起きたりしないよう配慮しながら、中止に向けて動きましょう。
反社チェック時に注意したいポイント
反社チェックを行う際は、次のようなポイントに注意しましょう。
一度だけでなく定期的に実施する
反社チェックは、実施する期間を考慮する必要があります。最初の付き合い開始時に実施するのはもちろんのこと、定期的に実施して会社の健全性を担保しましょう。
以前は問題なかった取引先が、いつの間にか反社会勢力と関わりを持っていたということも考えられます。また、反社チェックの頻度を高めること自体が、反社との関わりを抑制することにもつながります。
ツールをうまく活用する
自社で反社チェックを行う場合は、会社情報の確認やインターネット上の情報を確認するなどの方法があります。しかし、自社で基準を設定することは難易度が高く、偏った結果が出たり、実態を調べきれなかったりする可能性があります。
反社チェックのためのツールをうまく活用し、効率的にチェックを実施しましょう。ただし、ツールに任せきりにしないことが重要です。得られた結果を基に、自分たちでさらに根拠を確認し、必要に応じて専門家への調査を依頼するなどして、最終決定を下します。
また、ツールの導入にかかる費用や導入の手間も考慮したうえで決定する必要があります。
主観的な判断をしない
「あの人は大丈夫」「あの会社が反社なわけがない」など、自分の直感や経験などに頼って人を判断し、反社チェックを怠ることは危険なので避けましょう。
反社チェックは、企業人として実施が必要です。会社の規模が小さいから実施しなくても良いということもありません。会社の規模を問わず、健全な経営を行うために反社チェックは必ず実施することを推奨します。
まとめ
反社チェックは、取引先や従業員が反社会的勢力と関係していないかを確認する重要なコンプライアンス対応業務です。企業の信用を守り法的リスクを回避するうえで、すべての企業に求められる基本的な取り組みといえます。
効果的な反社チェックには、以下の4ステップを段階的に進めることが重要です。
- 公的情報とネット検索による基礎調査
- 専門データベースを活用したスクリーニング
- 疑義がある場合の調査会社への依頼
- 最終的な行政・警察への相談
さらに、精度向上には自動データ化や外部データベースとの連携、他のビジネスリスクも検知できる包括的なシステムの導入が有効です。
例えば、Sansanのリスクチェック機能では、名刺やメール署名から自動で情報を取り込み、反社会的勢力に加え、マネーロンダリングや人権侵害なども検知可能です。
接点のない企業についても事前にリスク検索が行えるため、営業活動の効率化にもつながります。継続的かつ確実なチェック体制を整え、信頼される企業経営を実現していきましょう。

リスクチェック powered by LSEG/KYCC
リスクチェックのサービスについて、ご利用の流れや導入後のメリットについて説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部

