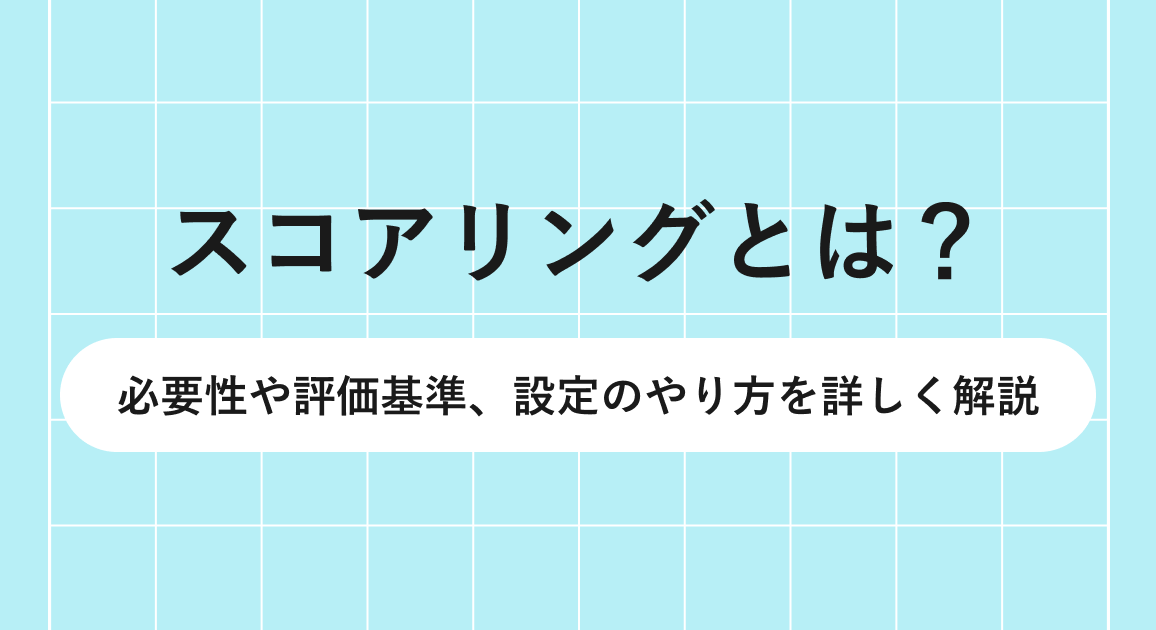- 経営・ビジネス全般
リスクマネジメントとは?4つの基本プロセスと成功ポイントをわかりやすく紹介
公開日:
更新日:
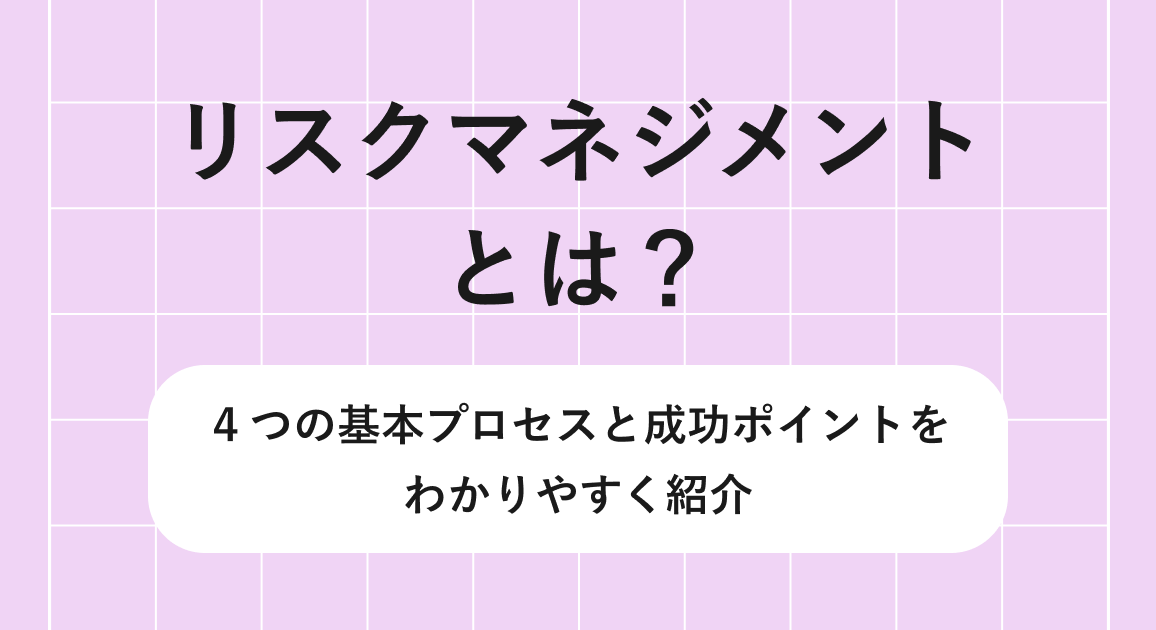
リスクマネジメントとは、将来発生する可能性があるリスクを事前に想定し、被害を最小限に抑える経営手法です。的確に実践することで、企業は脅威と機会を的確に見極め、ビジネスの成長につなげられるでしょう。本記事では、リスクマネジメントについて、基本プロセスと成功のポイントを解説します。
営業力強化で生産性向上を後押しする
リスクマネジメントとは

リスクマネジメントとは、将来発生する可能性があるリスクを事前に想定し、被害を最小限に抑えるための経営手法です。
企業におけるリスクを視覚化して適切なプロセスで評価・対応することで、事業継続や信頼性維持に役立ちます。
想定されるリスクは、自然災害や情報漏えい、法令違反といった明確に認識できるものだけではありません。判断ミスや意思決定の遅れなど、目に見えにくい要素も含まれます。
現在では、企業価値向上やガバナンス強化といった観点からも、リスクマネジメントの重要性が一層高まっています。
的確なリスク管理体制は、企業の持続的な成長と信頼構築に欠かせない要素と言えるでしょう。
企業におけるリスクの定義とは

では、企業におけるリスクの定義とはどのようなものでしょうか。
ISO 31000では、リスクを「目的に対する不確かさの影響」と定義しており、企業にとってリスクは必ずしもマイナス要因だけを指すものではないとしています。
そのため、企業ではリスクを一律に排除するのではなく、許容できる範囲を明確にしながら適切に管理・活用する姿勢が重要です。
ここでは、企業活動に関わる代表的なリスクを「純粋リスク」と「投機的リスク」に分類し、それぞれの特徴について解説します。
純粋リスク
純粋リスクとは、発生した際に企業へマイナスの影響を与えるリスクです。
具体的には、以下のようなものが純粋リスクに該当します。
- 自然災害:地震、台風、水害などによる工場やオフィスの損害
- 情報漏えい:顧客情報や機密データの外部流出
- コンプライアンス違反:法令違反による罰則や企業イメージの低下
- 労働災害:従業員の事故やけがによる業務停止
- 設備故障:製造ラインやITシステムの重大なトラブル
これらのリスクは基本的に発生確率を下げたり、影響を軽減したりする方向で対処する必要があります。
また、発生前にどれだけ備えていたかによって損害規模は大きく変わるため、リスクの継続的な管理と定期的な見直しが不可欠です。
投機的リスク
投機的リスクは、企業にとってプラスにもマイナスにも働く可能性を持った不確実性の高いリスクです。
具体例としては、以下のような事象が投機的リスクに含まれます。
- 新規事業への参入:市場開拓による成長の機会と失敗のリスク
- 海外展開:国際市場進出による売上拡大と、文化・法規制の違いによるリスク
- M&A(企業の合併・買収):事業規模の拡大と統合の失敗に伴うリスク
- 為替変動:為替差益・差損が経営に与える影響
- 株価変動:資産評価額や資金調達条件へ及ぼす影響
投機的リスクは、完全に回避するのではなく、期待されるリターンとのバランスを慎重に見極めたうえで、戦略的にリスクを取っていく対策がポイントです。
特に経営層には、挑戦すべきリスクと回避すべきリスクを適切に見極める冷静な判断力が求められます。
リスクマネジメントの目的
リスクマネジメントの目的は、リスクをゼロにするのではなく、適切にコントロールして企業の持続的な成長を実現することです。
リスクマネジメントを適切に実施できれば、企業は不測の事態による損害を防ぐだけでなく、以下のような効果も期待できます。
- 意思決定を迅速化できる
- 経営資源を最適に配分できる
これにより、企業の競争力強化にもつながるでしょう。
また、リスクマネジメントに取り組むことは、社内外のステークホルダーに対して企業の透明性と信頼性を示すうえでも重要です。
結果として、ガバナンスの強化や企業レピュテーションの維持にも貢献します。
リスクを単なる脅威と捉えるのではなく、チャンスとして生かせる柔軟な企業体質を築くことが、リスクマネジメントの最大の目的と言えるでしょう。
リスクマネジメントの基本プロセス4つ
リスクマネジメントを実践するには、リスク管理の仕組み化が重要です。
ここでは、リスクマネジメントの基本プロセスについて見ていきましょう。
1.特定
リスクマネジメントの最初のステップは、自社にどんなリスクがあるのかを洗い出す作業です。
リスクを正確に特定できると、後の分析や対応策の質も変わってきます。
例えば、以下のようなリスクが想定できるでしょう。
- 自然災害
- 法規制の変更
- 情報漏えい
- 人的ミス
リスクを特定する際は、各部門や現場の担当者からヒアリングを行い、実態に即したリスクを漏れなくリストアップすることが重要です。
また、過去のトラブル事例や社内報告、事故情報なども参考にして、想定されるリスクを文書化しておくと役立ちます。
2.分析
リスクを特定した後は、それぞれのリスクが自社に与える影響度と発生頻度を分析します。
具体的な分析ポイントは以下のとおりです。
- 影響度(経済的損失、企業イメージへの影響、業務停止リスクなど)
- 発生頻度(過去の発生件数や発生確率の予測)
分析の際は、リスクマトリクスやスコアリングといった手法を活用すると、優先順位を視覚的に整理できます。
部門ごとの主観に偏らないよう、客観的な指標を用いることで、実用性の高い分析結果が得られるでしょう。
3.評価
分析したリスクに対応する優先順位を決める評価のステップです。
リスクを「許容可能なもの」と「対応が必要なもの」に分類して、対応方針を明確にします。
評価にあたっては、以下の観点で判断を行います。
- 影響度(損失額、業務への影響の大きさなど)
- 発生頻度(発生する可能性の高さ)
分析のときと同じく、リスクマトリクスやスコアリングを用いれば視覚的に整理できるため、関係者間で共通理解が得やすくなります。
各部門や関係者と共有しながら評価を進めれば、対応策立案もスムーズに進行できます。
4.対応
リスク評価の結果、対応が必要と判断されたリスクは、具体的な対策に移ります。
対応方法は、主に以下の4つに分類されます。
- 回避:リスクを発生させる行動を取らない
- 低減:リスクの発生確率や影響度を下げる
- 移転:保険契約やアウトソーシングによりリスクを第三者に移す
- 受容:リスクを許容範囲内として受け入れる
リスクの性質や事業戦略に応じて、これらの中から最適な対応方法を選択します。
例えば、情報漏えいリスクに対しては、セキュリティー体制の強化や社員向けの教育研修を実施するなどが効果的です。自然災害リスクに対しては、BCP(事業継続計画)を策定し、非常時に備える対策が有効です。
対応策は文書化したうえで関係部署と共有し、緊急時にも迅速かつ的確な対応ができる体制を整備します。
リスクマネジメントを成功させる5つのポイント

ここでは、リスクマネジメントを成功させるための5つのポイントを紹介します。
1.組織全体として取り組む
リスクマネジメントは一部の部署や担当者のみが行うものではなく、組織全体で取り組むべき経営活動です。
経営層が主導し、各部門と連携しながらリスクへの意識と対策を全体に浸透させていく体制が求められます。部門間でリスクに対する温度差があると、対応の質やスピードにばらつきが出てしまうため、意識の統一が欠かせません。
日常業務の中でリスクを意識できる文化を育み、全社員が主体的にリスク対応に取り組める状態を目指しすことが重要です。
2.対策内容をマニュアル化する(標準化)
リスクが発生した際に迅速かつ的確な対応を行うために、対応手順や判断基準をマニュアル化しておくことが重要です。
具体的には、以下のような対応フローを準備しておくとよいでしょう。
- 情報漏えいが発生した場合の初動対応
- 自然災害発生時の安全確保・業務継続
- トラブル対応時の連絡・報告手順
場面ごとの対応フローを用意して、誰が見てもすぐに対応できるようにしておくのがポイントです。
また、マニュアルを作成した後も定期的な見直しや現場からのフィードバックを取り入れて改善していく対応も欠かせません。
対応方法を標準化しておけば、リスクマネジメント全体の品質向上につながります。
3.定期的な見直しと検証を行う
ビジネス環境や業務内容の変化に伴い、リスクの種類や重要度も変化します。
そのため、定期的なリスクの再評価と検証を行うことが大切です。
例えば、年に1回程度の頻度でリスクアセスメントを実施して、潜在的なリスクや新たに発生しうるリスクを把握します。これによりリスクマネジメント体制の最適化が図れます。
また、リスク発生時の対応履歴をもとに、実際の対応が適切だったかどうかを振り返り、改善点を洗い出す対策も有効です。
検証結果を反映しながらプロセスやマニュアルをアップデートし、より実効性の高いリスクマネジメント体制を構築していきましょう。
4.リスクマネジメント委員会を設置する
リスクマネジメントを継続的に運用・改善していくためには、社内に中核的な役割を果たす委員会を設置することが効果的です。
委員会には、経営層や法務、情報システムなど各部門の代表者などが参加して、部門横断的な視点でリスクを管理できる体制を構築します。
設置された委員会は定期的にリスクの状況をレビューし、優先度の高いリスクに対する施策を検討・実行する役割を担います。これにより、組織全体のリスクマネジメントが可能です。
また、リスク対応に関する責任の所在を明確にしておくと、スピード感のある対応や正確性の向上にもつながるでしょう。
5.専門家のサポートを受ける
必要に応じて、外部の専門家の協力を得ることも有効です。
企業が直面するリスクの中には、法務・情報セキュリティ・会計など、専門的な知識が求められる領域も含まれます。
例えば、個人情報保護やコンプライアンス強化については、顧問弁護士のアドバイスを受けることで、法的リスクを未然に防げるでしょう。CISO(最高情報セキュリティ責任者)やセキュリティベンダーと連携して、システムの脆弱性を診断・補強する取り組みなども効果的です。
自社だけで対応を完結せずに、外部の専門知見を柔軟に取り入れていけば、より盤石なリスクマネジメント体制の構築につながります。
リスクマネジメントの類語との違い
リスクに関する用語には、リスクマネジメント以外にも類似した表現がいくつかあります。
ここでは、リスクアセスメント、リスクヘッジ、クライシスマネジメントの違いについて解説します。
リスクアセスメント
リスクアセスメントとは、リスクマネジメントの中でも「特定」「分析」「評価」といったステップを指します。
主に「どのようなリスクがあるか」「それがどれほど重大か」を見極めるためのリスク評価プロセスです。
法律やガイドラインなどで義務付けられているケースもあり、特に製造業や建設業などでは必須の取り組みとされています。
リスクマネジメントが「リスクにどう対応するか」まで含んでいるのに対し、リスクアセスメントはその前段階であるリスクの把握と分析に限定されている点が大きな違いです。
リスクヘッジ
リスクヘッジとは、将来発生する可能性のある損失を避けるためにあらかじめ手を打っておく対策のことを指します。
特に金融分野で多く用いられ、為替変動や原材料価格の高騰といったリスクを回避するために、保険への加入や契約条件で調整といった手段が取られます。
「リスクに備える」という点ではリスクマネジメントと共通していますが、リスクヘッジはより具体的な回避策にフォーカスしている点が特徴です。
リスクマネジメントがリスクの洗い出しから評価・対応・改善まで広くカバーするのに対し、リスクヘッジはその中の事前の対策手段の一部である点が異なります。
クライシスマネジメント
クライシスマネジメントとは、実際に重大なトラブルや緊急事態が発生した後に、被害を最小限に抑えるための対応活動を指す言葉です。
自然災害や不祥事、サイバー攻撃など、企業に甚大な影響を及ぼす「危機」への対処を目的としています。
リスクマネジメントが事前にリスクを想定して備える広い概念であるのに対し、クライシスマネジメントは「発生後の対応」に特化しているのが特徴です。
日本語では「危機管理」と訳され、BCP(事業継続計画)や広報対応、被害状況の把握と共有、組織体制の再構築といった緊急時の各種対応がクライシスマネジメントに含まれます。
まとめ
リスクマネジメントは企業の持続的成長や信頼確保に不可欠な経営活動です。
リスクへの対応が後手に回れば、損失の発生だけでなく、企業価値にも深刻な影響を及ぼしかねません。
ビジネスデータベース「Sansan」を活用すると、名刺や商談履歴といった顧客情報をデータ化し、社内での共有が可能です。これにより部門間の情報連携を強化し、リスクの早期発見や初動対応の迅速化を支援します。
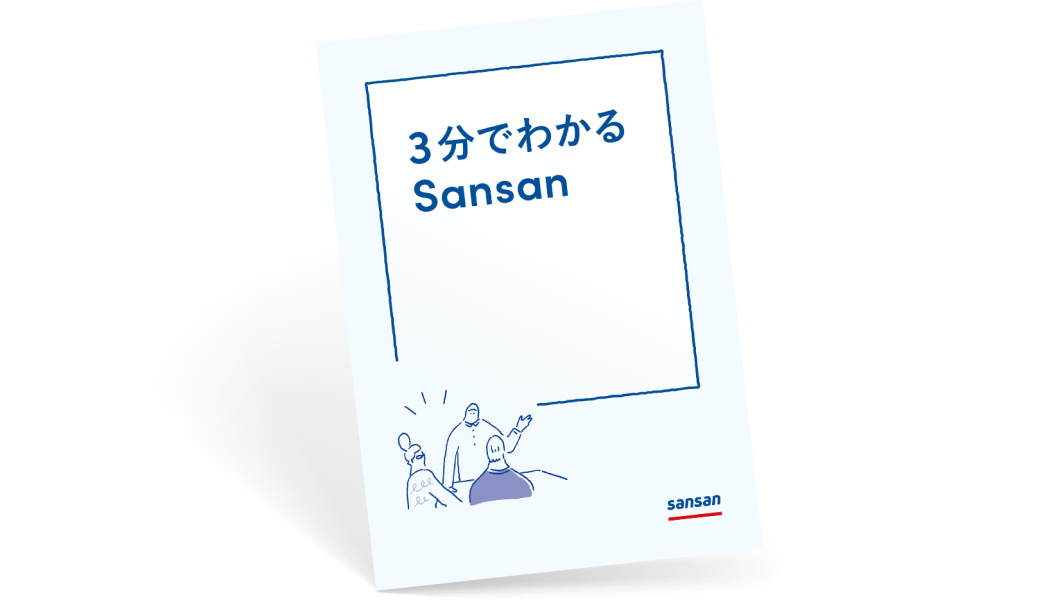
3分でわかるSansan
ビジネスデータベース「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部