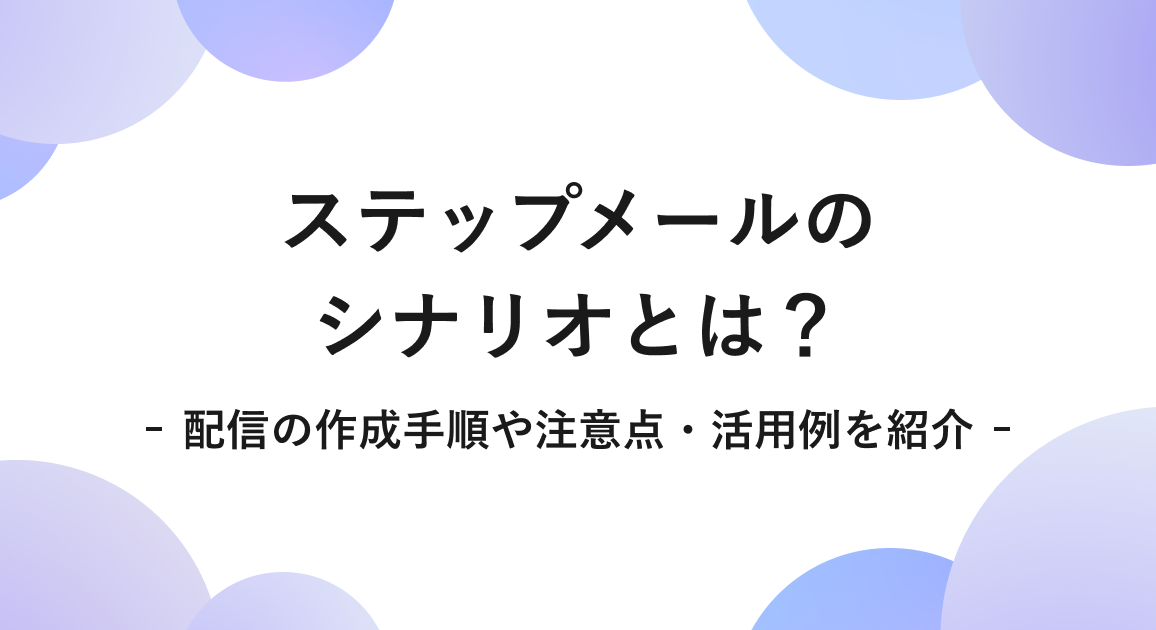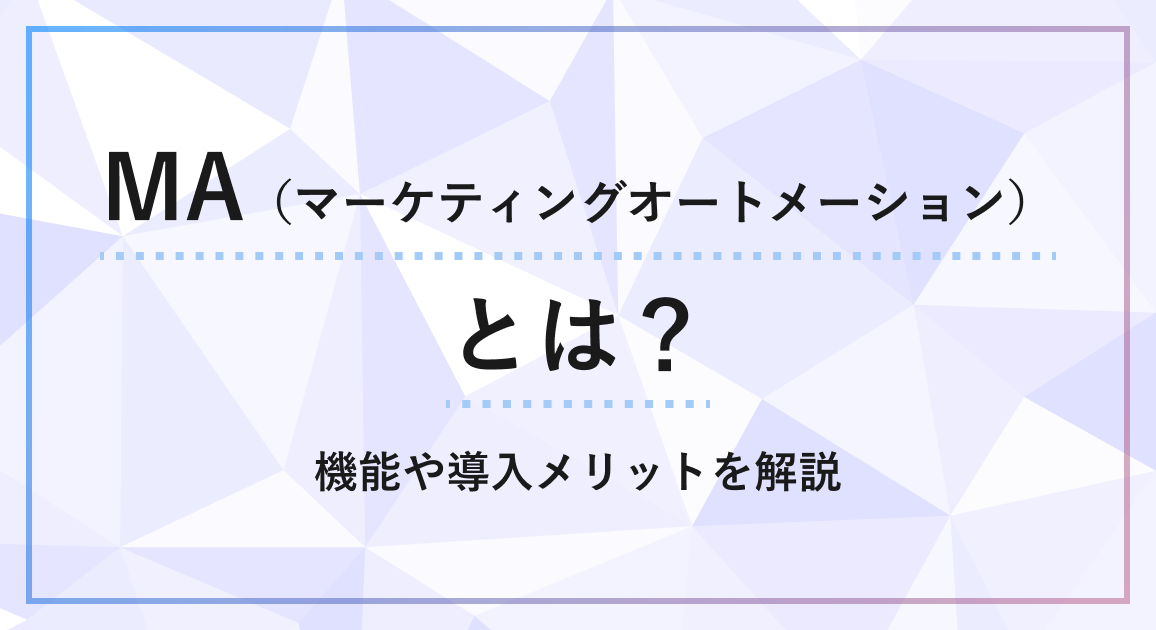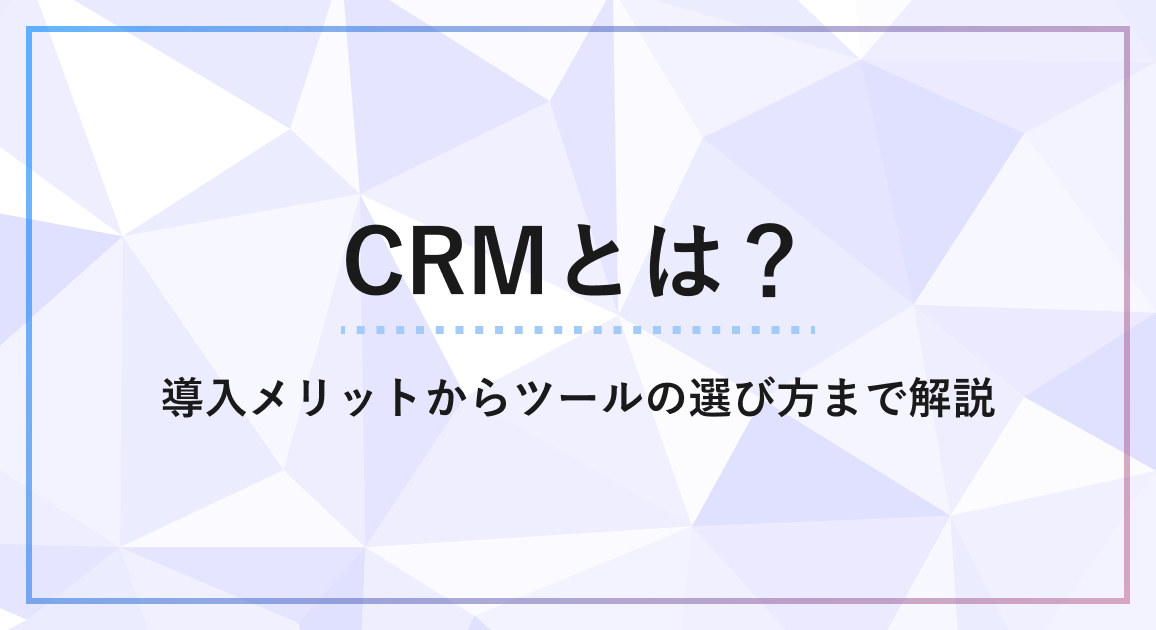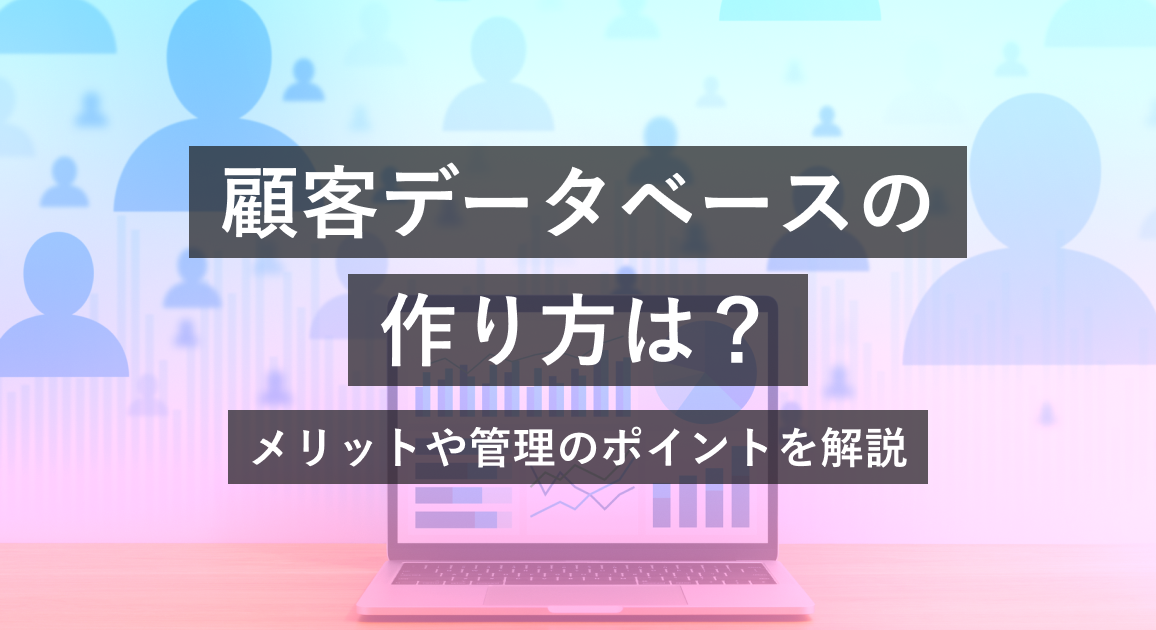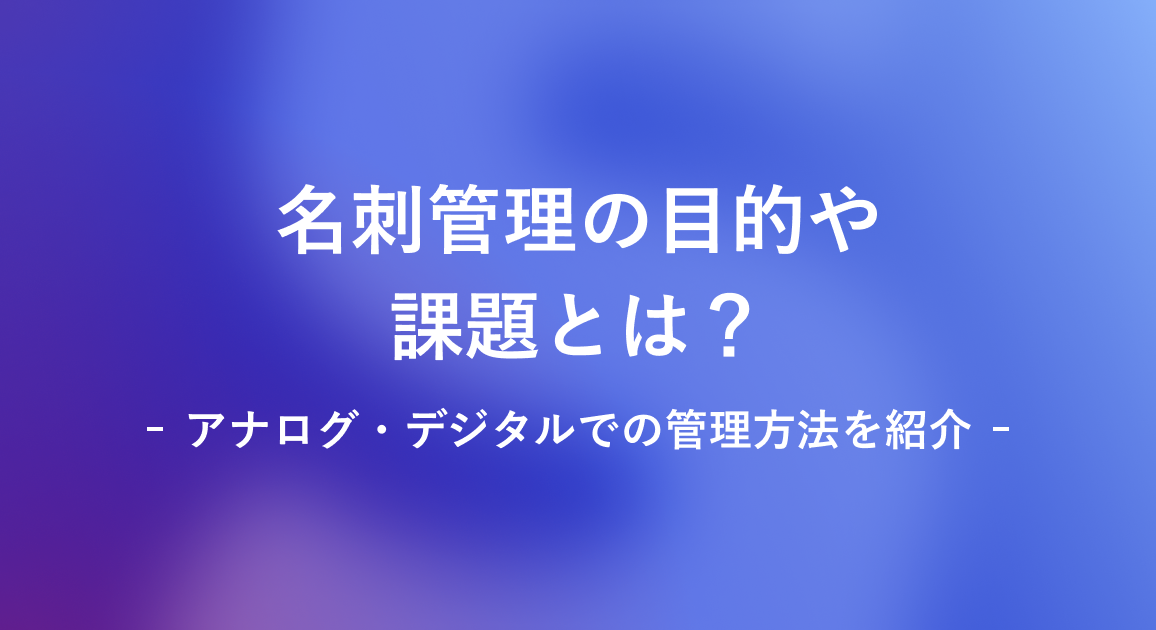- マーケティングノウハウ
ステップメールの役割とは?メリットやデメリット、作成・配信方法を解説
公開日:
更新日:
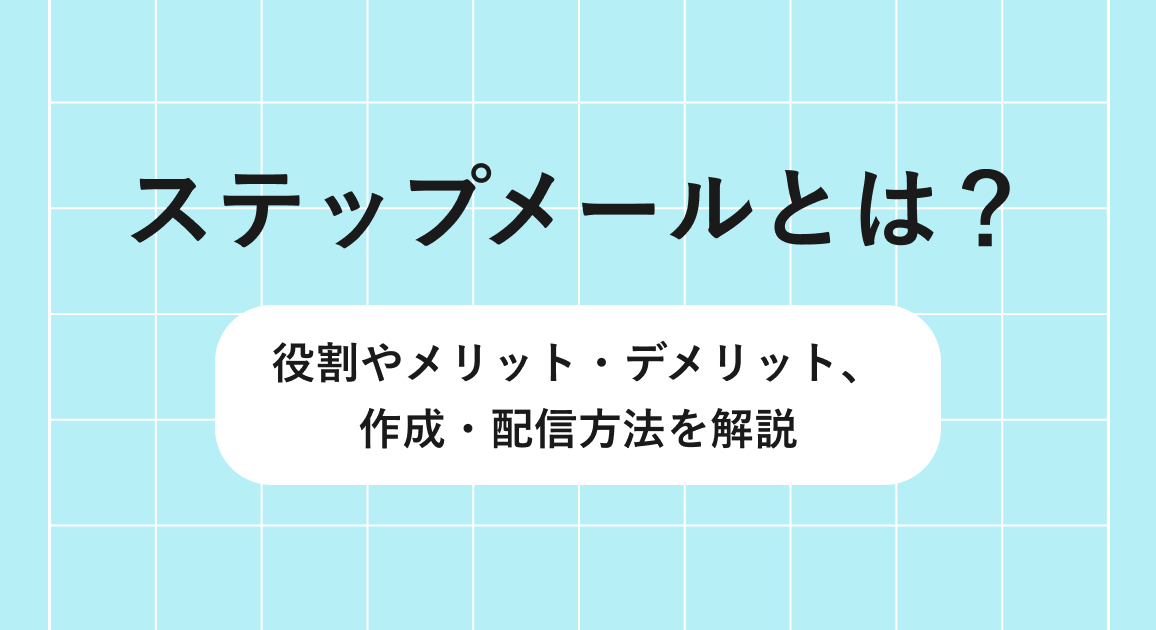
ステップメールとは、あらかじめ設定した条件に基づき、メールを自動で配信するマーケティング手法です。会員登録やWebページの閲覧といったアクションを契機にステップメールを配信することで、見込み顧客の購買意欲を高めたり、密度の高いコミュニケーションを実現したりなど、さまざまな効果が期待できます。
ステップメールはビジネスに役立つメールマーケティング手法の一つです。うまく取り入れるためには、ステップメールの概要やメルマガとの違い、作成方法、配信のポイントなどを押さえておく必要があります。
この記事では、ステップメールの概要やメリット・デメリットを解説し、作成・配信する際のポイントもあわせてご紹介します。
リード育成の課題を解決する
ステップメールとは?役割やメルマガとの違い

ステップメールとは、ユーザーが資料ダウンロード・申し込み・初回購入など特定のアクションを起こした場合に、事前に設定したスケジュールやシナリオに基づき、自動的に配信される複数のメールです。
ここではステップメールの仕組みと役割、メルマガとの違いについて解説します。
ステップメールの仕組み
ステップメールは、予定したタイミングやトリガーに基づき、あらかじめ作成しておいたメールを順番に自動配信するもので、配信回数・スケジュール・配信内容などは自由に組み合わせることが可能です。
例えば、Webで自社サービスへの会員登録を行ったユーザーに対し、1通目に「会員登録に対してのお礼メール」、2通目に「自社商品の紹介」、3通目に「特別イベント・セミナーへの案内」を送るといった流れで実施されます。
ステップメールの役割
ステップメールの主な役割は、見込み顧客の購買意欲を、効果的かつ効率的に高めていくことです。手動によるメール配信の場合でも、顧客情報を基に顧客ごとにメールの内容を変えながら、タイミングを見計らって配信することも可能ですが、多くの作業工数がかかります。
ステップメールはこうしたメールを用いたマーケティング業務を自動化できるため、ベストなタイミングでメールを配信し、見込み顧客の購買意欲を醸成できます。
メルマガとの共通点と相違点

ステップメールとメルマガ(メールマガジン)は、どちらもメールマーケティングの一種です。メールマーケティングとは、見込み顧客・顧客リストに対してメールを送信し・アプローチし、反応に応じてアクションを起こすマーケティング手法です。
いずれも見込み顧客や顧客に対し、メールで有益な情報を届けることや、自社の商品・サービスをアピールする点では共通の役割があります。
しかし、詳細な目的・配信内容・配信タイミングにおいて、次の表に示すようにいくつかの違いがあります。
ステップメール | メルマガ | |
|---|---|---|
目的 | 見込み顧客の購買意欲の醸成や、顧客へのアップセル・クロスセル | 見込み顧客・顧客と接点をもち続けることや関係構築 |
配信内容 | 購買意欲を高めるような訴求が組み込まれている | 新商品やイベント開催の案内や、製品や業界情報などのお役立ち情報の発信 |
配信タイミング | ユーザーのアクションを起点に段階的に配信が始まる | メーリングリストに対し、一斉に送信する |
ステップメールは見込み顧客の購買意欲を高め、顧客にアップセル・クロスセルを促すために段階的に配信され、購買に導く内容です。
一方で、メルマガは見込み顧客・顧客との接点を保ちながら関係構築し、新商品やイベント情報、お役立ち情報を一斉に送信するものです。
ステップメールとメルマガは、目的・配信内容・タイミングが異なるため、状況に応じて使い分ける必要があります。
自社の商品・サービスへの理解を段階的に深めてもらい、徐々に購買意欲を高める場合にはステップメールを、新製品の情報やキャンペーン情報を届ける際にはメルマガが適しているといえるでしょう。
ステップメールのメリット
ステップメールをマーケティング活動に取り入れるメリットは、大きく次の3つです。
1、購買意欲を醸成できる
ステップメールの最大の特徴は顧客の購買意欲を段階的に高められる点です。ステップの配信は細かく設定できるため、最も効果的と考えられるタイミングでアプローチできます。
例えば、サブスクリプションのサービスを提供している企業のケースを考えてみましょう。
この場合、1カ月間の無料体験期間の終了直前で「本登録をすすめるステップメール」を配信することや、「本契約した場合に利用可能な機能」をあらためて訴求するといった内容が、見込み顧客の購買意欲醸成に有効と考えられます。
2、メールマーケティングを一部自動化できる
メールマーケティングを実施する際には、さまざまな業務が発生します。その中の配信業務を自動化できる点が、ステップメールのメリットといえます。
従来のメールマーケティングでは、顧客ごとの性質や状況を把握したうえで配信内容を使い分けることは、手間がかかり、難易度が高いとされていました。
一方で、ステップメールであれば、メールの内容や配信するタイミングやトリガーを設定しておくことで、自動で顧客にアプローチすることが可能です。
業務効率化によって削減できた時間や人的リソースを、マーケティングのコア業務である施策の立案や顧客対応に費やせるようになり、ビジネス成長の促進にもつながるでしょう。
3、効果測定が行いやすい
ステップメールでは、ステップごとの効果を測定できるため、施策の振り返りや今後の施策の立案にも生かせます。
例えば、1週間に分けて配信するステップメールのうち、5日目から開封率が低下しているケースでは、4日目までの配信内容で、その後のメールに対する興味付けができていない可能性があります。
このように、ステップメールはメールのパフォーマンスの計測が容易です。分析と改善を繰り返していくことで、メールマーケティングの効果をさらに高めていくことが可能です。
ステップメールのデメリット
ステップメールを活用する際には、以下のようなデメリットにも留意する必要があります。
1、導入にはコストがかかる
メールの配信自体は、GmailやOutlookなどの無料メール配信ツールで行えますが、ステップメールの配信設定には専用のツールが必要になるため、初期費用や月額費用が発生します。
また、条件に応じて配信内容を変更することや、複数のメールに対してトリガーを設定し順序立てて配信するなど、複雑な設定が必要です。
ステップメールの導入・設定には、金銭面・時間・人的リソースといった多方面でのコストがかかるため、それに見合った効果が得られるか事前に十分な検討が必要です。
2、メール制作・シナリオ設計の難易度が高い
ステップメールを活用して顧客の購買意欲を高めていくためには、セールスライティングやコピーライティングのスキルも求められます。こうしたスキルは一長一短で身につくものでもないため、長期的にライティングスキルを磨いていく必要があります。
社内で適切なスキルをもつ人材がいない場合は、外部への委託を視野に入れることも一案です。
また、ステップメールでは複数のメールを作成し、顧客の興味関心を徐々に高めていくよう組み合わせていく必要があるため、メルマガよりもシナリオ設計の難易度が高い点もデメリットといえます。「顧客のニーズとマッチしているか」「配信する内容に過不足はないか」「効果的な順番・タイミングで訴求できているか」といった点を考慮したうえで、シナリオを設計する必要があります。
3、最新情報の配信には向いていない
ステップメールは、あらかじめ設定したスケジュールや内容に基づき段階的に配信されるため、最新情報の配信には向いていないケースがあります。
急な変更やリアルタイムでの情報更新が必要な場合、メール内容を変更する作業が発生します。頻繁なメール内容の変更や調整が求められる場面では、ステップメールよりもメルマガのほうが適しているかもしれません。具体的には、法律や仕組みの改正、緊急性を要するトレンドの配信などは、その都度メルマガを作成・配信すると良いでしょう。
ステップメールのデメリットも考慮しつつ、適切なメールマーケティングの手法を選択することが重要です。
ステップメールの作成・配信方法

ステップメールを作成する際は、次のステップに沿って進めていきましょう。
STEP1:ゴールを明確にする
ステップメールを成果につなげるためには、明確なゴールの設定が不可欠です。ゴールが定義されていない場合、メールの効果測定が難しくなり、目的達成への方針も不透明になります。
たとえば、次のような具体的かつ測定可能な目標を設定すると良いでしょう。
- 新規見込み顧客の創出
- 既存顧客のリピート購入
- 特定の商品の売り上げ向上 など
このような目標に対し、開封率・クリック率・購入率などの「KPI(重要業績評価指標)」を設定することで、メールキャンペーンの効果を評価しやすくなります。また、目標達成に要する期間を設定し、成果を確認するためのスケジュールも立てておきましょう。
STEP2:ターゲットを絞る
効果的なステップメールキャンペーンを構築するには、ターゲットを具体的に絞り込む必要があります。広い層に一律でメールを送付するよりも、特定のニーズや関心を持つグループに絞ったほうが成果につながりやすくなります。
ターゲットを絞ることで、メッセージがよりリアルで魅力的なものになり、受け手の関心をひきやすくなります。
具体的には、顧客データを基に共通の属性や行動パターンに基づきセグメントを作成します。マーケティング領域におけるセグメントとは、市場や顧客を特定の基準でグループに分類することです。
たとえば、購買履歴や興味関心に基づきセグメントを作成するといった方法があります。
STEP3:カスタマージャーニーマップを作成する
ターゲットを設定したあとは、カスタマージャーニーマップを作成します。
カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品・サービスを認知し、企業とのファーストコンタクトから購入、アフターフォローに至るまでの一連の流れを可視化したものです。マーケティング施策の立案や実行に作成するケースが多いですが、ステップメールでも活用できます。
ステップメールでカスタマージャーニーマップを作成すると、顧客の心理状況や行動の変化を顧客視点に立って考えメールの内容を考えられるようになります。
たとえば、認知フェーズでは商品・サービスの特徴を詳しく述べる、購入フェーズでは利用することで得られる効果を訴求するなどです。
STEP4:シナリオを構築する
ステップ3で作成したカスタマージャーニーマップを参考に、シナリオを構築します。このステップでは、ステップメールの内容や配信数、間隔などの詳細を決めましょう。
シナリオを作成するうえでのポイントは、最後まで読んでもらえるような構成にすることです。1通目で顧客の関心を引き、段階的に信頼を築いたうえで、最終的な購入を促す構成にすることが重要です。
なお、シナリオの正解は一つではないため、このステップで100点満点をめざすのではなく、効果改善をしていく前提で作成すると良いでしょう。
STEP5:メール文を作成・配信する
最後に、シナリオをベースとしながら、顧客の悩みやニーズを解消できるメール文を作成します。簡単なステップメールであれば人の手によっても行えますが、複雑な条件分岐に沿ってステップメールを組むのは難易度が高いため、専用ツールの導入も検討すると良いでしょう。
ステップメールは一度作成して終わりではなく、見込み顧客や顧客の反応・フィードバックを参考に、適宜更新していくことが重要です。詳しくは「ステップメールを作成・配信する際のポイント」の章でも解説しています。
ステップメールの配信数と間隔の目安
ステップメールの適切な配信数は、業種や商材の特性、価格帯によって異なるため、自社の状況に応じて柔軟に設計する必要があります。
たとえば、商品・サービスの価格が高額で購入のハードルが高く、検討期間が長期化しやすい場合は、配信数を多めに設定し、段階的に購入意欲を高めていくと効果的です。
一方で、初期費用が比較的低額なサブスクリプションタイプのサービスなどであれば、序盤の段階から購買を訴求してみても良いかもしれません。
ステップメールの適切な配信頻度は、見込み顧客・顧客のニーズの高さや状況によって異なります。購入意思が明確な見込み顧客に対しては、意欲が高いうちに購入を促すメールまで送信したほうが、高い効果が見込めるケースもあります。
ステップメールの配信数や配信間隔に絶対的な正解はないため、開封率やコンバージョン率などの実績データをもとに、適宜見直すことが重要です。
ステップメールの構成パターン例
ステップメールの構成パターンは目的に応じて基本型と短期集中型、長期育成型の3種類から選択できます。ここでは、パターン別の違いについて解説します。
パターン1:基本型(7通)
基本型の7通構成は多くの業界で実績のある標準的なステップメール形式です。初回のお礼と案内から始まり、価値提供や問題提起、解決策提示と段階的に信頼関係を構築します。
具体的な発信内容と目的を配信順でまとめると、以下の通りです。
配信順 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
1通目 | 初回お礼と案内 | 登録への感謝と今後の流れを説明 |
2通目 | 価値提供と関係構築 | 有益情報の提供で信頼関係を構築 |
3通目 | 問題提起 | 顧客が抱える課題を明確化 |
4通目 | 解決策提示 | 課題に対する具体的な解決方法を提案 |
5通目 | 事例紹介 | 成功事例で効果を証明 |
6通目 | 特典案内 | 限定特典で購入意欲を高める |
7通目 | 最終オファー | 購入決断を促す最終案内 |
基本型の特徴は各ステップの目的が明確で、顧客の心理状態に合わせた内容設計ができる点です。一般的に配信間隔は2〜3日おきに設定し、約2週間かけて信頼関係を構築していきます。
パターン2:短期集中型(5通)
短期集中型は限られた期間で素早く成約に結びつけたい場合に効果的な構成です。お礼とプレゼントから始まり、悩みへの共感と解決策、具体的なノウハウの提供へと進みます。
具体的な発信内容と目的を配信順でまとめると、以下の通りです。
配信順 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
1通目 | お礼とプレゼント | 即時価値提供で関心を引く |
2通目 | 悩み共感と解決策 | 顧客の課題に共感し解決の方向性を示す |
3通目 | 具体的ノウハウ | 実践的な情報提供で専門性をアピール |
4通目 | 事例と実績 | 具体的な成功事例で信頼性を高める |
5通目 | 限定オファー | 期間限定性を強調し即決を促す |
短期集中型では、各メールの内容を充実させ、1〜2日おきに配信することで、顧客の関心を維持することが重要です。
限定感や緊急性を適切に伝えることで、迅速な行動喚起につなげられます。
パターン3:長期育成型(10通)
長期育成型は顧客との関係構築を重視し、丁寧に信頼関係を築いて成約へと導く構成です。
初回お礼から始まり、自己紹介、業界課題提示と段階的に専門性と信頼性を示していきます。
配信順 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
1通目 | 初回お礼 | 登録への感謝と関係構築の第一歩 |
2通目 | 自己紹介 | 信頼性と親近感の醸成 |
3通目 | 業界課題提示 | 業界の問題点を共有し共感を得る |
4通目 | 基礎知識提供 | 教育的価値の提供で専門性をアピール |
5通目 | 具体的解決策 | 課題に対する解決方法の提案 |
6通目 | 実践テクニック | 具体的な実践方法の紹介 |
7通目 | 成功事例 | 実際の成功例で効果を証明 |
8通目 | 特典案内 | 購入メリットの強調 |
9通目 | FAQ対応 | 不安や疑問の解消 |
10通目 | 最終案内 | 購入決断を促す最終アプローチ |
長期育成型では各メールの間隔を3〜4日程度に設定し、約1カ月かけて丁寧な関係構築を行います。顧客の理解度や反応を見ながら配信間隔を調整することで、より効果的なコミュニケーションが実現できます。
ステップメールのツールを選ぶ際のポイント
ステップメール配信ツールの選定は、配信規模や予算、必要機能を明確にした上で複数のツールを比較検討することが大切です。ここでは、ツールを選ぶ際のポイントについて解説します。
配信上限と料金プランを確認
ステップメールツールを選ぶ際は、自社の配信予定数に応じた配信上限と料金プランの確認が不可欠です。
多くのツールでは、月間配信数やメールアドレス登録数に応じて段階的な料金体系を採用しており、事業規模に合わせた選択が可能です。
小規模から始める場合は、無料プランや低価格プランから始め、配信数の増加に応じてアップグレードできるツールが適しています。一方、大規模な配信を予定している場合は、ボリュームディスカウントがあるプランが費用対効果に優れています。
料金プランの比較では月額費用だけでなく、初期設定費用やオプション機能の追加費用も含めた総コストで判断することが重要です。将来的な配信数の増加も見据えて、スケーラビリティの高いプランを選択することで、長期的なコスト管理が可能になります。
効果測定・分析機能の有無
効果的なステップメール運用には、詳細な効果測定と分析機能が不可欠です。開封率やクリック率、コンバージョン率などの基本指標を測定できるだけでなく、メール内の各リンクの反応を分析できる機能が重要です。
高度な分析機能を備えたツールでは、A/Bテストやセグメント別の反応分析が可能となり、継続的な施策改善を強力にサポートします。
データの視覚化機能やカスタムレポート作成機能があれば、経営層への報告や意思決定も容易になります。
効果測定機能を選ぶ際は、自社のKPIに合わせた指標が測定できるかを確認することが重要です。
セキュリティー対策
ステップメールツールの選定では、顧客情報を扱う以上、セキュリティ対策が整っているかの確認が必須です。ISO27001やプライバシーマークなどの認証取得状況、データ暗号化の対応状況を確認することで、情報漏えいリスクを最小化できます。
信頼性の高いツールでは、二段階認証やIPアドレス制限などのアクセス管理機能が実装されており、不正アクセスを防止します。また、定期的なセキュリティアップデートやバックアップ体制が整っているかも重要な判断基準です。
ユーザーサポート体制の充実度
ステップメールツールの運用では、技術的な問題や操作方法の疑問が生じた際のサポート体制が重要です。メールやチャット、電話などの複数のサポートチャネルが用意されているか、日本語対応の有無を確認することが必要です。
サポート対応時間が自社の業務時間と合致しているか、緊急時の対応体制が整っているかも重要な判断基準となります。マニュアルやナレッジベース、動画チュートリアルなどの自己解決リソースが充実しているツールは、日常的な運用がスムーズです。
他システムとの連携機能や拡張性の有無
効率的なマーケティング活動には、ステップメールツールと他システムとの連携が重要です。CRMやMAツール、SNSなど、既存システムとのデータ連携がスムーズに行えるかを確認することが必要です。
APIやWebhookなどの連携機能が充実しているツールでは、自動化やワークフローの構築が容易になります。また、Zapierなどの連携サービスに対応しているかどうかも、システム間の連携を簡易化する重要な要素です。
ステップメールを作成・配信する際のポイント

効果的なステップメールの作成・配信には、次のポイントを押さえると良いでしょう。
コピーライティング・セールスライティングを駆使する
ステップメールを使った施策の成否の要となるのは、配信するメールの内容です。自社の商品・サービスをアピールしつつ、顧客の購買意欲を高めていくにはコピーライティングやセールスライティングが欠かせません。コピーライティングの目的は商品・サービスの認知度を高め興味付けすることであり、セールスライティングは最終的な行動を促すものです。
こうしたライティングテクニックを適宜取り入れることで、メールマーケティングの効果を最大限高めていけるでしょう。
定期的にメールの件名やシナリオの内容を再考する
デジタル化やインターネットの発達、SNSの普及にともない、顧客はさまざまな情報にアクセスできるようになりました。こうした状況下では、顧客の取り巻く環境や抱えている悩み・課題も急激に変化します。
変化に迅速に対応するためにも、ステップメールは一度作成して終わりではなく、施策の効果を測定しながら、定期的にメールの件名やシナリオの内容を再考していく必要があります。
メールのパフォーマンスを総合的に評価するとともに、メールごとの開封率やコンバージョン率などを細かく評価していき、改善していきましょう。
外部ツールと連携する
ステップメール配信ツールによっては、MA・SFA・CRMなどの外部マーケティングツールと連携が可能なツールもあります。MA・SFA・CRMのそれぞれの概要は以下の通りです。
- MA(Marketing Automation):マーケティング業務を自動化・効率化できるツールやシステム。リードジェネレーション(見込み顧客の創出)からリードナーチャリング(購買意欲の醸成)、コンバージョン(成約)に至るまでのマーケティングの一連の流れで活用できる。
- SFA(Sales Force Automation):営業や顧客管理に役立つツールやシステム。顧客情報・案件・商談を管理でき、営業を効率化する際に役立つ。
- CRM(Customer Relationship Management):顧客関係管理とも呼ばれるツール。顧客情報を管理・統合し、社内で共有することで良好な顧客関係を構築する。
ステップメール配信ツールと外部ツールとの連携によって、顧客情報の共有や把握がスムーズになるほか、より包括的な顧客情報の取得や管理が可能になります。
例えば、メール以外のチャネルでのマーケティング施策の実施や、パーソナライズとターゲティングの精度の向上が期待できます。これにより、ユーザーへより価値のあるコンテンツを提供しやすくなります。
ステップメール配信ツールを導入する際は、こうした外部ツールと連携できるかをあわせて確認しましょう。
最新かつ正確な顧客情報を活用する
ステップメールの効果の最大化には、最新で正確な顧客情報の活用が求められます。顧客の行動や嗜好(しこう)が変化する中では、最新の情報に基づいてパーソナライズされたコンテンツを提供することで、受け手の興味を引き、購買意欲を高めやすいためです。
定期的なデータの更新や顧客行動のモニタリングを通じ、タイムリーで適切なメッセージを届け、顧客との関係を強化することがポイントです。そのためには、最新かつ、正確な顧客情報を得られるような体制を整える必要があります。
オンラインであれば、Webサイトのアクセスログ解析・フォームへの入力情報・顧客アンケートなどから、オフラインであればセミナーやイベントでの名刺交換などから顧客データを収集し、活用しましょう。
取得した顧客情報を正確かつ最新な状態でデータベース化することで、ステップメールはもちろん、さまざまなマーケティング活動に生かせる基盤を整えられます。
ステップメールを運用する際の注意点
ステップメールの効果的な運用には、法令遵守から配信設計、効果測定まで多角的な視点での管理が必要です。ここでは、ステップメールを運用する際の注意点について解説します。
特定電子メール法の遵守を徹底する
ステップメール運用では、特定電子メール法をはじめとする法令遵守が最優先事項です。受信者の明示的な同意を得た上での配信や送信者情報の明記、配信停止手続きの簡便化など、法的要件を満たした運用が必要です。
法令違反は企業イメージの低下だけでなく、罰金などの法的制裁を受ける可能性があります。
定期的な法令知識のアップデートと社内ルールの見直しを行い、コンプライアンス体制を強化することが重要です。
法令遵守の実践では、オプトイン取得時の同意文言の明確化やプライバシーポリシーの適切な表示が必要です。配信リストの定期的なクリーニングを行い、長期間反応のないアドレスを除外することで、スパム判定リスクを低減できます。
定期的なKPIの確認と改善を行う
ステップメールの効果を最大化するには、開封率やクリック率などの重要指標を定期的に確認し、改善活動を継続することが必要です。業界平均値や自社の過去データと比較分析することで、現状の課題を明確化できます。
効果測定では単純な数値だけでなく、メールごとの反応傾向や顧客セグメント別の反応差異も分析しましょう。A/Bテストを活用して件名やコンテンツ、配信タイミングなどの要素を最適化することで、継続的な改善が可能になります。
KPIの管理においては、短期的な数値変動だけでなく、長期的な傾向も把握することが不可欠です。
定期的なレビューを設け、営業部門や商品開発部門とも情報共有することで、全社的な改善活動につなげられます。
配信タイミングの最適化を図る
ステップメールの効果を高めるには、顧客の行動パターンに合わせた配信タイミングの最適化が重要です。業界や顧客層によって最適な曜日や時間帯は異なるため、データに基づいた検証と調整が必要になります。
ビジネスパーソン向けなら平日の午前中や夕方、一般消費者向けなら平日夜や週末が効果的とされていますが、自社データに基づく検証が不可欠です。配信間隔も顧客の購買サイクルに合わせて設計します。
タイミングの最適化では、顧客のアクションに連動した配信設計も効果的です。メール開封やリンククリックなどの行動に基づいて次のメールを配信すれば、顧客の関心が高いタイミングでの適切なアプローチが可能になります。
まとめ
ステップメールは、予定したタイミングやトリガーに基づき、あらかじめ作成したメールを順番に自動で配信するものです。見込み顧客や既存顧客の購買意欲を高められるほか、メールマーケティング業務の一部を自動化できるメリットがあります。
効果的なステップメールの作成・配信には、コピーライティングやセールスライティングの活用に加え、内容の定期的な見直しが求められます。また、顧客情報を最新かつ正確な状態で収集・管理できる体制の構築も不可欠です。
営業DXサービス「Sansan」は、名刺をはじめとした顧客との接点情報を一元管理し、全社での共有やメール配信を可能にするサービスです。顧客情報を正確かつ最新の状態でデータベース化でき、MAツールと連携することで、顧客情報を基にしたメール配信も可能です。
ステップメール配信をメールマーケティングの一環として取り組みたい方は、Sansanの導入をぜひご検討ください。
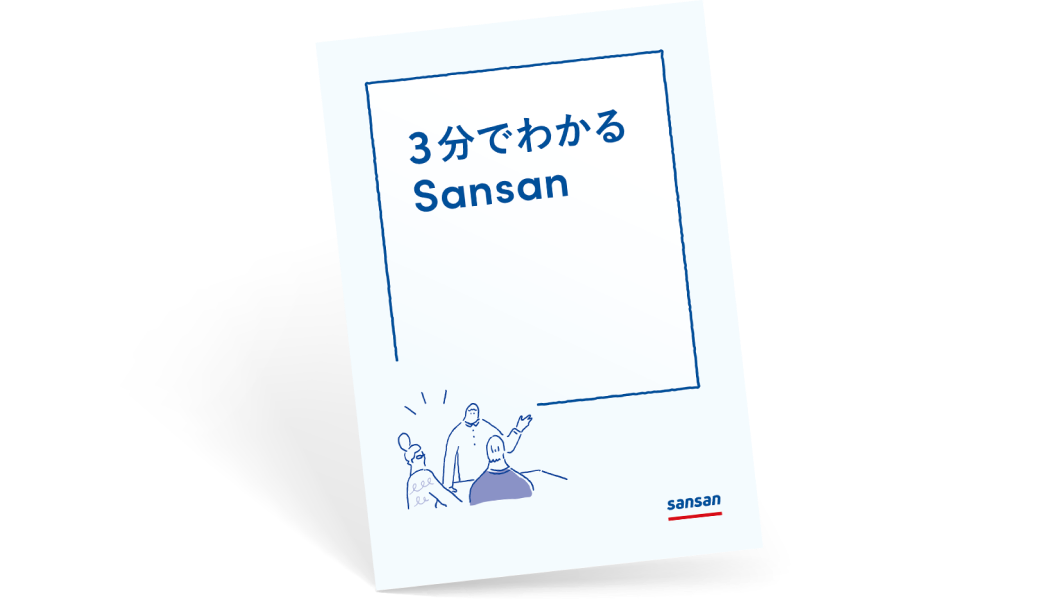
3分でわかる Sansan
営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部