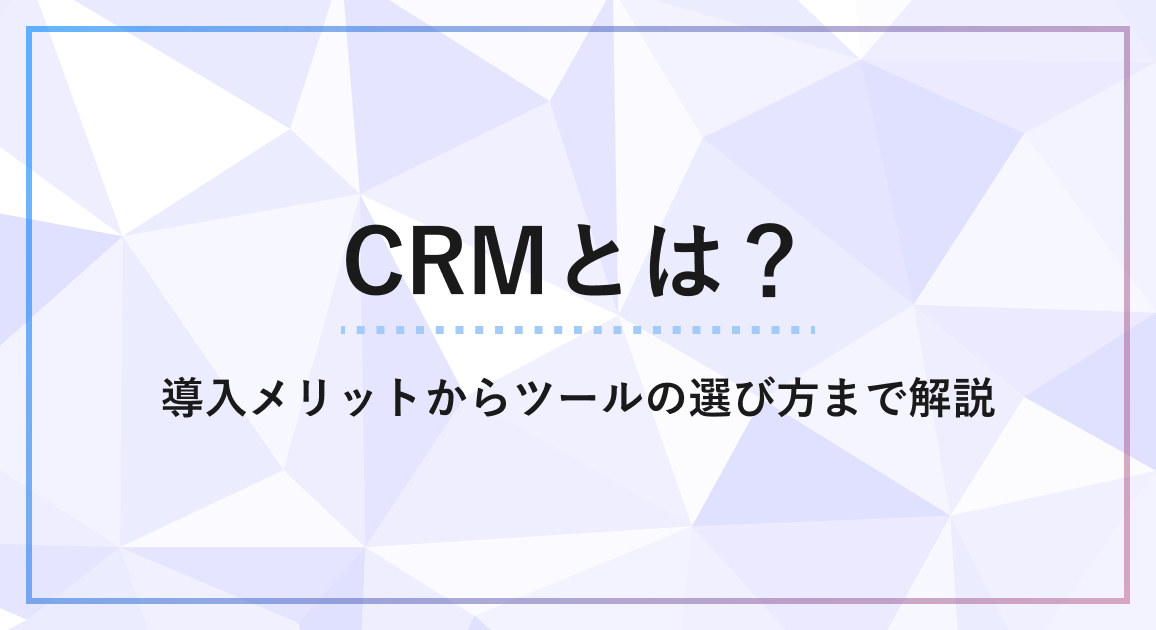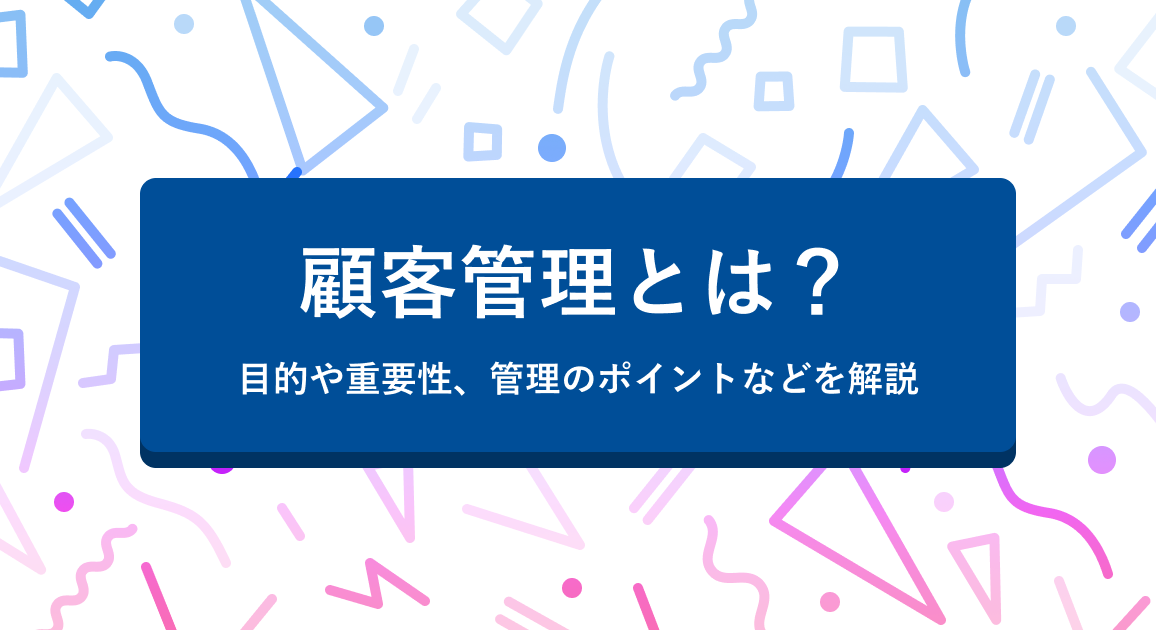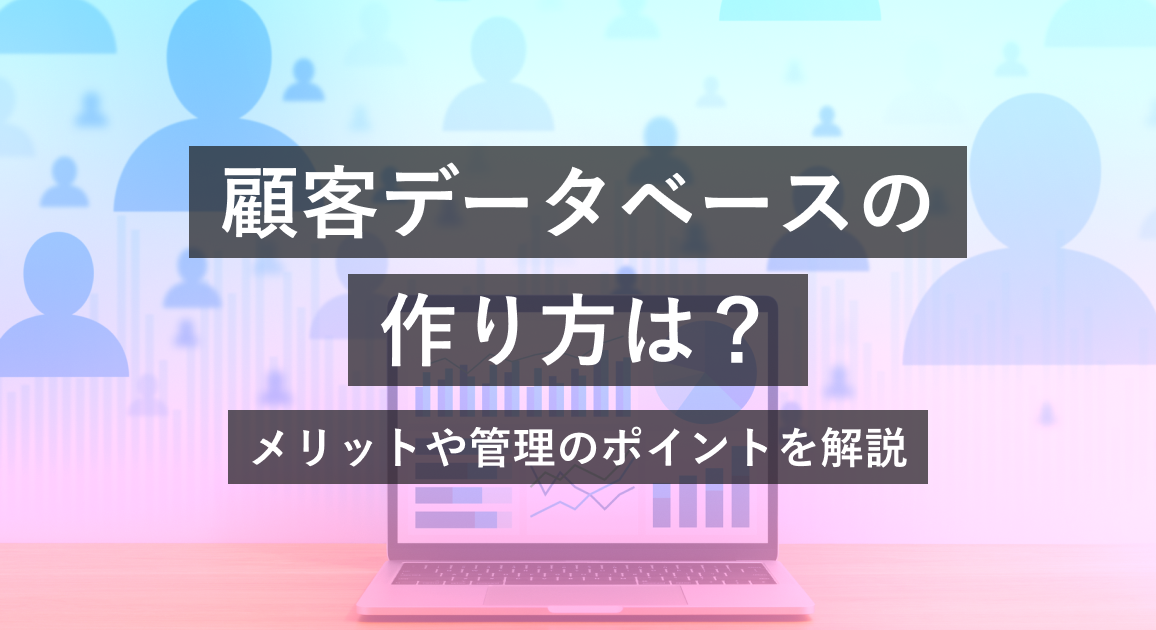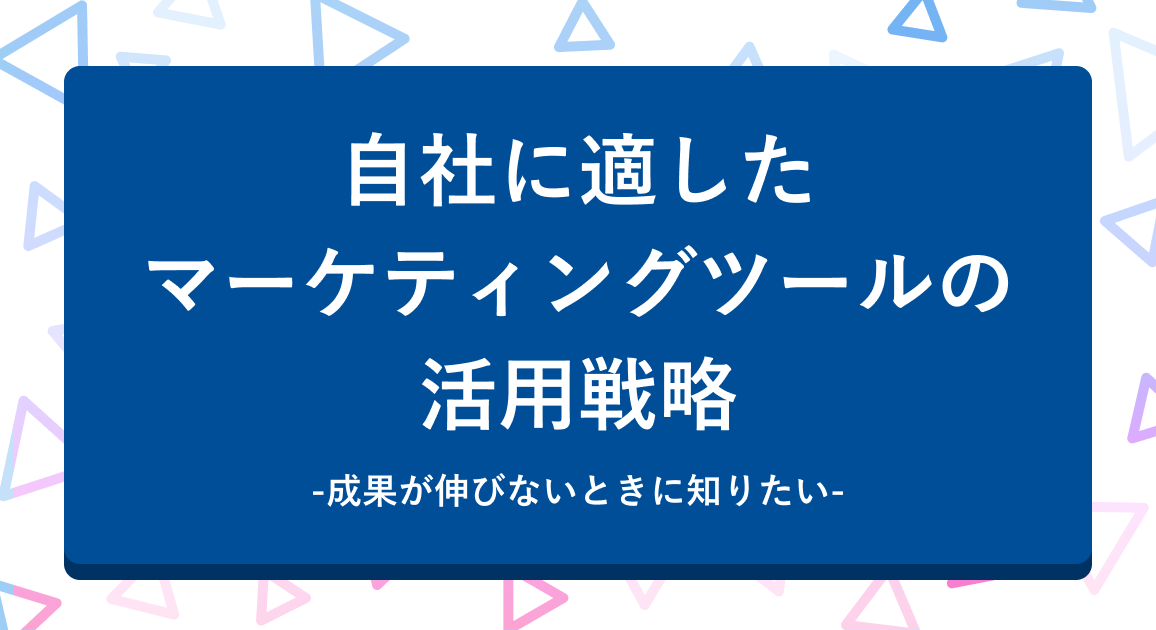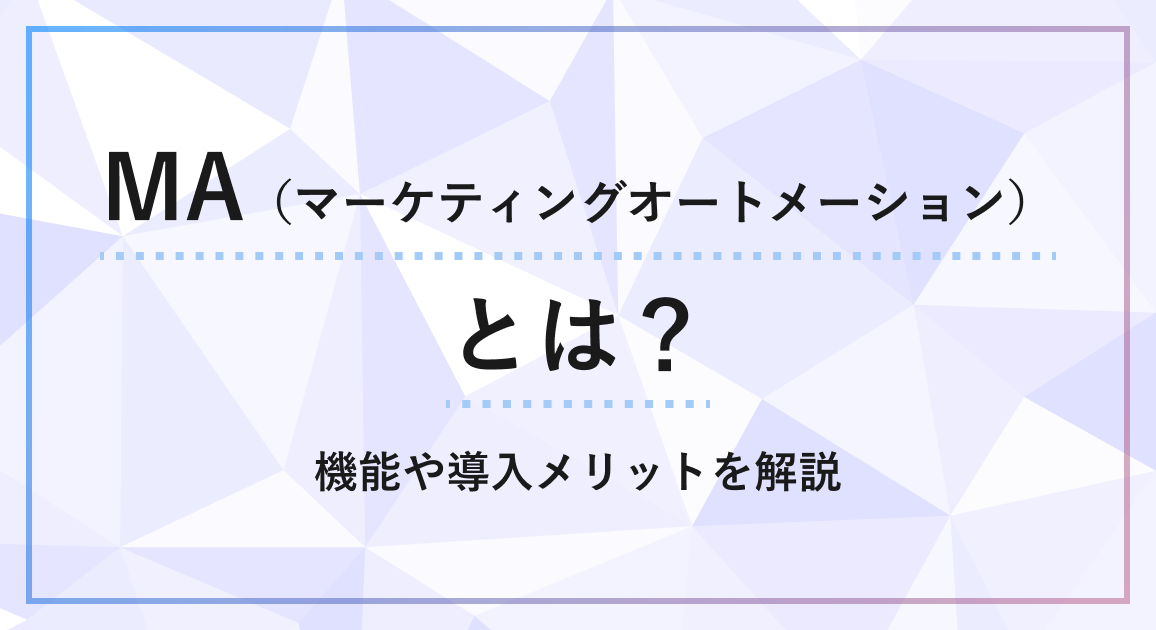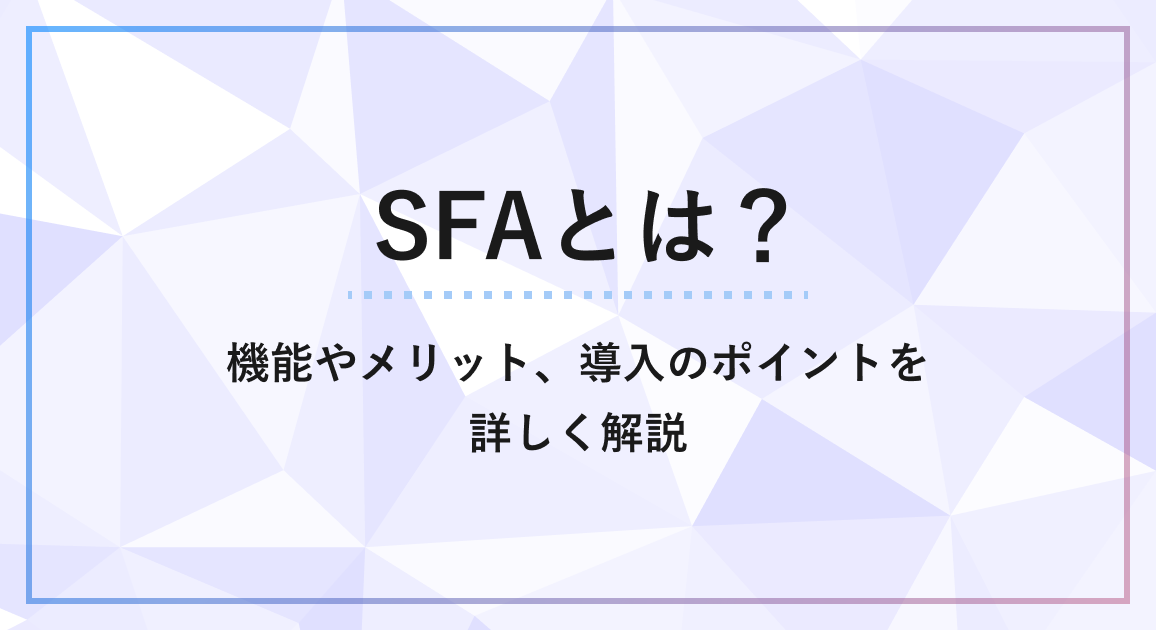- CRM
CRMはコールセンターに必要?導入のメリットや注意点を解説
公開日:
更新日:

コールセンターは、企業と顧客をつなぐ重要な役割がある部門です。顧客のニーズをくみ取り、商品・サービスの質改善や開発するためには、欠かせません。
コールセンターで得た顧客情報は人力でも管理できますが、規模が大きくなってくると煩雑になり、ビジネスに生かすのは難しくなるでしょう。そこで有効なのが、コールセンターでCRMを活用することです。
本記事では、コールセンターにCRMが必要な理由や導入するメリットなどを解説します。コールセンターで求められる機能や注意点などもあわせて紹介するので、CRMをコールセンターに導入する際に参考にしてください。
使いにくい顧客データの問題を解決
コールセンターにおけるCRMの役割

CRM(Customer Relationship Management)とは、「顧客関係管理」とも呼ばれる、顧客管理に役立つツールやシステムの総称です。
CRMに対して、営業部門やマーケティング部門など、売り上げを直接作っている部門が活用しているイメージを感じるかもしれません。しかし、顧客との窓口となり、かつ良好な関係性を作っていくうえで欠かせない部門のコールセンターでも、CRMは重要です。
次章以降で、その理由をご紹介します。
コールセンターでCRMが求められる理由
CRMがコールセンターで求められている背景にあるのが「顧客ニーズの多様化」です。
インターネットやSNSが普及した結果、顧客は自らさまざまな情報に触れられるようになりました。これまで企業が一方的にマーケティング活動を行い、顧客に購入してもらっていた時代から、顧客自身が商品・サービスを選ぶ時代へと移行しています。
多様化する個々のニーズや好みに柔軟に対応し、One to Oneの対応をしていくためには、顧客を深く理解し、それぞれに最適な提案をしていく必要があるでしょう。
コールセンターがこうした流れに対応し、顧客対応や顧客情報の集積・管理など、企業の中で求められる役割を果たす際に、CRMが役立ちます。
CTIとの違い
CTI(Computer Telephony Integration)とは、電話・FAXとコンピューターシステムを連携させる技術です。
顧客情報を画面に自動で表示させるポップアップ機能や、特定のオペレーターに負担がかからないようにする電話制御機能、トラブル防止やサービスの質改善に役立つ録音・着信履歴機能などを指します。
CTIの主な目的が「業務効率化」なのに対し、CRMの目的は「顧客情報を把握し、適切なアプローチをする」という点で、両者は異なります。顧客情報を適切に活用する観点から、CTIを単体で導入するのではなく、CRMもあわせて導入するのがおすすめです。
コールセンターにCRMを導入するメリット

ここでは、コールセンターにCRMを導入する、次の3つのメリットを解説します。
- カスタマーサポートの質の強化
- コールセンターの業務効率化
- コールセンターで得た顧客情報の社内共有
カスタマーサポートの質の強化
CRMには、顧客からの問い合わせ内容や対応状況などのデータを蓄積できます。
蓄積した情報をカスタマーサポートのナレッジベースとすることで、対応の質を高められるでしょう。例えば、オペレーターが初めて直面した課題でも、過去の記録を参考に対応にあたることで、スムーズに乗り切ることができます。
トラブルに迅速に対応できれば、マイナスなイメージを抱いている顧客の心理を、プラス方向に転換することも可能です。結果的に、顧客からの信頼を得つつ、顧客満足度も向上させられるでしょう。
コールセンターの業務効率化
CRMでは、顧客の氏名や住所、電話番号、メールアドレスなどの基本的な情報はもちろん、過去の問い合わせ内容や購入履歴、行動パターン、Webアクセスログなどを確認できます。
CRMを通して一元管理されたこれらの情報をベースに顧客対応にあたることができれば、業務を効率化できるでしょう。例えば、顧客の商談内容は営業部門に問い合わせしなければならなかった課題を、CRMで確認すればコールセンター内で対応を完結できるようになります。
また、顧客からのフィードバックを基に、商品・サービス開発を行うことも可能です。
コールセンターで得た顧客情報の社内共有
コールセンターで得た顧客の情報は、営業・マーケティングにも役立ちます。さらなる顧客満足度の向上のためにも積極的に社内で共有すべきでしょう。その際、CRMを導入しているとスムーズにデータを共有できます。
顧客との窓口となるコールセンターには、顧客の声が集まりやすいという特徴があります。コールセンターで得た顧客の意見を営業やマーケティング部門に共有すれば、商品・サービスの質改善・向上や、新商品の開発につなげられるでしょう。
また、質の高い顧客情報を社内で共有することで、迅速なサポートを提供できるようにもなります。顧客の抱えている課題を先回りで解決できれば、顧客満足度を高められるでしょう。
コールセンターにCRMを導入する際の注意点

コールセンターにCRMを導入すると、先述したさまざまなメリットを得られますが、いくつか注意点もあります。導入する際は、次の3つに注意してください。
- 導入の目的を明確にする
- 長期目線を持って取り組む
- 導入にはコストがかかることを理解する
導入の目的を明確にする
導入に当たっては、業務効率化なのか、顧客満足度を高める施策のためなのかなど、目的を明確にしておく必要があります。
目的を明確にし、それらを共有できていれば、コールセンター部門全体からの理解を得やすく、導入がスムーズに進みやすいでしょう。効果測定を的確に行うという観点からも、導入意図の具体化・共有は欠かせません。
また、目的を明確にできていれば、導入するツールを決めやすいのはもちろん、戦略やプランを策定しやすくなります。
長期目線を持って取り組む
コールセンターにCRMを導入したからといって、すぐに求める効果が表れ始めたり、課題を解決できたりするわけではありません。
CRMの本来の目的は「顧客との関係性をより良好にする」ことです。そのためには、じっくり時間をかけて信頼関係を構築していく必要があります。導入当初はなかなか結果が出なくても、PDCAサイクルを回しながら、施策の効果を分析・検討し、長期的に取り組んでいきましょう。
導入にはコストがかかることを理解する
CRMの導入に当たっては、金銭的・時間的コストがかかる点は事前に把握しておきましょう。
ツール導入利用の初期費用や月額料金、サポート費用、人件費などがかかります。また、社員がツールの利用に慣れ、使いこなせるまでにある程度の時間を要するでしょう。
CRM導入で得られる効果ばかりに焦点を当てるのではなく、時間的・金銭的コストがどれくらいかかるのかを把握したうえで、費用対効果を考慮し、導入を検討してください。
コールセンターに導入するCRMの選び方

数多くのCRMがあるので、何を導入すべきか迷う方もいるでしょう。コールセンターに導入するCRMは、次の3つのポイントを軸に選ぶと良いでしょう。
必要な機能が過不足なくそろっているか確認する
CRMの機能に不足があると、顧客情報をベースとした営業活動やマーケティング活動に支障が出ます。顧客情報管理機能に加えて、部門を超えて共有できる機能や、検索機能、FAQ作成機能などがあると良いでしょう。
ただし、ハイスペックすぎるとかえって使いこなせない可能性があります。CRMの良さを引き出せず、かけたコストが無駄になりかねません。
機能が過不足なくそろっているか判断するためにも、注意点であげたように導入の目的を明確にしておくことが重要です。
操作性に優れているか
企業と顧客の接点となるコールセンターでは、CRMを頻繁に操作することが想定されます。そこで重要なのが、ツールの操作性です。
ボタンの大きさや配置、画面の構成など個人の好みもありますが、操作性に優れているものは基本的に誰にとっても使いやすいでしょう。反対に操作が難しいと、ツールの機能を最大限引き出せず、導入の目的を達成することなく頓挫してしまう可能性があります。
実際の使用感を確かめるために、デモ版があれば申し込んでみるのがおすすめです。
他ツールとの連携を取れるか
外部ツールと連携が取れるか否かも、重要なポイントです。CRMは単体でも役立つツールですが、MAやSFAなどのツールと活用すると、良質な顧客体験を提供できたり、営業効率を高められたりします。
MA(Marketing Automation)とは、マーケティング業務を自動化・効率化するツールやシステムの総称です。リード創出からリードナーチャリング、コンバージョンに至るまでの流れで活躍します。
SFA(Sales Force Automation)とは、営業や顧客管理に役立つツールやシステムの総称です。営業効率を高められるほか、今後の施策の立案にも活用できます。
MAとSFAの詳細は、こちらの記事を参考にしてください。
まとめ
顧客と企業の架け橋となるCRMは、コールセンターにおいて有用です。社内で顧客情報を共有できるほか、カスタマーサポートの質改善やオペレーターのストレス軽減など、さまざまなメリットがあります。
必要な機能が搭載されているか把握するためにも、事前に運用の目的や現状の課題を理解しておきましょう。
今回紹介したCRMと同様に、Sansanは顧客情報や対応履歴のデータを蓄積・活用できるサービスです。コールセンターにおけるカスタマーサポートの質を改善したり、得られた情報を営業やマーケティング部門に共有したりする際に役立ちます。
MAやSFAなどの外部ツールとの連携も可能で、企業の営業・マーケティング活動を後押しします。ぜひ導入をご検討ください。
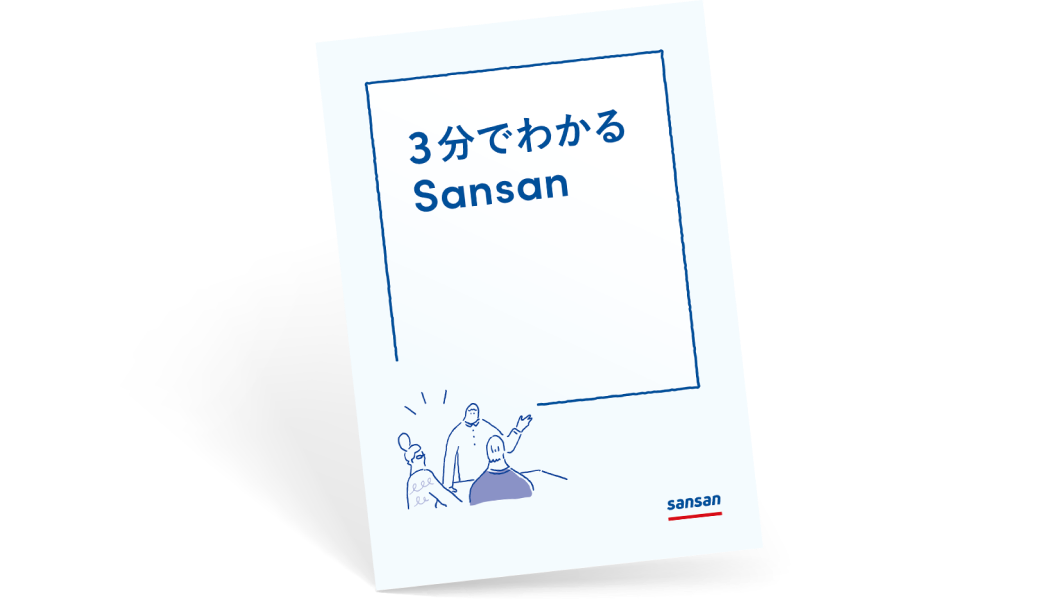
3分でわかる Sansan
営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部