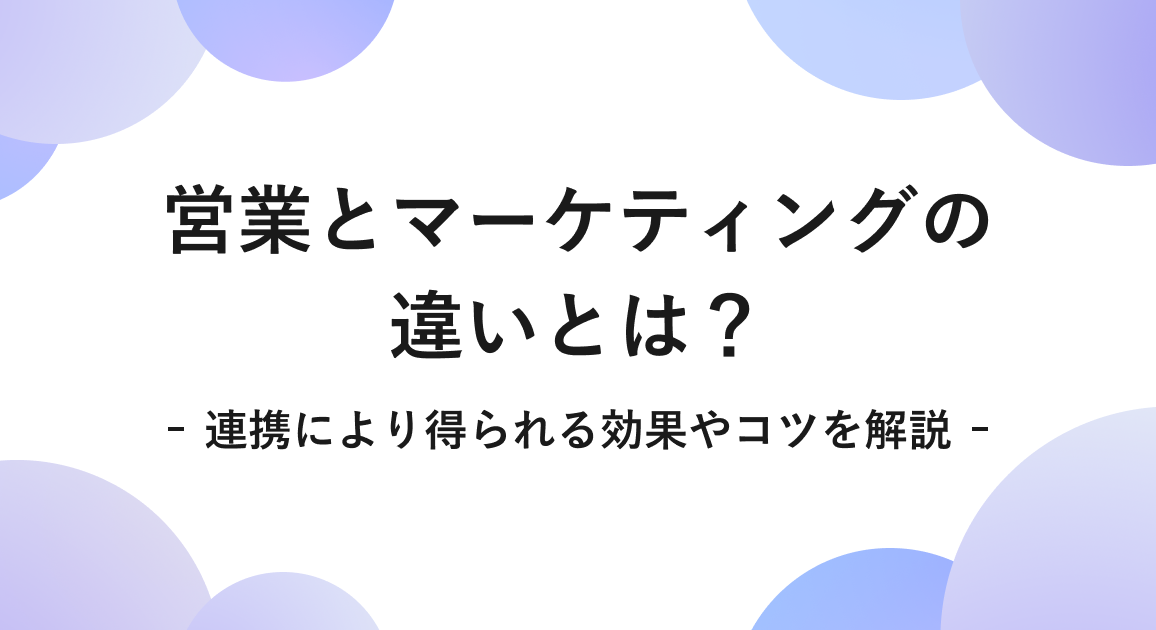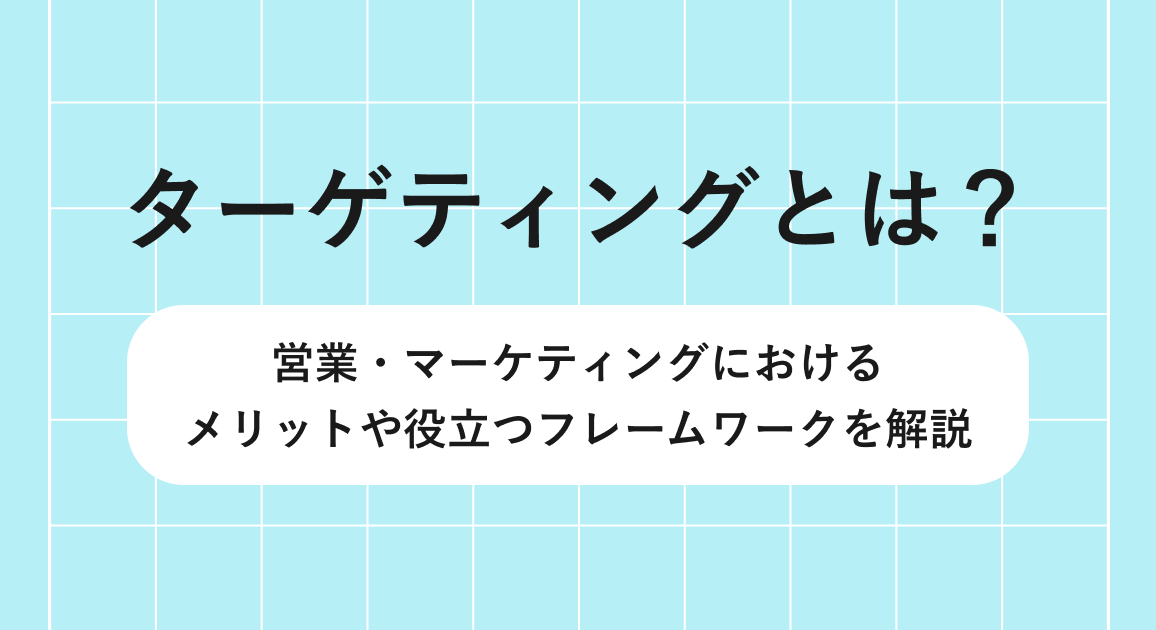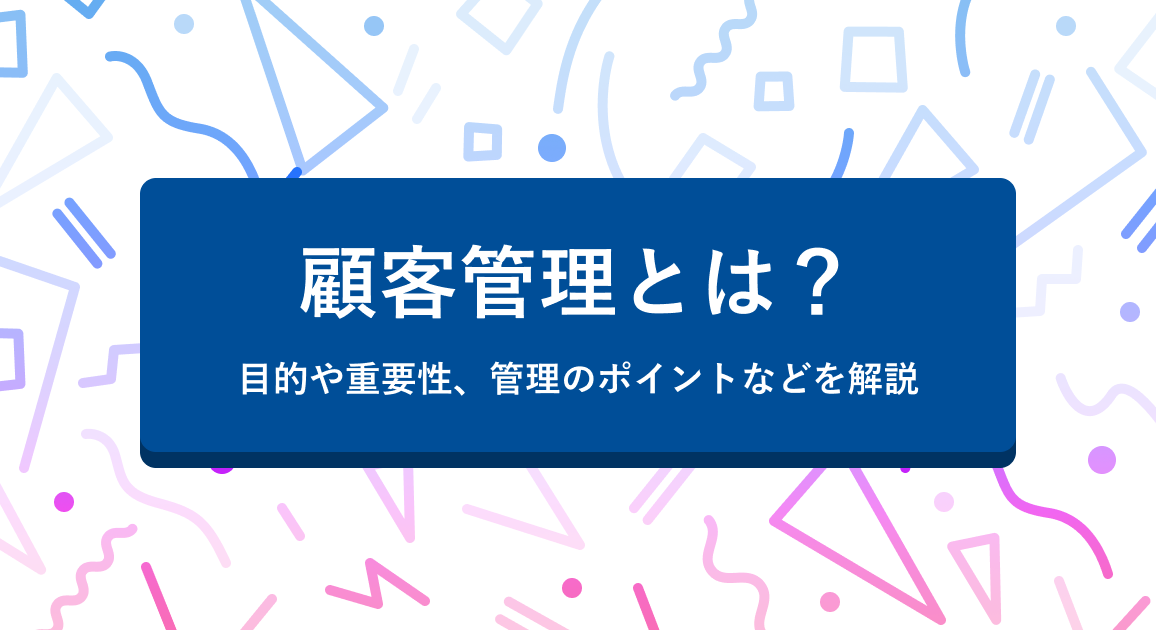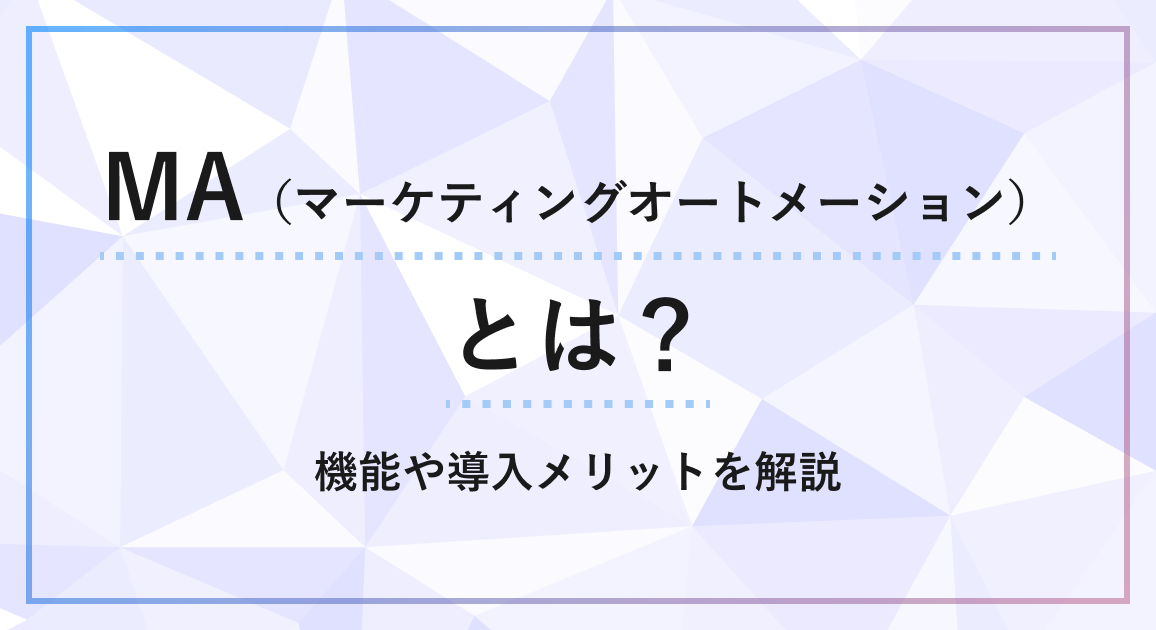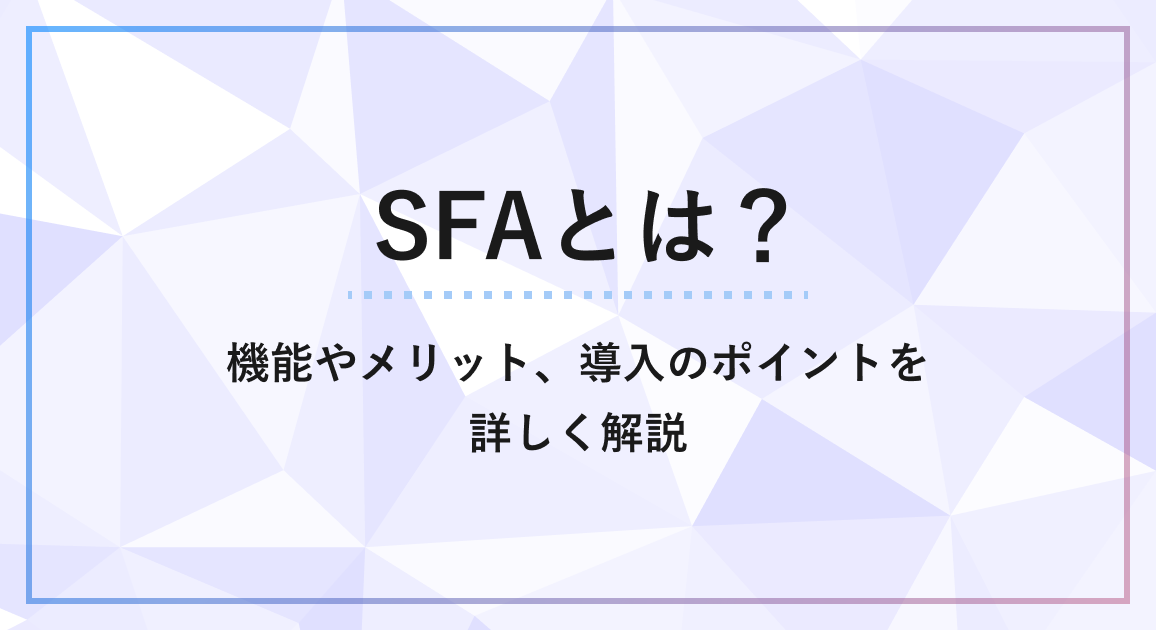- マーケティングノウハウ
マーケティングの意味とは?マーケティングの種類や施策立案の流れ、ポイントを解説
公開日:
更新日:
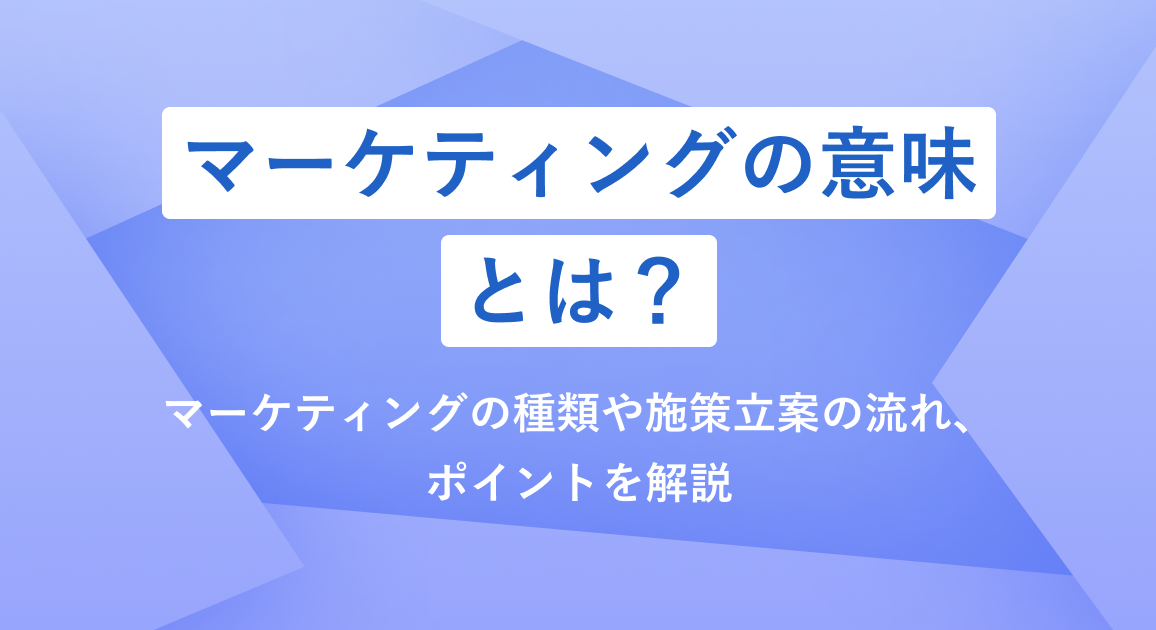
マーケティングとは、商品やサービスが売れる仕組みを作ることです。自社の商品やサービスを多くの顧客に購入してもらうためには、効果的なマーケティングが欠かせません。
本記事では、マーケティングの正しい意味や種類、施策を考える際の基本的な手順とポイントをわかりやすく紹介します。
マーケティングでの活用メリットをご紹介
マーケティングの意味は?

まずは、マーケティングの概要や、一般的な販売やセールスとの違いについて見ていきましょう。
マーケティング=顧客が買いたくなる仕組みを作ること
マーケティングとは、商品やサービスが売れる仕組みを作ることです。
どれほど素晴らしい商品やサービスでも、顧客に存在を知られていなければ売ることはできません。また、顧客に知られても、顧客が必要と感じなければ売れることはないでしょう。
マーケティングの一連の活動は、以下の流れです。
- 顧客のニーズをつかむ
- ニーズのある顧客に商品を知ってもらう
- 商品やサービスが顧客のニーズをどう解決するのかを示す
- 顧客が買いたくなるようなアプローチを行う
商品の提供によって顧客のニーズを満たすとともに、企業の利益を拡大していくことがマーケティングの理想とする形です。
マーケティングとセールスの違い
マーケティングとセールスは、働きかける方向が違います。
セールスとは、商品を売ることを目的に顧客に対してこちらから商品を提案し、売り込みなどの働きかけを実施することです。
一方、マーケティングでは、販売活動を行わずとも顧客が自らの意思で購入するように促します。
マーケティングの「商品やサービスが売れる仕組み」とは、顧客が起点となって商品を購入すべく行動してくれるように促すことです。
マーケティング | セールス |
・商品やサービスが売れる仕組みを作る ・顧客が自らの意志で購入する | ・企業側からアプローチして商品を提案し売り込む |
マーケティングの種類
マーケティングには、主に以下の3種類があり、顧客へのアプローチ方法がそれぞれ異なります。
- マスマーケティング
- ダイレクトマーケティング
- インバウンドマーケティング
それぞれ見ていきましょう。
マスマーケティング
マスマーケティングは、不特定多数の顧客に対して行うマーケティングです。
テレビ・新聞・雑誌などのいわゆるマスメディアを介して、商品やサービスを訴求します。
商品やサービス、自社のことを不特定多数の人に知ってもらい、認知度を向上させたい場合に用いられます。また、多くの人が利用対象になるBtoC商材においても効果的な方法です。
多くの人にアプローチできますが、一方で金額は高額になりがちです。
ダイレクトマーケティング
ダイレクトマーケティングとは、ターゲットを定め、直接的に商品やサービスを訴求する方法です。
具体的には、メール、SNSなどを通じたプロモーションや、テレビショッピングやダイレクトメール、インターネットショッピングなどが、ダイレクトマーケティングに該当します。
ある一定の条件に該当する顧客に対して商品やサービスを訴求するため、ニーズに沿った訴求が可能となり、顧客からの信頼感を得やすい点が特徴です。
また、費やした費用に対してどれだけの効果があったかが測定しやすい点も、ダイレクトマーケティングのメリットです。PDCAを回して施策の改善も素早く行えます。
特にメールやSNSといったデジタルを活用する手法では、顧客の反応をリアルタイムにデータで測定し、費用対効果を見ながら予算を有効に活用できます。
インバウンドマーケティング
インバウンドマーケティングは、直接的に商品やサービスを購入してもらうよう訴求するのではなく、顧客自身に自社の商品やサービスを見つけてもらい、問い合わせや申し込みのアクションをしてもらえるよう仕向ける方法です。
例えば、検索サイトで顧客が自社サービスに関連(or関係)するキーワードを検索した際に、サイトが上位に表示されるように工夫するSEO対策や、顧客に興味を持ってもらえるようなコラムをオウンドメディアに掲載し、自社サイトに誘導するなどのコンテンツマーケティングが該当します。
インバウンドマーケティングの施策により自社にアクションを起こしてきた顧客は、すでに購買意欲が高い可能性がある点が特徴です。
マーケティング施策を考えるときの流れ

マーケティング施策を考えるときの流れは、次の通りです。
- 市場調査・環境分析を行う
- セグメンテーションとターゲティングを行う
- ベネフィットを見極める
- マーケティング戦略を策定する
- 効果測定と改善
それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。
1.市場調査・環境分析を行う
まずは市場や顧客の調査を行い、市場の規模や傾向、顧客のニーズなどを明らかにしましょう。
このような調査を環境分析といい、内部環境分析と外部環境分析の2つに分けられます。
内部環境分析とは自社の強みや弱みに関する分析手法です。一方で外部環境分析とは、市場や顧客のニーズ、競争状況、競合の特徴、などの外部の状況を分析する手法です。
これらはマーケティングプロセス全体に大きく関与するため、慎重に行う必要があります。
具体的な環境分析の手法は次の通りです。
PEST分析

PEST分析は、自社をとりまくマクロ環境を4つの領域で分析するフレームワークです。PESTという名称は、は「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の頭文字から取られています。
一見すると自社に関係のなさそうな要素であっても、影響が及ぶ可能性がある外部の環境を明らかにできます。
分析は、頭文字となっている政治・経済・社会・技術の領域ごとに行います。最近変化したもの、あるいは変わらない傾向などを要素ごとに把握すると、各領域の影響を踏まえた長期的な市場のトレンドがつかめます。
5F分析

5F分析は、業界内の5つの力関係を分析し、市場内の競争の激しさや収益性を明らかにする手法です。
5つの力関係とは「競合他社」「新規参入の脅威」「売り手の交渉力」「買い手の交渉力」「代替品の脅威」の5つを指します。
市場や業界そのものが魅力的かどうかや、参入や撤退の判断に役立つフレームワークです。
3C分析

3C分析とは、「Customer(市場・顧客)、Competitor(競合他社)、Company(自社)」の3つのカテゴリでマーケティングに必要な要素を洗い出し、自社のめざすべき方向性を探るためのフレームワークです。
最初に「Customer(市場・顧客)」を分析し、次いで「Competitor(競合他社)」、最後に「Company(自社)」の順で分析を進めます。
これにより、顧客に対して自社が提供できる価値が何かを大まかに明らかにできます。
SWOT分析

SWOT分析は、内部環境と外部環境を 「Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)」の4つの観点で整理し、自社の立ち位置や強み、改善すべき点を洗い出すフレームワークです。
4つの観点を整理したのち、強み・弱みと機会・脅威をかけ合わせることで、より具体的な4つの戦略が導き出せます。
例えば、「Strength(強み)」と「Opportunity(機会)」では、市場の機会に対して自社の強みを生かす積極的な戦略を考案する、という具合です。
2.セグメンテーションとターゲティングを行う
市場の環境と自社の状況が把握できたら、次にマーケティングの対象とする顧客を設定します。そのためには、まずセグメンテーションを行います。
セグメンテーションは、対象となる市場の顧客を属性などで分類する作業です。BtoBであれば、業種・業態、売上規模、社員数、地域などで顧客を分類するのが一般的です。
セグメンテーションが終わったら、自社の強みや競合分析を基にマーケティング施策を展開するターゲットを絞り込みます。
アプローチすべき対象を絞り込むことでより顧客のニーズにマッチし自社の強みを生かせるため、効果的な戦略を立てることが可能です。
3.ベネフィットを見極める
ターゲットが定まったら、ターゲットのニーズに対して商品やサービスのどのような価値を訴求するのかを決定します。
商品やサービスにはさまざまな特徴や機能があります。その中から、ターゲットとなる顧客層にとって、最も価値があるもの(ベネフィット)が何であるかを見極め、訴求の中心とします。
また、市場で競合に負けないためには、自社の差別化ポイントを打ち出すことも欠かせません。違いを出しやすいものとしては価格を下げる方法があります。しかし、値下げは他社も簡単に追随できる施策であるため、慎重に行う必要があるでしょう。
価格や品質、機能性の高さに加え、顧客との接点の多さなど、自社の強みを生かした差別化が大切です。
マーケティング戦略を策定する
ターゲットと価値提案が定まったら、実際にどのように顧客に訴求を行うかを決定します。これには、4Pといわれるフレームワークの活用が有効です。
4Pとは、次の4つです。
- Procuct(商品・サービス)
- Price(価格)
- Place(流通・場所)
- Promotion(販促方法)
シンプルにいうと、4Pとは、何を、いくらで、どこで、どのように売るか、です。
先の工程で分析した対象となる顧客とベネフィットに基づき、それぞれの4つの要素を満たしていくことで、効果的な戦略を見いだすことができます。

4.効果測定と改善
施策を決定し実行したら、効果測定と改善も忘れないようにしましょう。
戦略の策定(Plan)、実行(Do)、効果測定と分析(Check)、改善(Action)の4要素からなるPDCAサイクルを繰り返すことが、マーケティング成果の最大化につながります。
より良い検証のためには、売り上げなどのゴールとなる指標だけではなく、売り上げに影響を与える成約率や、商談した顧客数、商談設定率なども効果測定できるようにしておくことが大切です。
細かい要素を収集・分析し、次の施策の効果がより高まるようブラッシュアップできます。
マーケティング施策を考えるときに大切なポイント

続いて、効果の高いマーケティング施策を考えるために押さえておくべき4つのポイントを紹介します。
ターゲットに合わせた施策とメッセージ
マーケティング施策は、ターゲットにあわせて設計しましょう。
顧客のニーズが多様化し、なおかつ情報があふれている現代では、誰にでも適用できるようなマーケティングを行ってもそれほど効果は期待できません。
顧客に選ばれる商品・サービスとなるためには、ターゲット一人ひとりのニーズに合わせた施策を講じることが大切です。
また、ターゲットに合わせた戦略は顧客となる見込みの低い層へのアプローチを回避できるため、不要なコストの発生も抑えられます。
不要なコストがでなければ、その分新たなマーケティング施策を実施できるため、効率的なマーケティングサイクルが確立できるでしょう。
顧客データの活用
セグメンテーションやターゲティングは、顧客データに基づいて実施することが重要です。
顧客データが適切に管理されていれば、自社の顧客傾向の分析を行うことができ、より精度の高いターゲティングが可能となるでしょう。
さらに、実施した施策の打ち手や結果を顧客ごとに保存しておけば、施策の改善スピードを高められるだけでなく、よりパーソナライズした戦略の立案につなげられます。
顧客データを管理し、特に自社の商品に必要な情報はデータとして持っておけるようにしておきましょう。
顧客へのフォローアップ
マーケティング施策を実施する際は、あらかじめ顧客のフォローアップ体制を整えておくことも大切です。
施策に対して顧客から反応があった際にすぐ対応できるようにしておかないと、せっかくのマーケティング施策が無駄になってしまいます。
フォローアップの対応が良ければ、契約の見込みが高まったり、自社のファンとなってくれる可能性が高まり、企業利益の拡大が期待できるでしょう。
ツールの活用
顧客データの管理やマーケティング施策の実施に当たっては、MAやSFA、CRMなどのツールの活用も検討しましょう。
主なツールと特徴は次の通りです。
- MA
顧客の行動の予測に基づいて自動化されたマーケティングを実施する
- SFA
営業活動の効率化や商談などのデータの管理・分析をサポートする
- CRM
顧客情報の管理と顧客との関係強化を目的として情報の管理を行う
いずれもマーケティングの効率化、成果向上に大きく貢献するツールです。
まとめ
マーケティングとは、商品やサービスが継続的に売れる仕組みを作ることです。顧客のニーズをつかみ、顧客にあった訴求や手法でアプローチすることで、継続的に顧客から求められる仕組みを作れます。
なお、効果的なマーケティングの実行には顧客データの活用が不可欠です。営業DXサービスの「Sansan」は、最新の顧客情報をクラウド上で一元管理し、商談情報を組織内で共有できます。また、MA、SFA、CRMとの連携もできるため、マーケティング施策の実行に大きく貢献します。
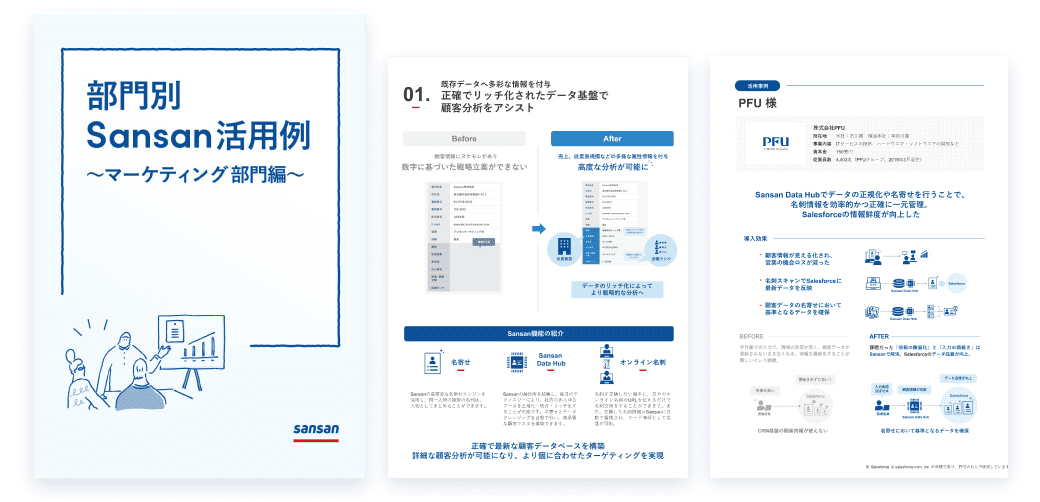
部門別Sansan活用例
〜マーケティング部門編〜
Sansanを全社でご利用いただくと、マーケティング部門でどんなメリットを感じるか、具体的にイメージしやすくなる資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部