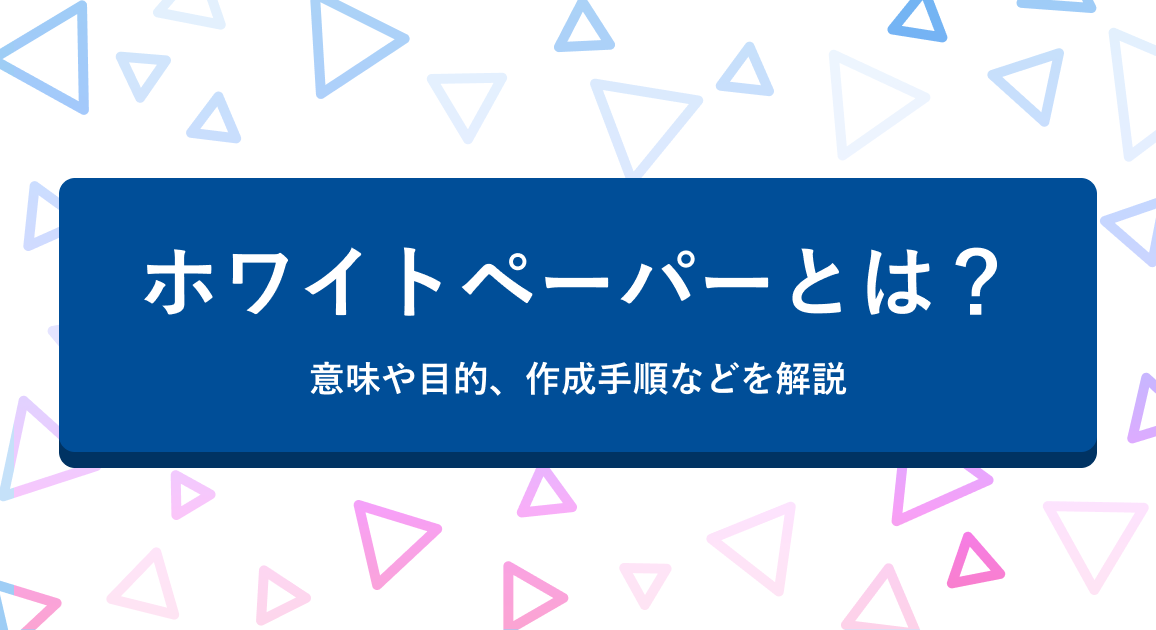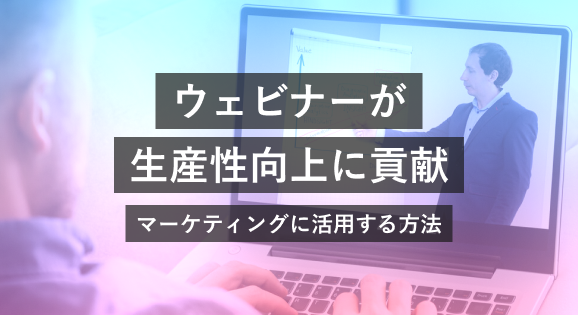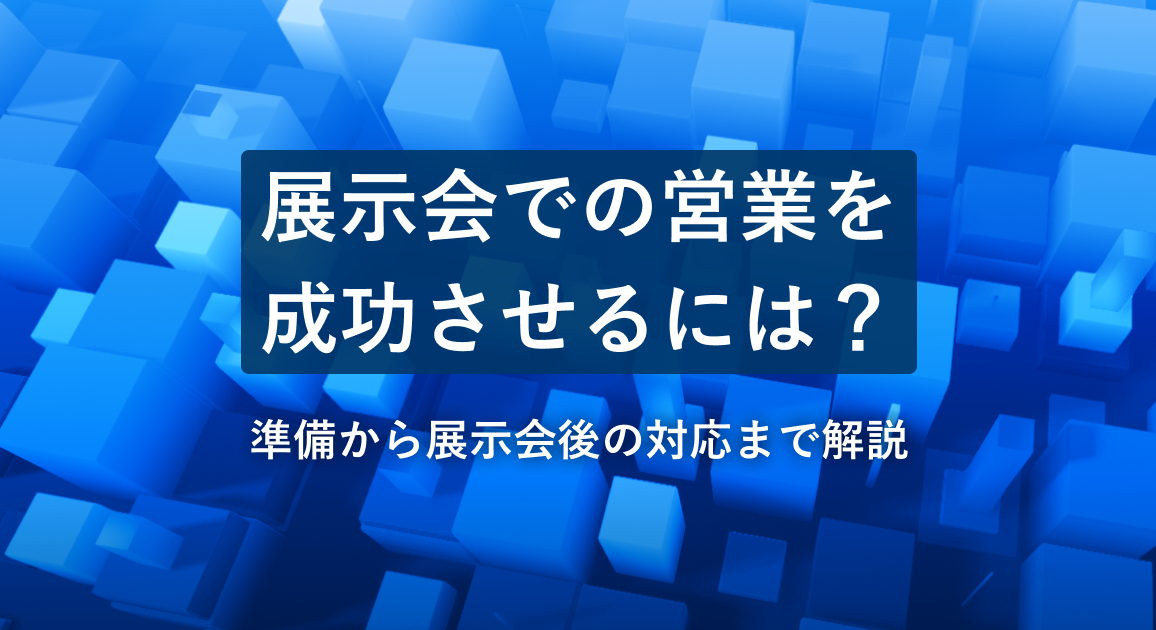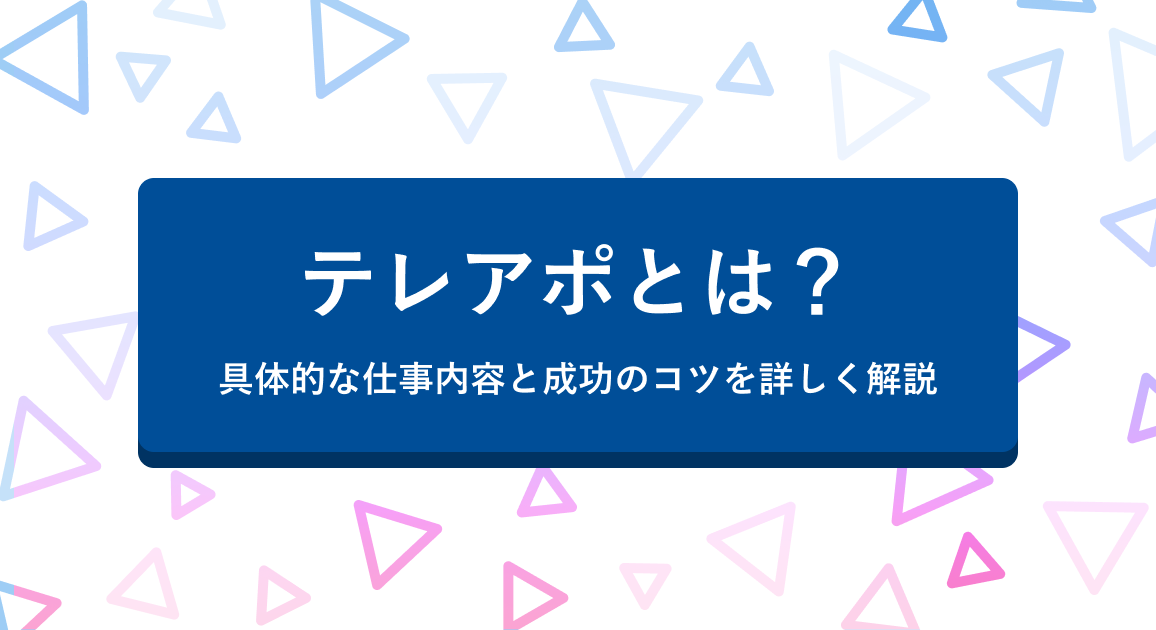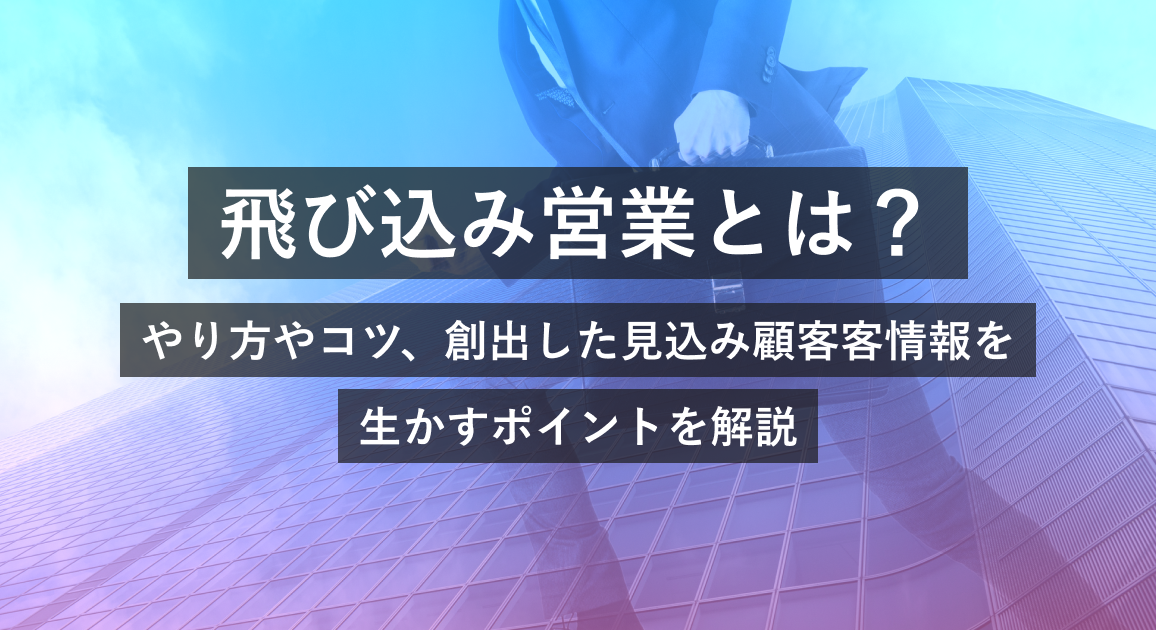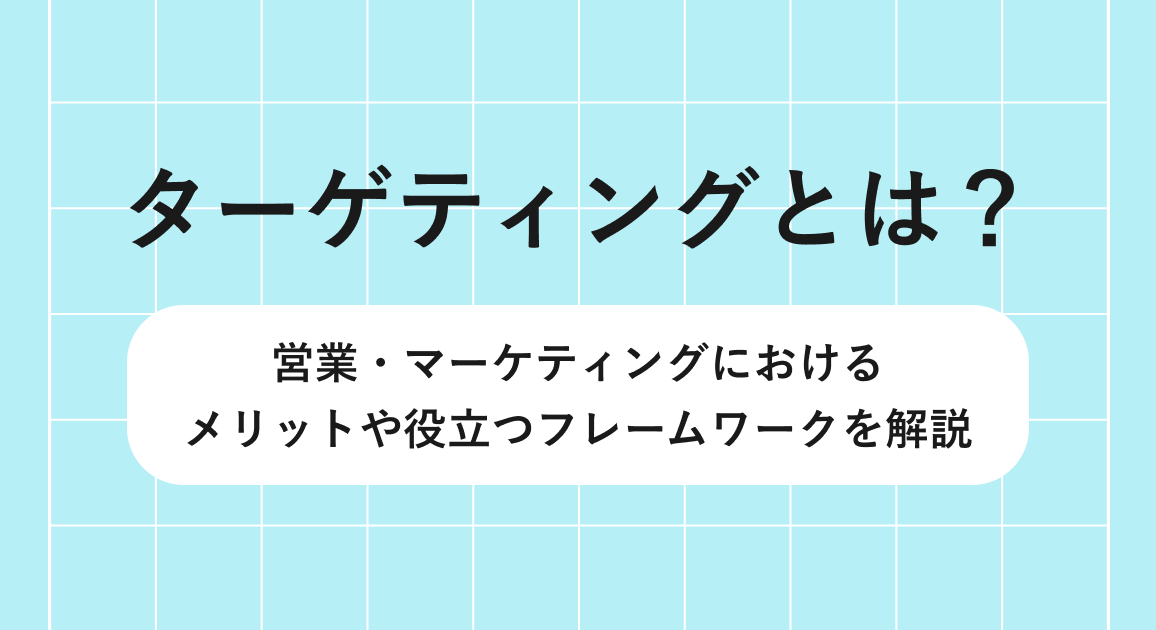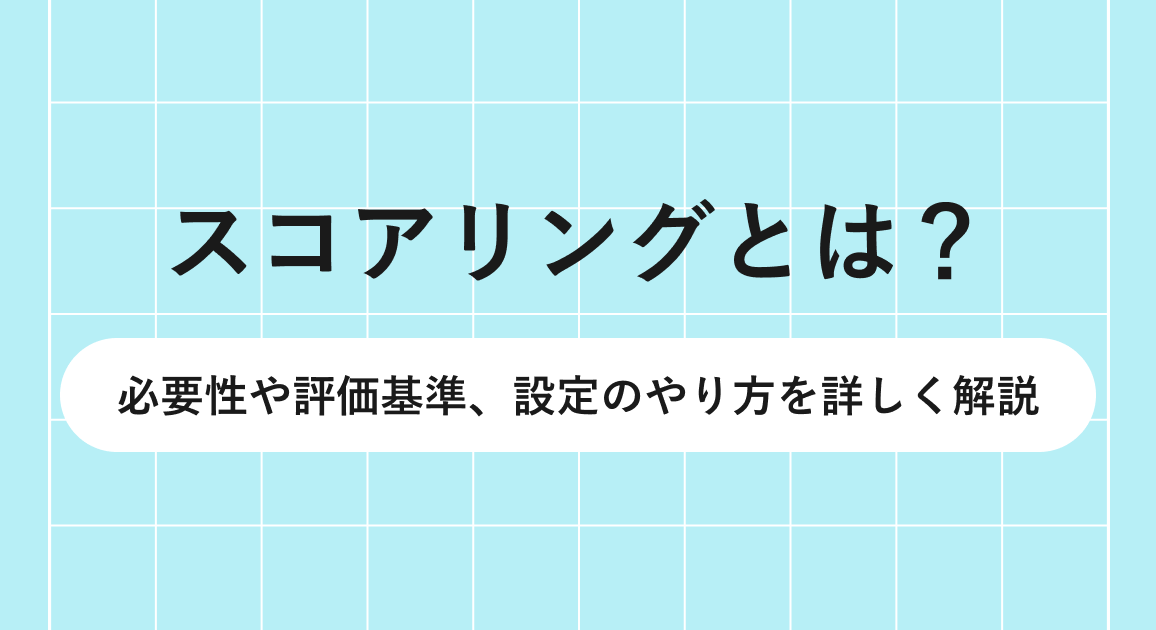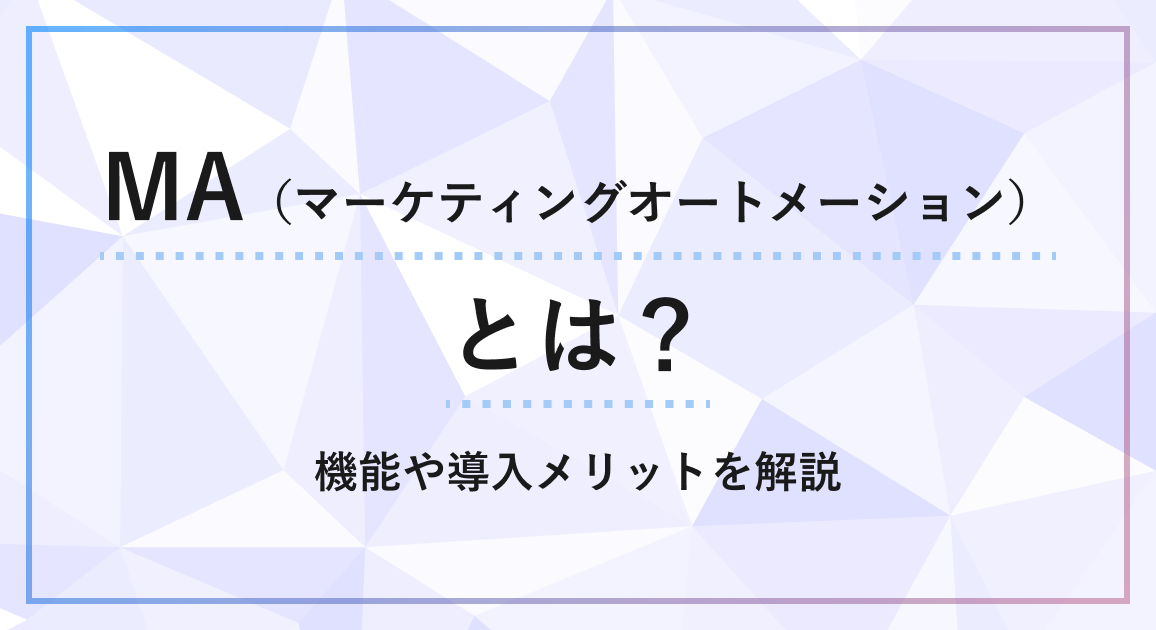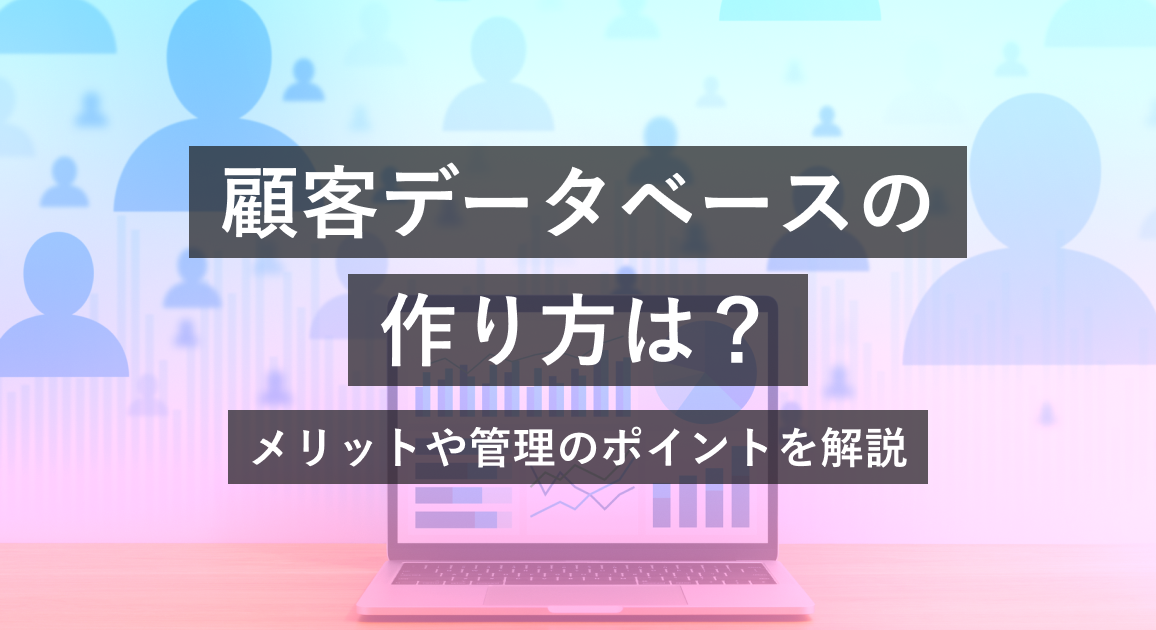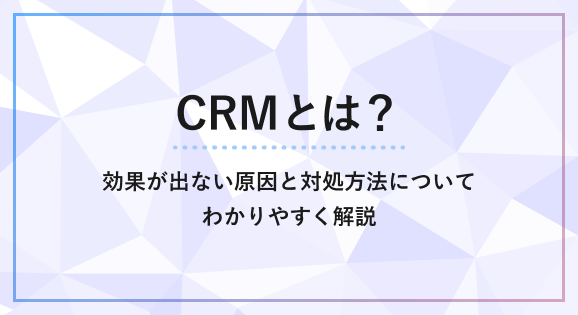- マーケティングノウハウ
BtoBのリード獲得手法12選|ポイントや活用方法も解説
公開日:
更新日:
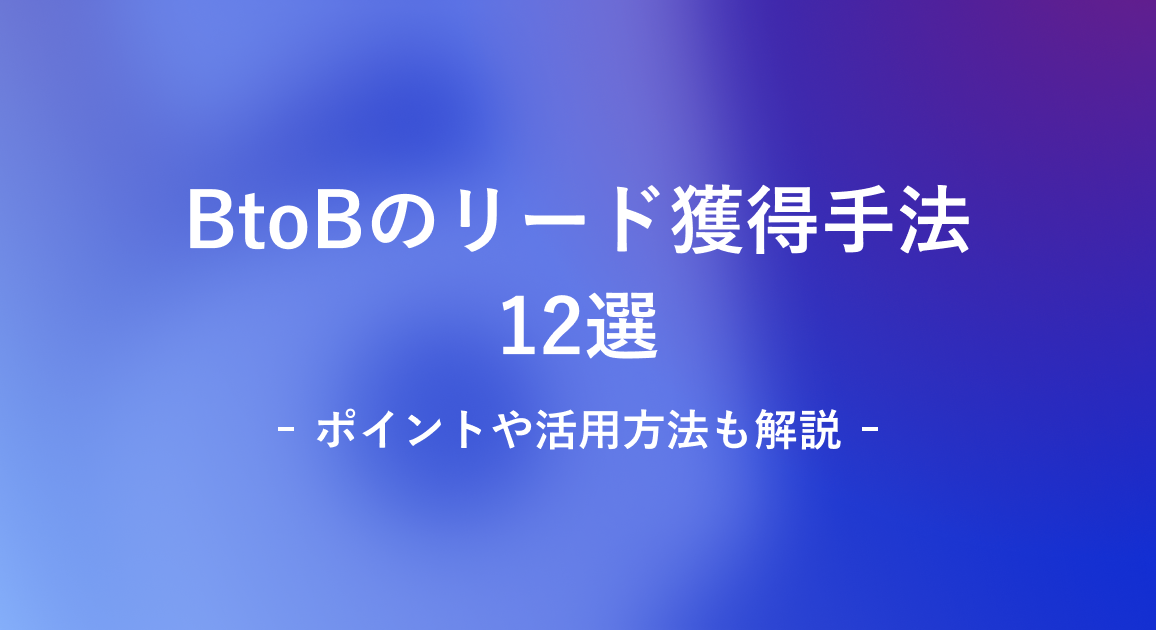
リード獲得(リードジェネレーション)は、見込み顧客情報を集めるプロセスであり、BtoBビジネスにおいて不可欠な要素となっています。リード獲得のアプローチの仕方はBtoBとBtoCで異なるため、BtoBに適した施策を講じる必要があります。
本記事では、BtoBにおけるリード獲得の手法や成功のポイント、獲得したリードの活用方法について詳しく解説します。
リード育成の課題を解決する
BtoBにおけるリード獲得とは

BtoBにおけるリード獲得(リードジェネレーション)とは、見込み顧客の個人情報(会社名・担当者名・部署・役職・メールアドレスなど)を収集することを意味します。「リード」は、企業の製品やサービスに興味を持ち、将来的に購入や取引につながる可能性のある顧客を指します。
ここでは、BtoBにおけるリード獲得の目的と、BtoCにおけるリード獲得との違いについて解説します。
BtoBでリード獲得をする目的
リード獲得は、見込み顧客と接触したあと、接点が生まれたユーザーから顧客情報を獲得するプロセスです。そのため、BtoBのリード獲得の目的は、大きく「顧客との接点をもつこと」と「顧客情報の獲得」の二つといえます。
接点構築のための施策には、SEO・SNS運用・広告運用などがあり、顧客情報の獲得の施策としては、問い合わせ数を増やすためのEFO(入力フォーム最適化)やメルマガの登録を促すなどの施策があります。
リードを獲得したあとは、リードナーチャリング(見込み顧客の購買意欲醸成)を行い、最終的に自社商品やサービスの販売促進につなげます。
BtoCでのリード獲得との違い
BtoB(企業間取引)とBtoC(企業消費者間取引)のリード獲得には、いくつか違いがあります。
まず、BtoBは企業同士の取引が主体であり、ビジネスプロフェッショナルや専門家が対象です。意思決定には複数のステークホルダーが関与し、購買プロセスは通常長く複雑であるため、BtoBのリード獲得には顧客ニーズの深い理解が必要です。
一方で、BtoCでは個人消費者が対象であるため、購買プロセスは迅速で直感的な傾向があります。BtoCの場合、戦略やコミュニケーションチャネルも異なり、価格や感情、個人の好みやライフスタイルに基づいた施策が求められます。
そのため、BtoBとBtoCのリード獲得戦略は異なるアプローチを採ることが一般的です。
代表的なBtoBのリード獲得手法12選

BtoBのリード獲得にはさまざまな手法がありますが、特に効果的な12種類の方法を紹介します。
オンライン施策
消費者の購買行動の変化にともない、オンライン環境では制約が少なく、全国規模で顧客にリーチできるメリットがあります。
具体的なオンライン施策として、以下があげられます。
- ホワイトペーパー
- ウェビナー
- 比較サイト(リードジェネレーションサービス)
- プレスリリース
- Web広告
- オウンドメディア(コンテンツSEO)
- SNSマーケティング
一つずつ解説します。
1. ホワイトペーパー
ホワイトペーパーとは、自社の商品・サービスに関する詳しい情報や導入事例、市場分析、ノウハウといった見込み顧客にとって役立つ情報をまとめた資料です。
見込み顧客が自社サイトやオウンドメディアからホワイトペーパーをダウンロードして資料請求する際に、企業名や担当者名、メールアドレスといった情報をフォームに入力してもらうことで顧客情報を獲得します。
BtoBビジネスでは導入までの比較検討期間が長くなるため、業界や製品に関する深い情報を提供するホワイトペーパーは、専門的な見込み顧客を引きつける効果的な手法といえます。
2. ウェビナー
ウェビナーとはWebとセミナーをかけ合わせた言葉で、「Webセミナー」や「オンラインセミナー」と呼ばれることもあります。
専門的なトピックに焦点を当てたウェビナーは、オンラインでの知識共有と顧客との双方向のコミュニケーションを促進できるため、BtoBでのリード獲得に適した方法です。
例えば、製造業向けのウェビナーでは最新の製造技術や業界の動向を解説し、参加者が質問や意見を共有できる場を提供します。これにより、業界専門家や意思決定者との有益な交流が生まれ、製品やサービスに対する関心を高めることが期待されます。
3. 比較サイト(リードジェネレーションサービス)
比較サイトやリードジェネレーションサービスは、BtoB向けのシステムやツールなどを紹介し、他社製品との比較や口コミを閲覧できるプラットホームやサービスです。
自社製品やサービスをほかの競合と比較する情報は、購買検討中の見込み顧客にとって注目度の大きい情報です。BtoB向けの比較サイトを活用することで、ターゲット層に自社の優位性をアピールする際に役立ちます。
また、比較サイトでは消費者からのレビューや評価も掲載されるため、良い評価を得ることで信頼性を高められる点もメリットです。
4. プレスリリース
プレスリリースは、新しい商品やサービスの情報、調査結果、お知らせなどを発信する手法です。新しい製品情報や、企業提携、成果などの重要な情報をプレスリリースとして公開することで、業界関係者やメディアを通じて注目を集められます。
BtoBのリード獲得における例として、ソフトウエア企業が新しい製品を発表する場合、専門的なITメディアに対してその製品に関するプレスリリースを行うといった方法があります。これにより、業界内での注目を喚起し、関連企業や専門家からの問い合わせや興味を引き出すことが期待できます。
プレスリリースを公開する際には、製品の特徴や利点を具体的に記載し、顧客がその価値を理解しやすい形で伝えることが重要です。
5. Web広告
Web広告(デジタル広告)とは、インターネット上で広告を表示するための手段です。ターゲットとなる業界や関連業種に効果的なオンライン広告を展開することで、見込み顧客からの認知・リード獲得の機会を創出できます。
例えば、クラウドサービスを提供する企業が業界向けのWeb広告を展開する場合、業界専門のオンラインプラットホームや専門メディアに広告を掲載することも一つの方法です。これにより、ターゲットとなる企業やプロフェッショナル層に向け、サービスの特徴や利点を訴求し、リードの興味を引き出すことにつながるでしょう。
6. オウンドメディア(コンテンツSEO)
オウンドメディアマーケティングとは、企業やブランドが自身のメディアチャネルを活用して、自社の情報やコンテンツを発信し、顧客との関係を構築するマーケティング手法です。
BtoBのリード獲得でオウンドメディアが役立つ理由は、専門的な業界情報や製品の使い方、成功事例を自社のブログやWebサイトで提供することで、業界関係者や検討中の企業に対して信頼性を構築し、興味を引き出すことができるためです。
なお、オウンドメディアでは顧客が検索するキーワードによって、「認知」から「比較検討」段階まで、幅広い層に向けた情報発信が可能です。そのため、リード獲得のあとのリード育成(リードナーチャリング)としても活用できる手法です。
7. SNSマーケティング
SNSマーケティングは、FacebookやInstagram、X(旧:Twitter)などのソーシャルメディアを活用して商品やサービスを宣伝し、顧客とのつながりを築くマーケティング手法です。
BtoBでのリード獲得の具体的な施策として、企業アカウントにて専門的な情報や業界トピックをSNSを通じて発信することや、SNS広告の出稿があげられます。
SNSマーケティングの利点は、低コストで効果的な広告を行えることです。テレビや新聞広告などの従来の広告手法に比べて、SNSマーケティングは費用が抑えられます。
ただし、BtoBの業界や商材の特性によっては、ターゲットとする企業担当者がSNSで情報収集していないケースも想定されます。そのため、ターゲット層のSNS利用状況を正確に把握し、どのプラットホームが有効かを分析する必要があります。
オフライン施策
オフライン施策は、直接的な対話や交流を通じてリードを獲得するアプローチです。BtoBのリード獲得手法として、次の5種類をご紹介します。
- セミナー
- 展示会
- テレアポ
- 飛び込み営業
- DM
8. セミナー
専門的なトピックに焦点を当てたセミナーを開催し、専門家や意思決定者を対象にしたリード獲得を図る方法です。特定のテーマやトピックに関心のある人々を集められるため、専門性の高いBtoBの領域でリードを獲得する可能性を高められます。
例えば、ITセキュリティー企業がセキュリティー対策の最新トレンドに焦点を当てたセミナーを開催した場合、セキュリティー担当者や情報システムマネジャーなど、関連業界の専門家の参加を促進できます。セミナーを通じて、参加者との直接的な対話や情報共有を行うことで、リードを獲得しやすくなります。
9. 展示会
業界の展示会やイベントに参加し、自社の製品やサービスを積極的にアピールすることで、リード獲得が期待できます。
展示会では直接的な対面機会が得られるため、製品やサービスに興味を持った潜在顧客と直接対話する機会を得られます。また、ブースでの説明を通じて、製品の特徴や利点を視覚的に伝えることで、印象深いコミュニケーションも可能です。
BtoBにおける展示会実施例として、製造業向けの展示会で新しい製品をデモンストレーションすることで、来場者が製品の性能や利点を直接体験し、質問や意見を交換する機会が増え、リードとなる企業担当者との関係構築が進むといった活用方法があります。
10. テレアポ
テレアポ(テレホンアポイントメント)は、電話を使用して新規の顧客を開拓し、商談やアポイントメントを獲得する手法です。リードに対して販促活動を行う「テレマーケティング」とは異なり、リード獲得を目的としています。
直接的で個別の対話が可能なテレアポは、顧客のニーズや課題に対応しやすく、企業ごとに課題やニーズの異なるBtoBの分野で活用しやすい手法です。
11. 飛び込み営業
飛び込み営業とは、事前のアポイントなしで企業を訪問する営業手法です。リード獲得方法として古くから採用されている手法であり、相手の反応や質問に直接的に対応でき、その場でフィードバックを得ることができます。
ただし、突然訪問することからあまり良い印象を抱かれないことが多いことや、営業担当者個人のスキルに成果が左右されやすいというデメリットがあります。
飛び込み営業は、オンラインを通じた情報収集をしていない企業へのアプローチや、対面で説明するほうが魅力が伝わりやすい商材の場合には有効な手法といえます。
12. DM
DM(ダイレクトメール)は、企業が直接郵送やメールなどの手段で、顧客や見込み顧客に製品やサービスに関する情報を提供するマーケティング手法です。。
定期的にDMを送付することで、企業の存在感を継続的にアピールできます。
また、特定のリンクや返信用の手段をDMに組み込むことで、反応を追跡しやすくなります。これにより、リードの関心や動向を把握しやすくなります。
BtoBのリード獲得を成功させるポイント

BtoBのリード獲得に役立つ手法は多数ありますが、これらの施策を実施するだけで成功するわけではありません。ここではBtoBのリード獲得を成功させるポイントについて解説します。
目的の明確化
まずは、リード獲得の目的を明確に定義することが不可欠です。達成したい具体的な成果や期待する収益を設定したうえで、リード獲得のための戦略を構築しましょう。目的がはっきりしていることで、チーム全体が一貫性を持って施策を実行できるようになります。
目的を明確にすることで、施策の成功評価も行いやすくなります。目標を達成できたかどうかを定量的かつ定性的な視点で評価し、必要に応じて戦略の修正を行いながら進めることで、成果の最大化につながるでしょう。
綿密なターゲット設定
BtoBのリード獲得は、ペルソナ設定やカスタマージャーニーマップを活用した慎重なターゲット設定が不可欠です。BtoBでリードへと転換したい相手を特定する際には、企業とその担当者の両方を考慮する必要があるため、具体的にどのような相手がリードとなるのかを詳細に検討し、リード獲得のターゲットを明確に定めることが求められます。
ペルソナを基にしたターゲット設定に加え、カスタマージャーニーマップの作成も重要です。カスタマージャーニーマップを活用することで、顧客が商品を認知してから購入までのプロセスが明確化され、統一感のあるリード獲得アプローチをチームや全社で共有できます。
さらに、3C分析を活用してターゲットを検討することもおすすめです。3C分析は「Customer」「Competitor」「Company」の観点から事業を分析する手法であり、自社の課題や競合状況を簡潔に把握する際に役立ちます。
効果検証・施策の絞り込み
リード獲得のための施策を実施したあとは、効果を定期的に検証し、データを分析することが重要です。どの施策が効果的であるかを把握し、不要な施策を絞り込むことで、リソースを最適化し、より効果的なリード獲得が可能になります。
効果検証のためには、事前に適切なKPI設定を行う必要があります。BtoBにおけるリード獲得のKPIの例として、「リード数」「商談数」「受注数」などがあげられます。
多くの施策を一度に実施すると費用が膨らみ、効率も悪くなります。そのため、目的やターゲットに対して効果が期待できる施策から順に実施し、投資対効果を高めることを意識しましょう。
BtoB企業が獲得したリードを営業に生かすポイント
BtoB企業がリードを獲得した際、そのリードを効果的に生かすことがビジネスの成否に直結します。ここでは、獲得したリードを営業活動に生かすためのポイントを解説します。
質の高いリードを選別して営業に渡す
リードの質を向上させるためには、量よりも質を重視することが不可欠です。獲得したリードの中から、潜在的なニーズや関心を持つ質の高いリードを選別しましょう。
質の高いリードを選別することで、営業チームは時間やリソースを最適に活用できます。特に、リードが商談に進む可能性が高い場合に優先的に営業に渡すことで、受注確率を向上させることが期待できます。
リードの選別の際には、蓄積したデータを分析し、企業の製品やサービスに本当に興味を持っている見込み顧客を明確に特定する必要があります。リードの質を判断するためには以下のポイントでの見極めが必要です。
- 企業の属性:企業規模や業種、従業員数、所在地など
- 個人の属性:担当者の所属部署や役職など
- 行動の履歴:Webサイトのアクセス履歴やイベント・セミナーの参加率など
リード選別のフェーズでは、上記のような条件をもとに「スコアリング」で購買意欲の高さを測る方法がよく用いられます。スコアリングとは、見込み顧客の属性や行動履歴、興味関心の度合いを数値化して計測し、熱量の高まりを点数で可視化する手法です。
スコアリングを高い精度で効率的に行うためには、MAツールが欠かせません。質の高いリードを営業に渡すためにも、ツールを効果的に活用しつつ、適切な基準や条件を設定しましょう。
リードに関する情報を社内で共有する
リード獲得後は、情報を迅速に社内で共有することがポイントです。特に、営業やマーケティング、カスタマーサポートなど、関連部門がリードに関する情報を把握しておくことは重要です。
顧客とのやり取りや過去の履歴、関心事などの情報を共有することで、営業担当者はより効果的なコミュニケーションを構築できます。これにより、リードがスムーズに商談に進みやすくなり、顧客体験も向上します。
こうした社内での情報共有を実施するためには、適切なツールが必要です。CRM(顧客関係管理)ツールや、顧客データベースを活用し、部署間でのリード情報の共有を行いましょう。これにより、リードへのアプローチの進捗に応じた適切な担当者の対応を実現しやすくなります。
インサイドセールスを活用したリードナーチャリングを実施する
獲得したリードがまだ営業に渡すべきでないと判断された場合、インサイドセールスを活用してリードナーチャリングを行うことが有益です。インサイドセールスとは、内部のセールスチームが顧客とのやり取りを担当し、興味を深めてから営業に引き継ぐプロセスです。
リードナーチャリングを通じて、見込み顧客との信頼関係を築きながら、製品やサービスについてより詳細な情報の提供を行いましょう。これにより、リードの購買意欲を醸成し、商談に進む際のハードルが低減します。
まとめ
BtoBにおけるリード獲得(リードジェネレーション)は、見込み顧客の重要な個人情報(会社名・担当者名・部署・役職・メールアドレスなど)を収集するプロセスです。
リード獲得はBtoBビジネスにおいて欠かせない要素であり、獲得したリードを営業に生かすためには、適切なツールやプロセスの導入、リード情報の適切な管理が求められます。
Sansanでは、名刺・フォーム入力・セミナー参加など、多岐にわたる顧客との接点から収集したリード情報を一元化し、営業活動をサポートします。これにより、顧客の最新状態を把握し、提案の質を向上させることが可能です。ぜひ、導入をご検討ください。
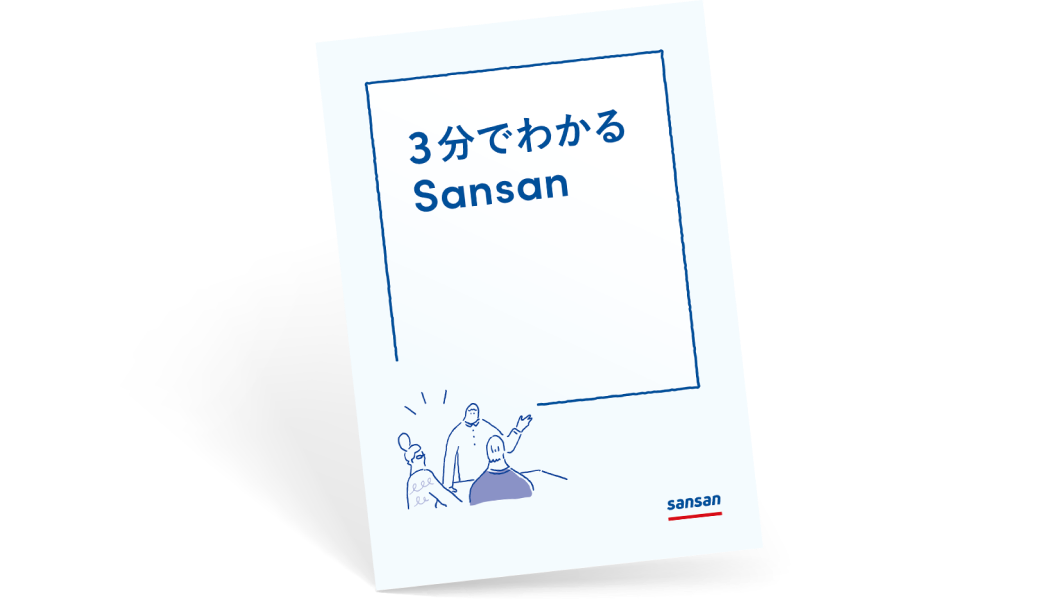
3分でわかる Sansan
営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部